MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2019.05.27
Medical Library 書評・新刊案内
仁志田 博司 編
髙橋 尚人,豊島 勝昭 編集協力
《評者》横尾 京子(広島大名誉教授)
今日の新生児医療の実践に不可欠な知識が詰まった一冊
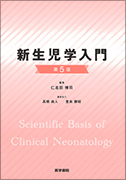 『新生児学入門』の初版から30年,数度の改訂を経て第5版が発行されました。もちろん,本書でも「日常の臨床で行っていることの科学的な理由を理解してもらう」という初版からの目的が貫かれており,表紙に配された英文タイトルでも「Scientific Basis of Clinical Neonatology」とうたわれています。大きく変わったのは,より進歩した新生児医療に応えるべく,髙橋尚人先生と豊島勝昭先生の両先生を編集協力として立てられ,さらに,新生児学各分野の専門の先生方が新たに執筆担当に加わったことです。本書は全22章から成り,2つに大別されています。1つは,新生児医療を支えるフィロソフィーと基本知識(第1~8章,第22章),もう1つは,新生児の適応生理と発達,および病態やその臨床(第9~21章)です。残すべき内容,加えるべき内容が吟味され,全体として第4版と同じ分量(432ページ)が維持されています。
『新生児学入門』の初版から30年,数度の改訂を経て第5版が発行されました。もちろん,本書でも「日常の臨床で行っていることの科学的な理由を理解してもらう」という初版からの目的が貫かれており,表紙に配された英文タイトルでも「Scientific Basis of Clinical Neonatology」とうたわれています。大きく変わったのは,より進歩した新生児医療に応えるべく,髙橋尚人先生と豊島勝昭先生の両先生を編集協力として立てられ,さらに,新生児学各分野の専門の先生方が新たに執筆担当に加わったことです。本書は全22章から成り,2つに大別されています。1つは,新生児医療を支えるフィロソフィーと基本知識(第1~8章,第22章),もう1つは,新生児の適応生理と発達,および病態やその臨床(第9~21章)です。残すべき内容,加えるべき内容が吟味され,全体として第4版と同じ分量(432ページ)が維持されています。
第1~8章は,これまでのように仁志田博司先生が執筆されており,新生児医療の考え方に一貫性が維持されています。加えて,新しい知見や方向性が重視され,第1章「新生児学総論」には新生児の薬物動態の特徴,第2章「発育・発達とその評価」にはフォローアップが追加され,第22章として「災害と新生児医療」が新設されました。一方,第3章「新生児診断学」から「検査結果の読み方」は省かれています。続く各章「新生児の養護と管理」「母子関係と家族の支援」「新生児医療とあたたかい心」「新生児医療における生命倫理」「医療事故と医原性疾患」では,仁志田先生作詩「新生児(あなた)に生きる」(巻頭p.ⅴ)をほうふつとさせ,新生児にかかわることの幸せの意味を知ることができます。
本書の後半もこれまで以上に洗練された構成と内容になっています。出生直後の適応生理が考慮され「体温調節と保温」の次に「新生児蘇生」「呼吸器系の基礎と臨床」「循環器系の基礎と臨床」と続きます。「新生児蘇生」は,第4版の「呼吸器系の基礎と臨床」から独立し章立てされたものです。そして「水・電解質バランスの基礎と臨床」「内分泌・代謝系の基礎と臨床」「栄養・消化器系の基礎と臨床」「黄疸の病態と臨床」「血液系の基礎と臨床」「免疫系と感染の基礎と臨床」「中枢神経系の基礎と臨床」「先天異常と遺伝」(本章は内容が一新されています)「主要疾患の病態と管理」と続き,いずれの章にも今日の新生児医療の実践に不可欠な知識やヒントが示されています。次版改訂の機会には,新生児のQOLを保証するためにも,「新生児の痛みの生理とケア」の記述が加わることを願っています。
助産や新生児看護をめざす若者や,新生児医療に従事する臨床家の皆さまが,あらためて日常ケアの科学性を解き明かすためにも,本書を活用されることをお勧めいたします。
B5・頁456 定価:本体5,800円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03625-2


インターライ方式ガイドブック
ケアプラン作成・質の管理・看護での活用
池上 直己,石橋 智昭,高野 龍昭 編
池上 直己,高野 龍昭,早尾 弘子,土屋 瑠美子,石橋 智昭,小野 恵子,阿部 詠子,五十嵐 歩 執筆
《評者》山田 雅子(聖路加国際大教授・在宅看護学)
病院でも,在宅でも,ケアの評価と質改善に活用できる
 インターライ方式は,自宅や施設で生活する要支援・要介護高齢者に多職種で提供するサービスの質を管理するために標準化されたツールです。病院では,看護診断や標準看護計画といったツールを用いて看護ケアの質を担保している例が多いかもしれません。しかし,患者が退院した後に介護保険サービスなど多職種チームで長期的な視野からケアを提供する場合には,院内で活用されている看護記録システムは役に立ちません。
インターライ方式は,自宅や施設で生活する要支援・要介護高齢者に多職種で提供するサービスの質を管理するために標準化されたツールです。病院では,看護診断や標準看護計画といったツールを用いて看護ケアの質を担保している例が多いかもしれません。しかし,患者が退院した後に介護保険サービスなど多職種チームで長期的な視野からケアを提供する場合には,院内で活用されている看護記録システムは役に立ちません。
家で過ごす高齢者は多様です。在宅ケアにかかわる看護師は一人一人の高齢者に対して,超個別な看護サービスを提供しているかもしれません。それにより利用者満足度は高いかもしれません。ですが,そのサービスの質が本当に高いかについては,おしなべて評価することができません。例えば,訪問看護ステーションの利用者のうち,褥瘡発生者の割合やその改善率,栄養状態の改善や排泄の自立に向けた達成度の算出などは難しい状況が続いています。ですが,いつまでもそれでよいわけではありません。
インターライ方式は,日頃から在宅ケアを利用する全ての高齢者のアセスメント,計画立案,モニタリングに使用すると,そのまま事業所の質管理指標としてデータ分析が可能となります。ケアマネジャーがインターライ方式を活用することによって,事業所ごとのケアの質を比較することができるでしょう。ケアマネジャーの多くが福祉職となった今,医療的な課題も含んだインターライ方式を活用することで,介護のみならず,最低限必要な医療に関する配慮について目を向けることができ,その対応の概要をケア指針から確認することもできます。
インターライ方式の特徴は,A~Vのセクションからなるアセスメント表に沿って高齢者の情報を入力すると,27種類のケア指針(Clinical Assessment Protocol;CAP)につながるようになっていることです。例えば失禁や皮膚の状態に特定の情報が入力されると,「CAP18.褥瘡」を検討することが必要だとわかります。インターライにこれまで積み重ねられたデータを活用して,コンピュータで解析された結果,その高齢者に必要なCAPを確認できるという仕組みに作り上げられています。
さて,ここまでは『インターライ方式ケアアセスメント――居宅・施設・高齢者住宅』(医学書院)という...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
