MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2017.11.13
Medical Library 書評・新刊案内
外科専門医受験のための演習問題と解説
第1集(増補版)・第2集
加納 宣康 監修
本多 通孝 編
《評者》山口 俊晴(がん研究会有明病院病院長)
簡潔にして要を得た,外科専門医試験合格のための書
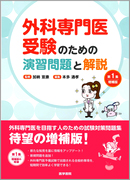 「簡潔にして要を得ている」という言葉が,本書にはぴったりと当てはまる。常に面倒なことは先送りして,土壇場になって徹夜で仕事を仕上げることが習いとなっているような受験者にはまさに待望の書である。もちろん,計画的に系統的に準備を着々と進め,自信を持って受験される方もおられると思うが,現場にある若手医師の多忙さはそれを必ずしも許さない状況にしている。
「簡潔にして要を得ている」という言葉が,本書にはぴったりと当てはまる。常に面倒なことは先送りして,土壇場になって徹夜で仕事を仕上げることが習いとなっているような受験者にはまさに待望の書である。もちろん,計画的に系統的に準備を着々と進め,自信を持って受験される方もおられると思うが,現場にある若手医師の多忙さはそれを必ずしも許さない状況にしている。
本書は外科専門医試験に合格するための書物である。著者たちはこれを活用しようとする受験者の現状を知り尽くしているだけに,なにより本書が「簡潔にして要を得ている」ことに留意して筆を進めている。「初版の序」に本多通孝医師のめざすところが,明快に書かれているので本文の前にぜひお読みいただきたい。
『第1集(増補版)』は2013年に刊行された『第1集』を,最新の内容にアップデートし,主に基本問題とその解説を簡明に加えてある。解説は短いが冗長な言葉をそぎ落とし,しかも重要な点はきっちりと盛り込まれており,無駄がない。写真や図もサイズは小さめだが,驚くほど鮮明なものが使用されており,記憶に残りやすい。最後のほうに,試験直前に時間が十分取れない読者のために,448に及ぶチェックリストが添えられているが,これが秀逸な出来である。外科専門医試験の合格という,最終のゴールに到達するためのダメ押しの部分であり,重要なポイントばかりである。
 『第2集』の演習問題と解説は,最近の試験問題では比較的新しいエビデンスに基づいたものもみられるようになったことに対応するために,新たに刊行された。前半は模擬試験として,実際の試験の雰囲気に慣れるためにも作られたもので,『第1集(増補版)』を終えた後に挑戦するようになっている。さらに,後半では分野別に,やや難易度の高い問題を掲載しており,これらの問題に挑戦することによりさらに自信が深まる仕組みになっている。まさに「至れり尽くせり」である。
『第2集』の演習問題と解説は,最近の試験問題では比較的新しいエビデンスに基づいたものもみられるようになったことに対応するために,新たに刊行された。前半は模擬試験として,実際の試験の雰囲気に慣れるためにも作られたもので,『第1集(増補版)』を終えた後に挑戦するようになっている。さらに,後半では分野別に,やや難易度の高い問題を掲載しており,これらの問題に挑戦することによりさらに自信が深まる仕組みになっている。まさに「至れり尽くせり」である。
本書が成功している原因は,従来の型にはまった問題集を,いわゆる権威者が執筆したのではなく,まだ頭の柔軟な若手のトップランナーたちが,斬新なアイデアの下に作成したところにある。また,監修には小生が日頃より敬愛する加納宣康先生が熱意を込めて当たっておられ,本書をさらに信頼性の高いものにしている。
試験に合格するためばかりでなく,合格の先にあるものを意識して,本書が読者たちに活用されたときこそ,多忙の中執筆した著者諸氏の努力は報われると言えよう。
[第1集(増補版)]B5・頁308 ISBN978-4-260-02495-2
[第2集]B5・頁264 ISBN978-4-260-03045-8
定価:各本体5,000円+税 医学書院
菊地 臣一 編
《評者》飯塚 秀明(金沢医大教授・脳神経外科学)
脊椎・脊髄手術に臨む際に読破してほしい必須の書
 本書は,脊椎・脊髄疾患の外科治療を専門とする医師,およびそれを志す医師にとって,必須の書籍と思われる。編著者の菊地臣一先生が序文で述べているように,本書のコンセプトは,「脊椎・脊髄外科の臨床というart」と「解剖というscience」の統合と言える。言うまでもなく,あらゆる手術の基本は,外科医が局所解剖を正確に把握し,その上で病変に対する手術体位を含めた適切な到達方法の選択が肝要である。特に,脊椎・脊髄手術におけるこれらの重要性は論をまたないであろう。
本書は,脊椎・脊髄疾患の外科治療を専門とする医師,およびそれを志す医師にとって,必須の書籍と思われる。編著者の菊地臣一先生が序文で述べているように,本書のコンセプトは,「脊椎・脊髄外科の臨床というart」と「解剖というscience」の統合と言える。言うまでもなく,あらゆる手術の基本は,外科医が局所解剖を正確に把握し,その上で病変に対する手術体位を含めた適切な到達方法の選択が肝要である。特に,脊椎・脊髄手術におけるこれらの重要性は論をまたないであろう。
本書は,第1章で,まず「脊椎手術に必要な神経解剖」として,臨床解剖の重要性とそれに基づく神経症状の解説が述べられている。画像診断が格段に進歩したとはいえ,脊椎・脊髄手術に携わる外科医にとって,診断の基本は神経学的所見に基づく責任病巣の把握であり,このためにもこの第1章は,全ての脊椎・脊髄外科医にとって極めて参考となるものである。
続いて,頚椎,胸椎,腰・仙椎疾患に対する,各種の到達法と手術手技が詳細に解説されている。それぞれの到達法において,手術適応,手術体位の基本,皮膚切開,到達法が,豊富な局所解剖写真と共に,具体的にわかりやすく解説されている。脊椎・脊髄手術で用いられているアプローチがほぼ全て網羅されており,手技のステップごとに,詳細な局所解剖写真を用いて解説されている。胸椎での前方到達法では,胸腔ドレーンの挿入に関する留意点をも解説しており,実際の臨床現場で役に立つように工夫されている。さらに,腰・仙椎では,特殊な手技として,各種固定術や内視鏡下手術・腹腔鏡下手術まで11の手技について手技上の留意点やポイント等も含めて解説されている。本書の特徴として,各術式の解説の後に,エキスパートによるその術式におけるポイントや手術のコツ(Pearls and Tipsを含めて)が述べられており,それぞれが極めて参考になる。
編著者の菊地先生が,腰・仙椎の傍正中アプローチ(Wiltseのアプローチ)におけるコメントで述べている,「navigation systemの導入により,三次元的解剖の把握は容易になった。しかし,術者の頭の中に,局所での神経根と周囲組織との相互関係が入っているのといないのとでは,手術時間と合併症発生の危険が格段に違う」(p.126,下線評者)は,至言である。
本書は,この領域の専門医をめざす若手医師にとって,ぜひともアシスタントに入る前に読破することを望みたい。また,専門医として第一線で脊椎・脊髄疾患の外科治療に励んでいるベテラン医師にとっても,今一度,自分の手術手技を振り返るために参考とすることを勧めたい。
A4・頁196 定価:本体16,000円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03044-1
長田 道夫,門川 俊明 著
《評者》横尾 隆(慈恵医大教授・腎病理学)
病理医と臨床医の敷居が低くなる良書
 腎臓を専門とする医師のほとんどが臨床における腎病理の重要性を理解し,よく勉強している。腎生検のカンファレンスや学会中のレクチャーなどはいつもどこも満員である。ただ,自信を持って自分は腎病理が読めるという臨床医はほとんどいないのが現状である。なぜだろうか。やはり腎病理の特殊性があるからではないだろうか。例えば,腫瘍の生検を病理診断する時,悪性か良性かの判断が重要で,経過や病因はあまり関係なく,その場の病理所見で治療法も決定される。しかし腎病理の場合,単にスナップショットのみで判断するのでなく時間軸を勘案してどのような経過でこの病態となり,今後どのようになっていくと推察できるかという情報が病理報告に求められる。したがって,病理アトラスで典型像をいくら見て理解しても実際に読めないことが多いのであろう。つまり正確な診断には臨床医と病理医が歩み寄って情報を共有することが不可欠となる。しかし,これまで十分にそれがなされていたかはいささか疑問である。両者が集うカンファレンスや研究会でも経験の豊富な腎病理医がどのような思考回路で判断したか述べることなく難解な症例の結論を出すことがあり,それを臨床医が聞いてただ鵜呑みにして“やっぱり腎病理は奥が深くて入門しづらい”と思って終わることがよくある。病理医から臨床医への一方通行であり,両者の壁は厚くなるばかりである。
腎臓を専門とする医師のほとんどが臨床における腎病理の重要性を理解し,よく勉強している。腎生検のカンファレンスや学会中のレクチャーなどはいつもどこも満員である。ただ,自信を持って自分は腎病理が読めるという臨床医はほとんどいないのが現状である。なぜだろうか。やはり腎病理の特殊性があるからではないだろうか。例えば,腫瘍の生検を病理診断する時,悪性か良性かの判断が重要で,経過や病因はあまり関係なく,その場の病理所見で治療法も決定される。しかし腎病理の場合,単にスナップショットのみで判断するのでなく時間軸を勘案してどのような経過でこの病態となり,今後どのようになっていくと推察できるかという情報が病理報告に求められる。したがって,病理アトラスで典型像をいくら見て理解しても実際に読めないことが多いのであろう。つまり正確な診断には臨床医と病理医が歩み寄って情報を共有することが不可欠となる。しかし,これまで十分にそれがなされていたかはいささか疑問である。両者が集うカンファレンスや研究会でも経験の豊富な腎病理医がどのような思考回路で判断したか述べることなく難解な症例の結論を出すことがあり,それを臨床医が聞いてただ鵜呑みにして“やっぱり腎病理は奥が深くて入門しづらい”と思って終わることがよくある。病理医から臨床医への一方通行であり,両者の壁は厚くなるばかりである。
その中で,この『なぜパターン認識だけで腎病理は読めないのか?』は腎病理医の代表の長田道夫先生(筑波大)と臨床医の代表の門川俊明先生(慶大医学教育統轄センター)が会話形式で,病理医がどのような思考プロセスで症例を読んでいくのか解き明かしており,大変実践的な内容となっている。特に日頃聞きにくいような基本的な内容も門川先生が臨床医目線でどんどん聞いてくれるし,また答える長田先生も臨床医が知っていてほしいことや病理医でも意見が分かれる内容などもそのまま歯切れよく回答しているので,非常に読みやすくまた腑に落ちやすい。これから腎病理を専門とする病理医になりたい方には,ぜひまず初めに読んで腎病理医とし...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。


