MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2014.07.28
Medical Library 書評・新刊案内
栗原 照幸 著
《評 者》髙橋 昭(名大名誉教授・神経内科)
長年にわたる実地診療の経験からまとめ上げられた書
 本書は,1987年以来,名著として改版や増刷を重ねてきた『神経病レジデントマニュアル』を全面的に改訂増補した書である。本書について語るとき,先生のご経歴を素通りすることはできない。
本書は,1987年以来,名著として改版や増刷を重ねてきた『神経病レジデントマニュアル』を全面的に改訂増補した書である。本書について語るとき,先生のご経歴を素通りすることはできない。
著者の栗原照幸先生は,1967年に慶應義塾大学医学部を卒業,米国ECFMG(外国人医師卒業教育委員会)試験に合格,ワシントン大学バーンズ病院でインターン,神経内科レジデント。神経生理学リサーチフェロー,宮崎医科大学神経内科学助教授(教授:荒木淑郎先生),東邦大学内科教授を経て,現在東邦大学名誉教授,神経内科津田沼で神経内科の実地診療に従事しておられる,日本を代表するベテラン神経内科医のお一人である。米国の医学教育システムを日本に紹介,日本神経学会では卒後教育委員として医学教育,特に卒後の研修に情熱をもって当たられ,現在の専門医制度の導入に大きな力を発揮された。
このようなご経歴の持ち主の栗原先生が,長年にわたる神経内科の実地診療のご経験を基にまとめ上げられたのが本書であり,上記の前身の書から25年以上の歴史が光る。神経内科学を学ぶに当たっての栗原先生の信条は,本書の第1章に詳述されているので,まずはこの章を熟読してほしい。
本書は症候学や診断手法の詳細を記した一般の神経内科診断学書ではない。「神経学的診察」の章では,むしろ簡潔に診察の要点が述べられ,これに対して「問診」の比重が大きく,神経疾患の診断にはベッドサイドの診察とともに問診が重要であることが強調され,その具体的な指針が述べられている。
「神経学的診察」の章では,多くのオリジナルの写真と図を用いられており,初心者や学生にとっても理解しやすいあたたかい配慮が随所に見られる。
神経疾患患者の診察への第一歩は神経症候の理解と分析である。このことから,日常多く経験される主要な神経内科領域のcommon symptomや徴候として,意識障害・昏睡,頭痛,てんかん,めまい,認知症,不随意運動,便秘・排尿障害などの自律神経障害がそれぞれ独立の章として記述され,実際の診療に大変有用である。さらに,本書の大きな特徴は,これらの症候の治療の要点が的確かつ簡潔にまとめられていることである。例えば「不随意運動」の章では,まず概要の項で診察の仕方と発症機序などがまとめられ,それに続く項では,主要な不随意運動の治療の要点が述べられている。この著述方針は本書の基本をなすものであり,これら以外の神経疾患についても治療に主眼が置かれている。このため,読者は実際の治療に際し,本書をひもとけば,診断や治療の指針が得られる。また各薬剤の,有害事象,薬価,保険点数の問題点にまでも言及されており,患者の経済的負担を考慮して診療に当たるように警鐘が鳴らされている。これらは類書に見ることができない本書の特徴である。
日常診療で最も多く直面する「脳血管障害」「認知症」「パーキンソン病」の章では,最近の治療法の利点欠点をご自身の長年にわたる豊富な経験や考え方に立脚して記されており,参考になる点が多い。
「神経・筋疾患」の項は,栗原先生のご専門が発揮された圧巻ともいえる内容である。重症筋無力症,多発性筋炎,周期性四肢麻痺などは,特にその感が強い。
付録として,ベッドサイドの診察に加えて,電気生理学的検査,画像診断の解説があり,これらへのアプローチと診断的有用性が述べられている。
座右の書として診察室に常備されることをお薦めしたい。
A5・頁408 定価:本体4,300円+税 医学書院
ISBN978-4-260-01893-7


マリー・ダナヒー,マギー・ニコル,ケイト・デヴィッドソン 編
菊池 安希子 監訳
網本 和,大嶋 伸雄 訳者代表
《評 者》二木 淑子(京大大学院教授・生活機能適応学)
複雑な問題を抱える患者の心理療法にチームで取り組む
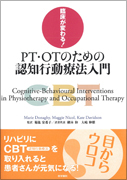 本書は,イギリスの心理学科,理学療法学科,作業療法学科,地域・病院のセラピストらにより執筆され,わが国の同職種チームにより訳された,認知行動療法の入門書である。
本書は,イギリスの心理学科,理学療法学科,作業療法学科,地域・病院のセラピストらにより執筆され,わが国の同職種チームにより訳された,認知行動療法の入門書である。
監訳者や執筆者の序に,多職種総心理士化ではなく,チーム医療にかかわる他の専門職の専門性の中に認知行動療法を取り込んで統合してもらうためのテキストとある。各自の治療の枠組みに認知行動的ストラテジーをどう取り込むかは,読者自身が読み取らなくてはならない。攻めて読む本といえる。
身体障害領域や地域・高齢者領域で仕事をしている,ある程度専門性が確立したセラピストの多くは,疾患による障害に対して従来の解釈では問題が解決しないことや,まずアウェアネス,自己洞察を深めるようなアプローチの必要があることに気付いている。なんとなく心理的問題にアプローチしないといけないとわかってはいても,心理療法はこうした入門書のガイドがないと登れない山である。
本書のPart 1(1-3章)では,非常にコンパクトに理論背景について解説してある。初期のオペラント学習理論のような行動療法に感情認知理論,論理情動療法などの認知療法が統合されて認知行動療法となる流れや,うつ病の認知モデルのキーコンセプト,認知行動療法の特徴(ソクラテス式質問法や認知的フォーミュレーションなど)の概説があり,次いで認知行動的アプローチをPT・OTになじみのある実践モデルに取り組むための解説がされている。
Part 2(4-11章)は,実践応用の各論であり,認知行動療法効果のエビデンスが高いうつ病,不安障害などの精神疾患だけでなく,慢性疼痛や線維筋痛症などに対するアプローチが,ケーススタディと共に解説されている。慢性疼痛例ではセラピストのボヤキにもしっかり応えてPT・OTの実践への取り入れ方のコツが書かれ,SMART(Specific, Measurable, Activity-related, Realistic, Time-related)なゴール設定など,認知リハビリテーションでもなじみの方法も紹介されている。
担当すると不思議に良くなるといった実践家は,無意識にここで紹介されている...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
