MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2012.10.15
Medical Library 書評・新刊案内
David A. Brent,Kimberly D. Poling,Tina R. Goldstein 著
高橋 祥友 訳
《評 者》山本 泰輔(防衛医大防衛医学研究センター・行動科学研究部門)
思春期・青年期患者の心理療法を扱う人々に広く読んでほしい一冊
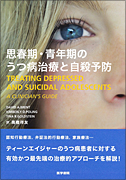 「死にたい」「生きているのがつらい」「気がついたら自傷(自殺未遂)に及んでいた」……,こうした若者が目の前に現れたときにどう接するかという問題は,教育現場にいる者,または心理療法,精神療法を担当する者にとっては,避けて通れない。こうした若者は,多くの場合,希死念慮の背景に多くの問題(精神疾患,社会スキルの未熟,経験の不足,不健康な人間関係など)を抱え,同世代のコミュニティから取り残され,それがさらに将来の適切な発達過程の機会を失わせるという悪循環の中にいる。このため,自殺予防としては,急性期には精神症状に対する治療,中長期的には成長を含む包括的な戦略が必要である。
「死にたい」「生きているのがつらい」「気がついたら自傷(自殺未遂)に及んでいた」……,こうした若者が目の前に現れたときにどう接するかという問題は,教育現場にいる者,または心理療法,精神療法を担当する者にとっては,避けて通れない。こうした若者は,多くの場合,希死念慮の背景に多くの問題(精神疾患,社会スキルの未熟,経験の不足,不健康な人間関係など)を抱え,同世代のコミュニティから取り残され,それがさらに将来の適切な発達過程の機会を失わせるという悪循環の中にいる。このため,自殺予防としては,急性期には精神症状に対する治療,中長期的には成長を含む包括的な戦略が必要である。
本書は,こうした急性期から中長期的に及ぶ問題点とその対処法について,具体的に,そして体系的に解説してくれている。個別のアプローチについては,患者とセラピストの実際のやりとりや有用なツールが例示されているので,それぞれ自分の扱っているケースで役に立つところを抜き出してそのまま使える。また,全体の大きな戦略について体系的に解説されており,これらをしっかり理解して実践することで,自分でケースを扱う際に,治療経過を論理的に把握し,患者と共有することを可能にしてくれる。連鎖分析による問題点や保護因子の把握,思考・感情・行動への効果的な介入といったスキルがわかりやすく解説されている。これら個別のアプローチ自体は特段新しいものではないが,体系的に理解することでこれらの組み合わせを戦略的に活用でき,また患者に説明・助言することができる。これにより,患者が抱えた問題の解決に向けて,セラピストと協力しながら,患者自身が努力し,多くを学んでいくことを可能にする。最終的に,患者が自分で健康的なサイクルへ復帰し,本来の軌道での生活を再開させることにつながる。
訳者の高橋祥友氏は,長年自殺予防に注力してきた日本を代表する精神科医である。その高橋氏のあとがきにも書かれている通り,上記にあるようなスキルの訓練を個人療法の場に統合することを本書は可能にした。米国の研究者による著作の翻訳であるため,日本での文化や会話形式にそぐわないところ(家庭に銃がある場合の保管法といった予防策が述べられていたり,患者とセラピストの会話で日本人にはピンとこない流れがあったりする)や,内容的に堅苦しいところもあるが,現実に自殺の危機にある若者と接している治療者にとって,本書は即実践可能なアプローチを提供してくれる。また,自殺予防に特化しなくても,これらの考え方は思春期・青年期患者の心理療法を扱う者にとって大いに応用し得る内容である。基本的には心理療法家,精神療法家を対象にした解説であるが,これらの体系的な理解は心に問題を抱える若者への支援に大いに役立つと思われ,それらにかかわる人々に広く読んでほしい一冊である。
A5・頁336 定価5,250円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-01556-1


神尾 陽子 編
《評 者》黒木 俊秀(肥前精神医療センター・医師養成研修センター長)
すべての精神保健医療関係者必携のマニュアル
 古参の精神科医の間では,いわゆるマニュアル本の類は価値が低いと見下す風潮がいまだにある。どうやら,30年前にDSM-IIIという文字通りのマニュアルが世界を席巻して以来,精神医学が薄っぺらになったという義憤を抱えているようだ。だが,DSM-III以前のわが国において,精神医学の基本と位置付けられていた,かのクルト・シュナイダーの『臨床精神病理学序説』も,元はといえば家庭医向けに書かれたマニュアル本ではなかったろうか。マニュアル本特有の薄さが,内容の厚みと相反する好例である。
古参の精神科医の間では,いわゆるマニュアル本の類は価値が低いと見下す風潮がいまだにある。どうやら,30年前にDSM-IIIという文字通りのマニュアルが世界を席巻して以来,精神医学が薄っぺらになったという義憤を抱えているようだ。だが,DSM-III以前のわが国において,精神医学の基本と位置付けられていた,かのクルト・シュナイダーの『臨床精神病理学序説』も,元はといえば家庭医向けに書かれたマニュアル本ではなかったろうか。マニュアル本特有の薄さが,内容の厚みと相反する好例である。
同様に本書も,そのいかにもマニュアル本らしいB5判・200ページほどの軽やかな装丁とは裏腹に,中身は驚くほど濃い。それも,昨今の精神科臨床において何かと話題になる成人の自閉症スペクトラム障害(ASD)の診療について,総勢30名ものわが国の第一人者が分担執筆した実践の「<1> まず本書が,優れた手引であるゆえんは,例えば,具体的な面接の要点を列挙した第章「特性に応じた面接の工夫」や第章「診断面接の進め方」であろう。第章「精神障害者保健福祉手帳用の診断書作成の注意点」や第章「成人の社会参加に向けて」の「主治医の意見書」のサンプルなども,支援にすぐに役立つ。 だが,本書をして傑出した実践の書たらしめているのは,なんといっても後半の症例編ではないだろうか。「面接で何と答えればよいのかわからない」「自分は何をやってもダメなんです」「社内での行動がおかしいと言われました」等々のタイトルを付けた症例について,各症例頁以内で,診断と治療方針をわかりやすく解説し,さらに診療のコツをコメントしたワンポイント・アドバイスが追記されている。一般の臨床医は,まず症例に目を通し,改めて解説編に戻っての診断概念や特徴を確認してみるのもよいだろう。症例の中には,特性を部分的に有するのみの診断基準閾値下例も含まれており,が提案しているのディメンジョン的概念が支援とリンクすることが示唆される。 本書を通読して感じる...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
