MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2009.05.11
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


上山 敬司,中川 克二 著
A4・頁96 定価3,360円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00788-7
《評 者》坂井 建雄(順大教授・解剖学)
実存する人体の構造を画像でいかに表現するか
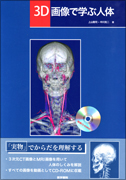 解剖図anatomical illustrationsには,ヴェサリウスの『ファブリカ』(1543)以来の長い歴史がある。木版画から始まり,16世紀後半から18世紀までの銅版画,19世紀のリトグラフと木口木版画を経て,20世紀の写真製版による解剖図に至るまで,印刷技術の発展は解剖図のあり方に大きな影響を与えた。
解剖図anatomical illustrationsには,ヴェサリウスの『ファブリカ』(1543)以来の長い歴史がある。木版画から始まり,16世紀後半から18世紀までの銅版画,19世紀のリトグラフと木口木版画を経て,20世紀の写真製版による解剖図に至るまで,印刷技術の発展は解剖図のあり方に大きな影響を与えた。
21世紀のコンピューターによる情報技術が可能にした驚異的な解剖図は,『プロメテウス解剖学アトラス』(医学書院,2007-2009)の中に見ることができる。人体のあらゆる構造について,理想の姿を追究して画像化したものである。基盤となる骨格の上に,筋,血管,神経,内臓,中枢神経などの構造が歪みなく積み重ねられ,さまざまな角度から描かれている。一つひとつの図に,誰かが描いたという人為を感じさせない,自然の表情が表現されている。アルビヌスの『人体骨格筋肉図』(1747)も,同様に理想の人体を追究した解剖図譜であり,銅版画による解剖図の最高傑作と目されている。解剖図の歴史については,拙著『人体観の歴史』(岩波書店,2008)を参考にしていただきたい。
人体解剖図の歴史には,理想の姿を求めるものと対極にあるもう一つの伝統がある。それは,実在する人体の構造を求めるものである。いくら詳細に描いたとしても,理想を追究すれば絵空事になってしまう。実際に存在するのは,個性豊かな一人ひとりの人間の身体である。銅版画の解剖図ではビドローの『人体解剖学105図』(1685),最近のものでは解剖体の写真を用いたローエン・横地らの『解剖学カラーアトラス』(医学書院,2007)などが,この方向を追究したものである。しかしこれらの解剖図に描かれているのは,死んだ身体であり,生きている人間の身体ではない。それが,実在の人体を描こうとする解剖図の抱える大きな問題点であった。
しかし現代の画像診断技術は,この障害を乗り越えることで,生きている人間の身体を解剖図として描くことを可能にした。前置きが長くなってしまったが,ここに紹介する『3D画像で学ぶ人体』は,そのような歴史的な意義を持つ書物である。
本書には,CTとMRIのマルチスライスイメージから再構成された3次元の画像をもとにした,多数の解剖図が掲げられている。骨格を取り出したもの,造影剤を入れた血管系を取り出したもの,3次元の画像の中に断面図をはめ込んだもの,臓器の輪郭線を手作業で同定し再構成したものなど,手段を尽くして,さまざまな種類の器官を描き出している。どの画像にも,実在する人体からとられた緊張感がにじみ出ている。付録で添えられたCD-ROMは,再構成された3次元画像を動画として見せてくれるもので,紙面に印刷された画像だけではわからない立体感が得られ,さらに大きな迫力がある。
本書の内容は7章に分かれている。「体幹部」「頭頸部と脳」「顔と頸部」「胸部」「骨盤と腹部」「上肢」「下肢」と全身を網羅している。収載された画像は,骨格,血管,中枢神経については質・量ともに充実しているが,内臓,骨格筋,末梢神経については物足りなさを感じる。これは画像診断の技術が持つ,そもそもの制約によるものである。
そして本書の画像の最大の特徴は,生理的および病的を含め,変異を含む人体の構造がそのまま表現されているところである。気管は拡張して彎曲している。椎骨動脈は左右で太さが異なり,右は第4頸椎で横突孔に入っている。冠状動脈にはバイパス術が行われている。腰椎が6個ある。これらは解剖学教育の一般的な教材としては使いにくい点である。しかし,人体は実際にはこのように変異に富むものだという大切な教訓を与えてくれる。
画像診断をもとにした,生きている人体の解剖図が現れた。掲載されている画像は,これまでの解剖図では得られない実在感を漂わせている。これをどう使い,どのように医療や医学教育に生かしていくか,それこそ現代の医学者に突きつけられている大きな課題ではないだろうか。


菊井 和子,大林 雅之,山口 三重子,斎藤 信也 編
《評 者》吉川 ひろみ(県立広島大教授・作業療法学)
ケアを提供する人に役立つ教材
 本書は,2006年と2007年に雑誌『訪問看護と介護』に連載された「事例で考える医療福祉倫理...
本書は,2006年と2007年に雑誌『訪問看護と介護』に連載された「事例で考える医療福祉倫理...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
