MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2008.09.01
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


宮坂 昌之 監修
長野 敬,太田 英彦 訳
《評 者》山鳥 重(神戸学院大教授・人間心理学)
さまざまなことを考えさせてくれる巨人イェルネの伝記
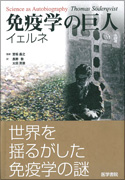 本書の主人公ニールス・イェルネ(Neils Jerne;1911-1994)は1984年,「免疫系の発達と制御の特異性に関する理論とモノクローナル抗体の生成原理の発見」に対してノーベル医学・生理学賞を与えられた免疫学者である。著者トーマス・セデルキスト(Thomas Soderqvist)は受賞直後の公開講演を聞いて,彼に興味を持ち,生前の本人との頻回のインタビュー,記録魔の本人が残した膨大な資料,学術誌への発表論文,研究仲間・知人・家人から聞き出したエピソードなど,膨大な資料に基づき,10年の歳月を費やして本書を完成している。評者はまったくの門外漢で,彼の業績について何の評価もできないが,本書に序文を寄せているわが国の免疫学の泰斗,多田富雄氏によると,彼は「近代免疫学の最後の傑出した理論家,預言者,伝道者」で,免疫学の「帝王」と呼ばれた人である。まさに知的巨人なのである。
本書の主人公ニールス・イェルネ(Neils Jerne;1911-1994)は1984年,「免疫系の発達と制御の特異性に関する理論とモノクローナル抗体の生成原理の発見」に対してノーベル医学・生理学賞を与えられた免疫学者である。著者トーマス・セデルキスト(Thomas Soderqvist)は受賞直後の公開講演を聞いて,彼に興味を持ち,生前の本人との頻回のインタビュー,記録魔の本人が残した膨大な資料,学術誌への発表論文,研究仲間・知人・家人から聞き出したエピソードなど,膨大な資料に基づき,10年の歳月を費やして本書を完成している。評者はまったくの門外漢で,彼の業績について何の評価もできないが,本書に序文を寄せているわが国の免疫学の泰斗,多田富雄氏によると,彼は「近代免疫学の最後の傑出した理論家,預言者,伝道者」で,免疫学の「帝王」と呼ばれた人である。まさに知的巨人なのである。
著者は伝記の草稿を時々,当のイェルネに読んでもらって意見を聞いていたらしいが,本人自身が面白がって読むばかりで,何か注文をつけるというようなことはほとんどなかったという。たった1つの反対は,伝記の題名に提案された「逃れようとする何たる抗い」に対してだったらしいが,本人の死後,デンマーク語で出版された原著は,結局この題が採用されている。この「逃れようとする何たる抗い」が,デイビッド・メル・ポール(David Mel Paul)によって「自伝としての科学:ニールス・イェルネのトラブル人生」という題名で圧縮・英訳された。本書はその翻訳である。
デンマーク語版題名や英語版題名が示唆するように,イェルネは行動の振幅が大きく,相当に型破りな人間だったらしい。常識的な学者の範畴を大きくはみ出した彼の生き様に科学的創造力の源を見ようとする試みが本書である。
両親はデンマーク人で,ロンドンで生まれた。5人きょうだいの4番目である。幼少期の一時期をデンマークの曽祖父母に預けられて過ごし,ついでオランダに移り,ここで大学(ライデン大学数学・物理学科)を卒業した。その3年後,23歳のときに今度はデンマークに移動して,コペンハーゲン大学医学部に入った。しかし臨床研修を終えてようやく医師資格を獲得したときにはすでに36歳になっていた。この間,会社に勤め,研究所に勤め,恋をし,結婚し,子供をもうけ,浮気をしている。
32歳のときに,デンマーク国立血清研究所標準化部門の秘書に採用されたのが,その後の彼の研究人生を決定した。秘書ながら研究活動に参加し,翌年には最初の論文を発表している。37歳で血清研究所の研究助手となり,本格的な研究生活に入る。40歳で“Nature”に論文を発表し,一躍注目を浴びる。この年,標準化部門の研究室長になった。45歳で研究現場を離れ,ジュネーブの世界保健機構(WHO)生物資料標準化部門医務官という行政職に転ずる。51歳で米国ピッツバーグ大学微生物学教室主任教授となる。しかし,米国は彼の好みでなく,わずか4年でフランクフルトのウォルフガング・ゲーテ大学教授とエールリヒ研究所所長としてヨーロッパへ戻る。
57歳のとき,スイス,バーゼルに設立予定のホフマン・ラロッシュ免疫学研究所の開設準備責任者に招かれる。彼はこの仕事に情熱を傾け,2年後の開所時から所長として10年をバーゼルで過ごす。蛇足ながら,わが利根川進氏がノーベル賞受賞研究を行ったのがこの研究所で,この時期のことである。69歳で所長を退き,パリのパスツール研究所顧問となるが,わずか1年で辞め,南フランスの広壮な邸宅に隠棲し,ここで没した。83歳であった。
彼は実験を嫌い,思索を好み,少ない実験から得られたデータを前に徹底的に考えたという。熟考するため,論文の発表はいつも遅れに遅れた。部下が早く完成してくれと懇願することがしばしばであった。学問的視野は広く,彼の最大の業績とされる「免疫のネットワーク理論」にはウィーナーのサイバネティクス理論や,チョムスキーの言語学理論が組み込まれているそうである。生物学の統一理論を構想していたという。彼のネットワーク理論はバーゼル研究所の研究体制に生かされているという著者の見方は面白い。さらにこの理論誕生のきっかけはデータそのものより,むしろ彼の個人生活にあるという指摘も面白い。個人や特異な性格に惹かれる傾向,個体間の確率的な衝突として人と人の出会いを見る傾向がそれだという。
彼は読書家で,それも哲学を好み,キェルケゴール,ニーチェ,ベルグソンに親しんだ。小説ではプルーストを愛した。この知的な精神は,生涯「優越者の微笑を持って相手を眺めることに満足した」という。
私生活は,彼がそれを不幸と感じたかどうかは知らず,客観的にはかなり荒れたものである。最初の妻は自殺に追い込まれているし,2番目の妻は,夫と子どもを捨ててまで彼のもとに奔ったのに,ついに彼の精神生活に場を占めることはなく,離婚している。彼の死を看取ったのは,2番目の妻と離婚後,わずか3か月で結婚した3番目の妻であった。しかも,この3回目の結婚生活の時期にも,彼は別の女性と親密な関係を始め,第3子をもうけている。最初の妻との間の2人の息子のうち,1人が本伝記の作成に協力しているが,父親に対する眼は決して温かいものではない。
彼を熱狂的に尊敬する人も多かったが,嫌う人もまた多かったらしい。著者自身はどうも後者に属し,本書全体に嫌な奴イェルネというトーンが響いているように思うのは評者の読み過ぎか。彼が人を愛するということを知っていたのかどうか,著者は疑っている。彼は常に何かから逃れよう逃れようとしていたのではないかというのがセデルキストの解釈である。
本書は精読を要求するが,それに値する内容を持っている。生きるとはどういうことか,愛するとはどういうことか,研究するとはどういうことか,学問するとはどういうことか,さまざまなことを考えさせてくれる。ぜひとも,多田富雄氏の名著『免疫の意味論』(青土社)との併読をお勧めしたい。
(おことわり:出来事と時間との関係を分かりやすくするため,西暦年でなく年齢を用いて彼の経歴をなぞったが,生年を基準に引き算しただけなので正確ではない。)
A5・頁488 定価4,830円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-250-00238-7


小野 啓郎 監訳
山本 利美雄,宮内 晃 訳
《評 者》角南 義文(竜操整形外科病院院長)
頭と“こころ”に効く骨折治療の座右の書
 骨折の治療では,骨折の発生したメカニズム,目に見えない合併損傷,その肢を再建するのにいかに生体力学的知識を応用するかなど,いわば自分の頭と“こころ”で治療方針を決める機会の多い奥深いものである。
骨折の治療では,骨折の発生したメカニズム,目に見えない合併損傷,その肢を再建するのにいかに生体力学的知識を応用するかなど,いわば自分の頭と“こころ”で治療方針を決める機会の多い奥深いものである。
そのためには,解剖学,生理学,生体力学を学んでおき,症例検討会で平素から各骨折の整復・固定,機能訓練(保存的にしろ,手術的治療にしろ)のイメージトレーニングを心がけておかねばならない。
本書には新しく著者,訳者が加わり,内容は約100頁増量しており,X線像が一部明瞭なものに取り換えられ,CT像も入った。図版には網かけをして一段と見やすくなっている。前半には骨折と骨折治療の基本的事項,後半は各論の中にAO分類が適宜挿入されている。
日本でも増えている老人大腿骨頚部骨折では,基本的なDHS固定の詳細とは別にMultipleピンニング法,人工骨頭,THA,この版ではバイポーラ人工骨頭,ガンマネイル法も紹介されている。
上腕骨近位部骨折ではNeer分類も紹介されているので,大腿骨転子間骨折の安定型,不安定型と,実際の治療に役立つEvans分類もAO分類以外にも挿入してもらいたかった。
本書はもともと医学生を対象にしたものとのことであるが,「骨折治療の基本手技を実際の手順通りに絵入りで解説」「保存的治療を基本に-とりわけ子供の骨折を重視」「成人の長管骨骨折では保存的治療と観血的治療の両者に目配りを」(監訳者の序)が理解しやすく解説してあり,医学生どころか整形外科医,特に初心者に大いに役立つものである。
私どもが初心者であった頃は,De PALMA“The Management of FRACTURES and DISLOCATIONS”が急患時に慌てて見入った書であった。本書はこれに類しているようであるが,総論と各論各章の絵とは別に,解説をよく読んでから図を見て考えることをお薦めしたい。急患を目の前にして,絵だけを見て治療にあたるべきでない。それは骨折治療の“こころ”ではない。
本書を読むと,若き日にCharnley“THE CLOSED TREATMENT of COMMON FRACTURES”を読んだときの考える悦びと感動を思い出す。
骨折治療を志すすべての医師の座右の書としてお薦めしたい。
B5・頁440 定価7,560円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00025-3


精神科身体合併症マニュアル
精神疾患と身体疾患を併せ持つ患者の診療と管理
野村 総一郎 監修
本田 明 編
《評 者》保坂 隆(東海大教授・精神医学)
すべての医師のために患者の心身両面を統合した評価・治療を知る
 本書には「精神疾患と身体疾患を併せ持つ患者の診療と管理」と副題がついているが,まさにタイトルそのままのポケットサイズの気の利いたマニュアルである。今の世代にはマニュアル的な本が好まれる,という意味ではなく,現場に求められる診断の手順や具体的な対処方法を知るには,まさにこのようなスタイルがベストなのである。
本書には「精神疾患と身体疾患を併せ持つ患者の診療と管理」と副題がついているが,まさにタイトルそのままのポケットサイズの気の利いたマニュアルである。今の世代にはマニュアル的な本が好まれる,という意味ではなく,現場に求められる診断の手順や具体的な対処方法を知るには,まさにこのようなスタイルがベストなのである。
私は90年代の初めに野村総一郎教授に初対面した。先生がまさに立川共済病院において,日本で初めてのMPU(Medical Psychiatry Unit)を開設した直後だった。ご自分でもおっしゃっていたが,MPU開設以後,「忙しい」を通り越して,体重が激減してしまったとのことであった。私は1988年に日本総合病院精神医学会の設立をお手伝いし,リエゾン精神医学を極めるべく90-92年に米国留学を終えた直後だったので,MPUには格別の関心があった。
少し理屈っぽい話をする。精神...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
