これからの統合失調症薬物治療を考える(岩田仲生)
2008.06.30
【Seminar】
アドヒアランスの向上,理想の抗精神病薬の創出をめざして
これからの統合失調症薬物治療を考える
統合失調症の治療において最も重要な視点はいかに再発を予防し,患者の社会生活機能を低下させないか,という点に尽きる。最近では,アドヒアランスという概念が統合失調症の再発予防の観点から重視されている。このアドヒアランスを向上させるために重要なポイントはどのようなものであろうか――。本紙では藤田保健衛生大学教授(精神医学教室)の岩田仲生氏に,アドヒアランスの重要性を中心に,統合失調症薬物治療に求められる最新の視点,そして今後の方向性についてお話を伺った(2008年5月20日にヤンセンファーマ株式会社が主催したウェブ講演会の内容から本稿を構成した)。
提供=ヤンセンファーマ株式会社
◆早期介入の重要性
まず,クリティカルピリオドについて述べたい。統合失調症の病態はいわゆる発達変性仮説で捉えられている。発達変性といっても,出生以来,継続的に疾患過程が進行を続けるわけではなく,この病気の予後を決定する重要な時期があり,どのように臨床的な介入を行うかにより,長期予後がある程度決まってくるという仮説である。この重要な時期をクリティカルピリオドと呼ぶ。
クリティカルピリオドは発症前後の期間にあたるため,いかにして早期に発見し,適切な介入を行うかが課題となる。この介入,すなわち統合失調症の治療には薬物療法が必須である。個人的に考える理想の薬は統合失調症の発症を生涯にわたり抑えるワクチンのような薬剤であるが,統合失調症の病態が解明されないと実現は困難であろう。
また,抗精神病薬の代謝に関連する酵素の解析から導き出した最適薬用量予測に基づいた投薬の実現は近い将来実現可能であるかもしれないが,本格的に臨床に応用可能になるまでにはまだ時間を要するため,私たちは現在用いることができる手法にて臨床現場で最善を尽くさねばならない。
そこで,現在使用可能な抗精神病薬に関する情報を,最新の知見を織り交ぜながら整理していきたい。
◆現在使用可能な薬剤の薬理プロファイルの考察
統合失調症はいまだに再発率が高く,長期予後の大幅な前進をみていない。
薬物治療に関してみると,現在は非定型の抗精神病薬がファーストチョイスとなってきたものの,多剤併用がいまだに主流であり,抗精神病薬をどのように使いこなすかという点についてさまざまな見解が存在する。ここでは抗精神病薬の薬理プロファイルとその臨床評価を改めて整理してみたい。
FDAに申請されたデータをもとに,現在わが国でも使用されている第二世代,4剤のハロペリドールに対する優越性を比較してみると(表1),クエチアピン,アリピプラゾールは同等,リスペリドン,オランザピンについては優越性が得られた。より詳細なデータからリスペリドンは4剤のなかで唯一,ハロペリドールよりも陽性症状に有効という結果が得られている。
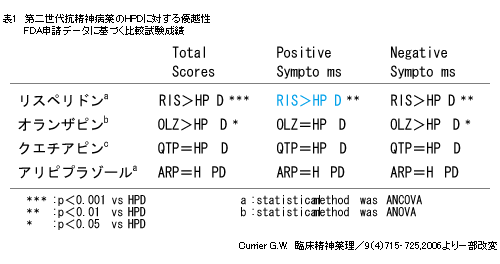
この理由について最近の知見から検証してみたい。
◆D2および5HT2A受容体結合親和性と陽性症状抑制効果
リスペリドンはハロペリドールより陽性症状に対する有効性が高いという結果であったが,ハロペリドールのドパミンD2受容体(以下,D2受容体)結合親和性はリスペリドンよりやや強い。したがって,D2受容体への親和性だけ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
