米国における一般内科とその研修システムについて(谷口俊文)
寄稿
2008.02.04
【寄稿】
米国における一般内科とその研修システムについて谷口 俊文(St.Luke's-Roosevelt Hospital Center内科レジデント)
これまで米国における一般内科については言及されることがあるものの,詳細に関してはなかなか情報を得ることができない状況にあった。米国における一般内科の研修をする機会に恵まれたので,日本における内科のシステムとの違いを中心に米国の「一般内科(General Internal Medicine)」とその研修システムを解説させていただきたい。
米国における一般内科医はおおまかにプライマリ・ケアとホスピタリストに分けることができる。ホスピタリストとは病棟専属医のことである。従来は外来をやりつつ自分の患者が入院した際には病棟へ足を運ばなくてはならなかったが,ホスピタリストを導入することにより,プライマリ・ケア医は外来に集中し,ホスピタリストは入院患者に集中するができ,効率化を図ることができるようになった。
一般内科医にはプライマリ・ケアなど外来のみを行う医師,ホスピタリストとして外来を持たない医師,自分の外来患者が入院した際に外来の前後の時間を利用して病棟も管理する医師などそのスタイルは様々である。どのようなスタイルの一般内科医になるにしろその守備範囲は広く,それらに対応できるように一般内科に特化した研修が必要である。
プライマリ・ケアにおける一般内科医
日本の内科研修において外来研修はほとんど整備されていない。総合診療部におけるプライマリ・ケア研修も始まったばかりである。ここでは一般内科におけるプライマリ・ケアの研修に関して取り上げたい。
プライマリ・ケア外来は完全予約制,急性疾患は救急に送る
外来は施設によって差はあるものの,週に1回のペースで半日の研修をしているところが多い。病棟のローテーション中は午後にプライマリ・ケアの外来がある。プライマリ・ケアの外来は日本での「総合内科」外来と似て非なるものである。基本的に完全予約制であり,慢性疾患の管理,各専門医への紹介,予防接種や定期検診など医療の中心を担う。
日本と違う点は,急性疾患を基本的には救急に送るということであろう。Walk-Inと呼び,予約なしでプライマリ・ケア外来で患者を受け入れることもあるが,その場で検査や点滴が必要と判断された場合にはそのまま救急に患者を送る。プライマリ・ケアと救急の棲み分けがしっかりできているためこのようなことが可能である。24時間受け入れ可能な北米型救急のシステムだからこそ成り立つシステムであろう。
診断のついていないような初診の患者は,基本的にはこの外来の予約を取って受診する。場合によってはWalk-Inで受診することもあろう。どうしても具合が悪く予約まで待てない場合は,直接救急外来を受診することもある。
定期検診に関しては,プライマリ・ケアの守備範囲は広い。身体検診や血液検査,尿検査はもちろんのこと,乳癌検診で乳房の触診および自己検診の指導,子宮頚癌検診(PAP Smear),内診などの婦人科検診もプライマリ・ケアの外来で行う。直腸癌検診すなわち米国では大腸内視鏡(便潜血では不十分)のスケジュールを管理,前立腺癌検診として直腸診とPSAの計測なども重要事項である。インフルエンザのワクチン,肺炎球菌ワクチン(Pneumovax),破傷風などの予防接種を行うのもプライマリ・ケアの仕事である。これらはすべてガイドライン,U.S. Preventive Services Task Forceから出ている推薦事項に従い,エビデンスに基づいて患者管理をする。そのためプライマリ・ケアにおいても最新の知識をアップ・デートしておく必要がある。
外来のブロック・ローテーションとCommunity Based Practice
週に1回の外来の他に,私の病院では1年間に4週間のブロック2つ(計8週間)の外来ローテーションが存在する。午前中はプライマリ・ケアの研修を行い,午後はプライマリ・ケアに役立ちそうな他科の外来にて研修を受けることができる。自分の将来の予定によって調節可能であり,感染症専門医を志望する私は,HIV外来や皮膚科外来における研修を多く入れた。
その他,私のプログラムの外来研修ではCommunity Based Practiceという枠がある。これは週に半日この外来ブロック期間中に近くの開業医と一緒に働き,実際に独り立ちした際の患者マネジメント,保険請求,訴訟対策などを学ぶことができる。
プライマリ・ケアの外来では,個々の患者をより統合的に管理しているように思う。なお,小児科・産婦人科なども診ることのできる家庭医(Family Practice)は一般内科のプライマリ・ケアよりもさらに守備範囲が広い。専門医志向の強いNew Yorkなどの大都市では,成人であれば一般内科医をかかりつけ医として持つ患者が多い。州によっては家庭医が幅を利かせる。同じ米国とはいえども地域差があるようだ。
ホスピタリストとしての一般内科医
一般内科研修の中心となるのはやはり病棟である。入院を必要とする患者は重症患者が多く,学ぶことが多い。幅広い知識を身につけることができるように病棟ローテーションも工夫されている。ここではまず,ホスピタリストとしての一般内科医がどのように機能するかを説明したい(図1)。
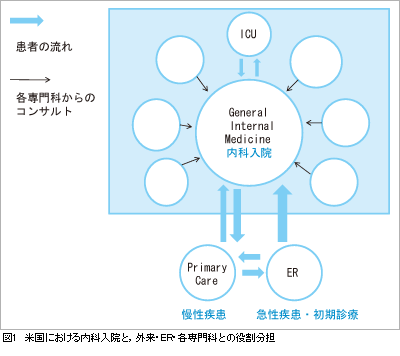
基本的にすべての内科患者は「一般内科」に入院すると考えればよい。そしてプロブレム・リストごとに,...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
