MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2008.01.14
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


「治らない」時代の医療者心得帳
カスガ先生の答えのない悩み相談室
春日 武彦 著
《評 者》丸山 順子(都立駒込病院・アレルギー膠原病科)
研修医のハートを鷲づかみ 肉声に満ちた「裏バイブル」
 現代は「治らない」時代である。たしかに,医療は目まぐるしく進歩したが,かえって複雑となり,「治らない」ことが浮き彫りとなってきた。そんな時代を医師として「まっとうな精神を維持しながら」生き抜くのは至難の業ともいえる。
現代は「治らない」時代である。たしかに,医療は目まぐるしく進歩したが,かえって複雑となり,「治らない」ことが浮き彫りとなってきた。そんな時代を医師として「まっとうな精神を維持しながら」生き抜くのは至難の業ともいえる。
本書は,兄貴的精神科医から,医師における思春期を過ごすわれわれ研修医たちへの裏バイブルである。
キーワードは『中腰力』
著者は,卒後6年間を産婦人科医として過ごし,その後精神科に移籍した経緯をもつ。その後,都立病院精神科部長などを歴任。語り口はきわめてシニカルであるが,長年医療の現場で臨床に汗を流してきたからこそ発することのできる肉声がわれわれのハートを掴む。
そんな著者がわれわれに提言する,「治らない」時代を生き抜く要が,『中腰力』だ。うまくいっているかどうかすぐに結果が出ない状態で,じっと辛抱して待つ能力である。つまり中腰で「中途半端さに耐える能力」が必要だというのだ。
その『中腰力』によって,白黒つかない宙ぶらりんの状態が経過することを耐え,「時間が問題を解決させる」力を大いに活用する。それが援助者の実力のひとつだと著者はいう。もちろん一分一秒を争う判断が必要なこともあるが,それはむしろ「治りうる」場面での問題であり,日々の「治らない」臨床の現場では,この『中腰力』がものを言うというのである。
「ケータイ番号教えて 」と言われたら?
」と言われたら?
中腰で乗り越えていかなければならない日々の臨床。この経験が単に同じ行為の退屈な繰り返しとなるか,そこに新たな発見を見出し,喜びに満ちた探求のプロセスとなるかは,中腰で対峙するときの対象との距離のとり方いかんである。「繰り返しであっても,それを同じフレームで眺めていれば確かに退屈かもしれないが,もっと違う分節の仕方をすれば,かえって単調なものほど意外なものが顕現しやすい」と著者はいう。
では,いかにして『中腰力』を身につけるのか? 本書のなかには,そのヒントとなる《カスガ式。切り返しフレーズ》がちりばめられている。
「(嫌味たっぷりに)医者なんて,人の不幸で儲けているんですよねえ」という患者さんに対して,「わたしが失業してしまう世の中になることを,待ち望んでいるんですけどね」と相手の言い分に同調するふりをして,そこから何か間抜けな結論を引き出してみせるとか。「先生のケータイ番号,教えてください 」と言われたときの切り返しなど,おおいに納得した。
」と言われたときの切り返しなど,おおいに納得した。
おおらかに,ためらおう
われわれが日々遭遇する挑戦的な場面や,逆に淡々とした医療という日常。それを単なる治療行為の反復としてではなく,医療者としての成長過程としてとらえることが重要である。またそれは同時に,その対象である患者さんが,自分の病気を受け入れ,病気とともに歩む方法を学ぶという双方の成熟過程であることを教えられた。
私自身,医師になってまだ6年。著者が産婦人科医から精神科医に転向する前の段階であるが,「医師の品格」として著者が指摘する,ある種の「おおらかさ」と「ためらう」ことをためらわない謙虚さを常に失わず,「治らない」時代を生き抜く『中腰力』を鍛えていきたい。
四六判・頁196 定価1,470円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00519-7


高久 史麿,白神 誠,藤上 雅子 監修
北村 聖 編集協力
《評 者》松山 賢治(共立薬科大教授・臨床薬学)
学生の教育から生涯教育まで広く活用されるべき一冊
 2006年から6年制の薬学教育がスタートし,その特徴は,今までの薬剤師教育(薬学教育)が知識偏重型から,臨床現場に必要な知識,技能,態度の3つを重視したより実践的な教育になったことである。知識に関してはCBT,態度・技能についてはOSCEで試験が課されるようになった。特に後者では,模擬患者に対して,薬局あるいは病棟において服薬指導する場面が設定されていて,ますますファーマシューティカルケアと服薬コミュニケーション能力が必要となってきている。
2006年から6年制の薬学教育がスタートし,その特徴は,今までの薬剤師教育(薬学教育)が知識偏重型から,臨床現場に必要な知識,技能,態度の3つを重視したより実践的な教育になったことである。知識に関してはCBT,態度・技能についてはOSCEで試験が課されるようになった。特に後者では,模擬患者に対して,薬局あるいは病棟において服薬指導する場面が設定されていて,ますますファーマシューティカルケアと服薬コミュニケーション能力が必要となってきている。
本書は,『ファーマシューティカルケア・ファーストステップ』というタイトルで,新薬学教育のコアカリキュラムに沿った重要な36主要疾患を取り上げ,医師サイドは自治医科大学学長の高久史麿先生をはじめ,52名の全国医学部教員の分担執筆,一方,薬剤師側の執筆者は,前柏戸病院薬剤科長の藤上雅子先生をはじめ16名の執筆陣で,空前絶後の豪華執筆陣である。このような場合,編集計画がよほどしっかりしていないと「船頭多くして船山に登る」にガッカリさせられることが多いが,本書はそんな懸念を打ち払い,読者は,従来の本から得られなかったライブの感動を受けることであろう。
革新的な展開を「コペルニクス的展開」と表現するが,まさに本書のことを形容するのにピッタリの言葉である。本書をちょっと覗いてみると,第1章は心臓・血管系の疾患で,(1)心房細動,(2)高血圧,(3)狭心症,(4)心不全があるが,その中から心房細動をピックアップしてみる。冒頭,心房細動の疾患について専門医師からの総説があり,Vaughan-Williamsの坑不整脈薬の分類を基にした作用機序や副作用などの説明後に,心房細動の疾患のケーススタディーが付随している。服薬コミュニケーションでは,その疾患が出演,薬剤師と患者の会話をライブで再現しているのが面白い。最後に心房細動へのアプローチとして,Sicilian Gambitからみた不整脈薬の選択基準で締めくくるなどなど専門書にしては面白すぎるというのが私の偽らざる感想である。
近年の薬剤師国家試験では,疾病から服薬指導まで組み込んだ総合的問題が出題されてきている。6年制の試験ではさらにこの傾向が顕著になることを予想している。ケーススタディーは学生のスモールグループディスカッションにも絶好の教材である。
本書の書評を書いている私の切なる希望を述べさせていただくと,「もっと他の疾患についてもこの様式で執筆していただき,ぜひ,続編を出してください」ということである。
本書は単に薬学生の教育のみならず現役薬剤師の生涯教育にも最適の本であり,本書が有効活用されることを希望する次第である。
B5・頁352 定価4,500円(税5%込)発行:ライフメディコム,発売:医学書院
ISBN978-4-260-70057-3


イラストレイテッド肺癌手術
手技の基本とアドバンスト・テクニック[DVD付] 第2版
坪田 紀明 著
《評 者》白日 高歩(第61回日本胸部外科学会会長/福岡大教授・外科)
詳細な図譜とDVDで肺癌手術の手技を理解する
 坪田紀明先生は今日,わが国の肺外科手術を代表する第一人者である。わが国における肺外科の技術は,かつての肺結核外科を継承する形で今日に伝えられてきた。評者らの若い頃(昭和40年代)にはまだ呼吸器外科手術では肺結核が主体であり,連日各種の区域切除や胸郭形成術が国内各施設で行われていた。もちろん肺葉切除がすべての手技の基本であり,当然肺全摘も今日以上に高頻度に実施されていたという記憶がある。やがてそれらが肺癌手術にとって代わられると,一時期ほとんどの手術が肺葉切除に限られるという印象であった。呼吸器外科医としての私は,これは自分たちの技術的発展を阻害し,外科医としての役割の放棄につながる現象で,決して歓迎されるものではないという危惧を持つようになった。いかに肺葉切除が肺癌手術の基本であっても,この手術ばかりで日々を過しては何の成長ももたらされないのである。
坪田紀明先生は今日,わが国の肺外科手術を代表する第一人者である。わが国における肺外科の技術は,かつての肺結核外科を継承する形で今日に伝えられてきた。評者らの若い頃(昭和40年代)にはまだ呼吸器外科手術では肺結核が主体であり,連日各種の区域切除や胸郭形成術が国内各施設で行われていた。もちろん肺葉切除がすべての手技の基本であり,当然肺全摘も今日以上に高頻度に実施されていたという記憶がある。やがてそれらが肺癌手術にとって代わられると,一時期ほとんどの手術が肺葉切除に限られるという印象であった。呼吸器外科医としての私は,これは自分たちの技術的発展を阻害し,外科医としての役割の放棄につながる現象で,決して歓迎されるものではないという危惧を持つようになった。いかに肺葉切除が肺癌手術の基本であっても,この手術ばかりで日々を過しては何の成長ももたらされないのである。
当時の拡大手術一辺倒の風潮が徐々に修正され,患者の機能損失を出来る限り小さくするための縮小手術も必要との認識が,外科領域全体にようやく浸透しつつあった。そのような雰囲気のもとに実際的な説得力を持って登場してきたのが,坪田先生の提唱する拡大区域切除術の概念であった。外科医は技術的な向上を常にめざすことが義務であり,若い人にとって難しい高度な手技への挑戦は向上への夢を与えるものである。各種区域切除は呼吸器外科医にとって,肺葉切除と並んで習得されるべき必須の技術のはずである。
今回出版された『イラストレイテッド肺癌手術』の第2版は,この区域切除を含めて肺葉切除,気管支形成手術,肺全摘など,手技的向上をめざすすべての呼吸器外科医の要望に応える内容で世に出された。第1版とはさらに装いを新たにして,DVDによる坪田先生の実際の手術の動画と手技解説(ナレーション)まで付け足されて提供されている。これを手にする人は先生の独特のハサミの持ち方,カード型小開胸器での術野展開,摘出肺領域に空気を送って切除する区域間切離の方法などを映像として詳しく学ぶことができるであろう。詳細な図譜で手技を理解しようとしても一定の限界を感じるはずの若い人たちにとって,現実の映像でその実際を学べることは,何という恩恵であろうか。新しい映像時代に生まれた彼等をうらやましがらずにはおれない。それと同時に,このような優れた手術書が世に送られることで,わが国のすべての若手呼吸器外科医が確固とした技術的基盤を与えられて,より大きく成長してゆくことを信ずるものである。
A4・頁216 定価18,900円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00461-9


《総合診療ブックス》
臨床医が知っておきたい女性の診かたのエッセンス
荒木 葉子 編
久慈 直昭,高松 潔,宮尾 益理子,柴田 美奈子 編集協力
《評 者》岸 玲子(北大教授・公衆衛生学)
折に触れて読んでほしい女性診療の珠玉のエッセンス
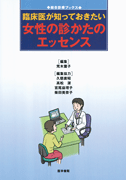 今日ほど女性のライフサイクルが劇的に変化
今日ほど女性のライフサイクルが劇的に変化この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
