MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.09.03
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


社団法人 日本リハビリテーション医学会 監修
日本リハビリテーション医学会診療ガイドライン委員会
リハビリテーション連携パス策定委員会 編
《評 者》浜村 明徳(小倉リハビリテーション病院長)
生き甲斐を持って生活できる連携リハ地域ネットワークづくりを
 このたび,日本リハビリテーション医学会診療ガイドライン委員会リハビリテーション連携パス策定委員会より,わが国の脳卒中診療やリハビリテーション(以下,リハ)医療,地域医療連携の第一線で活躍される115名の執筆者による脳卒中リハ連携に関する書が発刊された。
このたび,日本リハビリテーション医学会診療ガイドライン委員会リハビリテーション連携パス策定委員会より,わが国の脳卒中診療やリハビリテーション(以下,リハ)医療,地域医療連携の第一線で活躍される115名の執筆者による脳卒中リハ連携に関する書が発刊された。
本書は,冒頭で診療ガイドライン委員会の里宇明元担当理事が述べているように,「単にツールとしての連携パスのみに焦点を当てず,障害を持つ人々が地域で生き甲斐を持った生活を送れるように援助する活動としてのリハ医療」の一環,そのつなぎに関係する人とツールのあり方を示したことに類書が及ばない特質がある。いわば,リハ医療における「連携の科学書」であり,かつ連携マニュアルとしても活用できる「連携実践の手引書」ともなっている。
前半では,(1)脳卒中診療の現状と診療連携,(2)クリニカルパスの基本,(3)脳卒中診療におけるクリニカルパスの動向,(4)データベースとITの活用と開発と,脳卒中連携に関する基本的な事柄,連携の概要や科学的根拠などが紹介されている。連携の基本はパートナーシップ(栗原),仲間づくり活動(正門),お互いの信頼(橋本)など「人」であること,急性期から在宅生活支援に至る「システムづくりを意識した活動の中に連携がある」ことを多くの執筆者が述べている。また,クリニカルパスの意義やパス作成のポイント,その動向などを通して,効果に関することや今後の方向性も示されている。
後半はより多くのページを割いて,(5)連携パスの実践,(6)ユニットパスの実際,(7)連携相手に望むことなど,実践事例や関係者の意見などが紹介されている。現時点でのわが国の先駆的連携事例,特徴ある事例の殆どが紹介されていると言ってもよい。これらの事例から,連携パスは地域のネットワーク活動の結果としてできてきたものもあれば,連携パスを動かすことが契機となってネットワーク活動が始まった事例もあることがわかる。ここには,連携パスを実践するための知恵,ネットワークづくりのヒントが集積されている。
リハにおいて連携は目標であり,念仏のように唱えられてきた経緯がある。昨今,医療機関の役割分担が明確になり,連携なくしてリハが成り立たなくなった。そのことが,支援ツールとしてのパスを活用できるものとした。
本書を参考に,それぞれの地域,関係者,時期,障害度などに適したあり方が検討され,また本書が障害のある人々のQOLの向上,地域のみんなで切れ目なく支える地域リハ体制づくりの一助となることを期待したい。
A4・頁256 定価3,990円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00478-7


大江 透 著
《評 者》杉本 恒明(関東中央病院名誉院長)
臨床医の視点で有用性を評価した不整脈教科書
 立派な装幀の不整脈教科書である。大江透教授がお一人で書かれている。評者も実はかねて,こうした本を書きたいという願いはもっていた。しかし,いざ書くとなると,不得手な分野が目につき,それぞれの専門家に依頼するのが妥当と思われて,結局は分担執筆になってしまっていた。それを大江教授はお一人でおやりになった。大江教授でなくては書くことができなかった教科書であり,また,このような本の執筆者としてもっとも適切な人は大江教授であるとは誰もが認めるところであろう。
立派な装幀の不整脈教科書である。大江透教授がお一人で書かれている。評者も実はかねて,こうした本を書きたいという願いはもっていた。しかし,いざ書くとなると,不得手な分野が目につき,それぞれの専門家に依頼するのが妥当と思われて,結局は分担執筆になってしまっていた。それを大江教授はお一人でおやりになった。大江教授でなくては書くことができなかった教科書であり,また,このような本の執筆者としてもっとも適切な人は大江教授であるとは誰もが認めるところであろう。
大江教授は国立循環器病センターという臨床研究の場に長くあって,後に岡山大学内科教室という教育研究の場に移られた。この間にご自身がもたれた経験が本書執筆の動機となったもののように思われる。
不整脈の予後が健康な集団にみられた場合と末期患者にみられる場合とでは異なることを400年も昔の医学がすでに教えているということから本書は始まる。不整脈の分類には,心電図上の分類,原因・経過上の分類,電気生理学的検査による分類,発生機序による分類,有効薬剤による分類,日内変動による分類などと独自の分類がある。基礎的知識の解説がこれに続いて,次が検査である。基礎疾患の検索は本書ならではの章といえよう。診断は日常的な問診,身体所見,心電図によって行われる。この章ではティルト試験,圧反射感受性検査にもふれられている。ついで,電気生理学的検査である。電気生理学的検査は不整脈の機転を明確にし,診療に役立つ多くの知見を提供してきた。治療には薬物治療,デバイス治療,外科的治療,アブレーション,そして,さらに大規模臨床試験の成績が整理された問題点に私見を併せて紹介されている。各論では不整脈の種類別にこれらの知見が再度,まとめられていて,わかりやすい。ことに頻拍における興奮旋回路の同定,アブレーション部位の決定などについては流石に説得性がある。心室頻拍,心室細動が先にあって,これに心室期外収縮が続くのは,その意義を考えると理解しやすい。
本書に一貫しているのは,つねに臨床医としての視線があるということである。すべてが臨床的有用性によって評価されている。治療に役立つか,予後を改善するか,が評価の基準にある。アブレーション成功率別の不整脈の分類などはこの意味での独自の工夫であろう。
実にコンパクトによくまとめられている。単独執筆のよさであろう。また,大江教授の学識の深さを感じさせる。文章的には,独特の調子を帯びた表現もあって,講義風景が想像される。そして,このような大江教授の名講義が岡山大学の学生諸氏から,広くわれわれにも開放されたことを嬉しく思った。
B5・頁536 定価8,925円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00208-0


現場から学ぶ
自立支援のための住宅改修
みてわかる工夫事例・不適事例
鶴見 隆正,田村 茂,宮下 忠司,与島 秀則 著
《評 者》秋田 裕(横浜市総合リハビリテーションセンター)
生活様式・動作をもとに工夫のポイントを解説
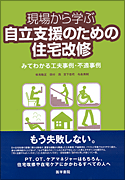 介護保険制度が始まって以来,住宅改修は介護サービスのひとつに位置づけられ,高齢者や障害のある方々の在宅生活を支援する重要な手段であるとの認識が定着したのは大変喜ばしいことです。しかし現状では,施工された住宅改修が必ずしも満足な結果をもたらしているとはかぎりません。せっかく改修工事をしたのに,使いにくい,期待したほどには改修効
介護保険制度が始まって以来,住宅改修は介護サービスのひとつに位置づけられ,高齢者や障害のある方々の在宅生活を支援する重要な手段であるとの認識が定着したのは大変喜ばしいことです。しかし現状では,施工された住宅改修が必ずしも満足な結果をもたらしているとはかぎりません。せっかく改修工事をしたのに,使いにくい,期待したほどには改修効この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
