MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.07.16
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


岡田 正,馬場 忠雄,山城 雄一郎 編
《評 者》武藤 泰敏(岐阜大名誉教授)
新領域の病態栄養学を 精力的に盛り込んだ良書
 かつて,『栄養化学概論』(芦田淳著,養賢堂)という名著があり,多くの人々が正しい栄養学を学ぶことができました。しかし,現在「食物や食品に含まれる栄養成分のみをテーマとするのではなく,同時に,それを受け入れる人間の側に立って考察していく」風潮が大きな支持を得つつあります。さらに,高齢者の栄養を考える時,“人間の尊厳”を重視した「人間栄養学」をめざした努力も推し進められています。
かつて,『栄養化学概論』(芦田淳著,養賢堂)という名著があり,多くの人々が正しい栄養学を学ぶことができました。しかし,現在「食物や食品に含まれる栄養成分のみをテーマとするのではなく,同時に,それを受け入れる人間の側に立って考察していく」風潮が大きな支持を得つつあります。さらに,高齢者の栄養を考える時,“人間の尊厳”を重視した「人間栄養学」をめざした努力も推し進められています。
このような視点に立った栄養学の名著が次々に上梓され,わが国に輸入されています。特に,Garrowらによる“Human Nutrition and Dietetics”(邦訳:『ヒューマン・ニュートリション-基礎・食事・臨床』医歯薬出版),Allisonの“Nutrition in Medicine, A Physician's View”(邦訳:『医師のための栄養学』ダノン健康栄養普及協会)などは真に味わいのある栄養学の指導書といってよいと思います。
しかし,残念ながら,日本人を対象とした系統的な人間栄養学(臨床栄養学)の専門書は決して多いとはいえません。このたび外科,内科,小児科領域の編者からなる,綿密な企画に沿った意欲的な著書が,医学書院から刊行されたのは注目に値します。「栄養は力」であるという自己体験をもつ臨床家として,病態改善を優先させた「栄養治療」は“医食同源”という東洋思想にも合致したもので,薬物治療に勝るとも劣らない,しかも,身体に優しい治療法といえます。
栄養アセスメントから栄養治療へ,チームワークから多職種協働のNSTへ,生活習慣病の栄養学(内臓脂肪の役割),時間栄養学,オーダーメイドの栄養学(個の栄養学),など新しい領域の病態栄養学が精力的に盛り込まれております。
なかでも,糖尿病の記述は圧巻であり,摂食・嚥下障害,肝移植も大変優れた内容ではないかと舌を巻いた次第です。高齢者の栄養学(骨格筋萎縮Sarcopenia)は今後の一大テーマですが,倫理的にも統一した見解が十分とはいえません。合併症に密接に関与した低栄養は当然治療の対象になりますが,一方,“irreversible”な(超)高齢者の低栄養状態は果たして“aggressive”な処置をすべきかは問題で,安らかな「死の準備」の裏返しではないかとも想像されてなりません。


吉良 健司 編
《評 者》牧田 光代(豊橋創造大教授・理学療法学)
施設と在宅のリハの違いを 実例とともに提示
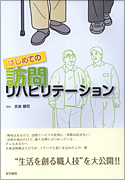 日本における訪問リハビリテーションの歴史は1982年に老人保健法が施行されたのに伴い,機能訓練事業および訪問指導事業に理学療法士がかかわったことから,制度的にはじまっている。医療としても診療報酬としての訪問理学療法が同時期に認められている。しかし,これらは数量的にも少なかった。本書の筆者たちが訪問リハビリテーションの研究会を立ち上げ,かかわったのは1999年から2006年。当時は2000年の介護保険制度施行に向かう途上であり,かつその創世記であった。筆者らは,研究会を立ち上げる前から実際には訪問リハビリを実践していたのだろうから,まさにこの道の草分け的存在であろう。本書の中で筆者らは「介護保険制度により訪問リハビリテーションが一気に普及するかと思ったがそうではなかった」と述べている。
日本における訪問リハビリテーションの歴史は1982年に老人保健法が施行されたのに伴い,機能訓練事業および訪問指導事業に理学療法士がかかわったことから,制度的にはじまっている。医療としても診療報酬としての訪問理学療法が同時期に認められている。しかし,これらは数量的にも少なかった。本書の筆者たちが訪問リハビリテーションの研究会を立ち上げ,かかわったのは1999年から2006年。当時は2000年の介護保険制度施行に向かう途上であり,かつその創世記であった。筆者らは,研究会を立ち上げる前から実際には訪問リハビリを実践していたのだろうから,まさにこの道の草分け的存在であろう。本書の中で筆者らは「介護保険制度により訪問リハビリテーションが一気に普及するかと思ったがそうではなかった」と述べている。
その原因の1つが本書に一貫して流れている訪問リハビリの理念であろう。訪問(在宅)リハビリには医療施設におけるリハビリとは場所が変わるだけではない本質的な違いがある。もちろん,そもそもの問題として訪問リハビリに携わる専門職種の数が少ないということもあるが,病院など医療施設に勤務する理学療法士などのリハビリ関連職種はおぼろげにその違いに気づいており,病院勤務から在宅への不安も持っていたのではないだろうか。
本書でも述べられているように,医療施設で行われる医療は医療モデルとして疾患や障害などの問題状況を医学的な原因に還元して解決策を講じるが,訪問リハビリのようにいわゆる地域においては「生活モデル」で問題解決を図ることが基本になる。生活モデルでは対象者を生活者としてとらえ,目的はQOL向上である。そのアプローチは生活そのものに対して行われ,主体は利用者であり,ゴールは生活の自立である。これをそのまま聞くと当然のように思えるが,医療モデルでは目的は疾病の治癒,延命であり,対象者は患者で,その方法は治療であるから,主体者は提供者すなわち医療従事者となる。このように対比してみると大差があるのがわかる。
従来は医学モデルをそのままあてはめ,「すでに治療はおわりました。障害は残りますが私たちのすべきことはもうありません。あとは貴方次第です」と自宅に戻していた人たちを,訪問して生活支援を行うのであるから,医療モデルだけで学んできた人たちにはどうしてよいかわからないのが実情であった。
しかし,施設から在宅への社会の流れで訪問リハビリテーションは今後需要が高まっていくものと思われる。このような中で,本書はこれから訪問リハビリテーションを始めようとする人々にとっては大変有益なものと考えられる。それは本書が現場で実践してきたことを裏づけにして書かれているからである。特に医療施設内でのリハビリテーションと在宅でのリハビリテーションの違いがその理念だけでなく,実例を交え懇切丁寧に書かれている。事例編に示される正解の多様性は正に生活の場においてこそのものである。
本書はこれから訪問リハビリテーションをはじめようとする専門職のみならず,訪問リハビリテーションとは何かを知りたい人たちの一般的な読み物としても有意義である。


糸満 盛憲,占部 憲,高平 尚伸 訳
《評 者》黒坂 昌弘(神戸大教授・整形外科学)
MISの光と影を 理論的かつ客観的に記載
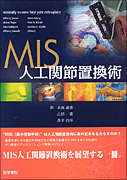 欧米の第一線で活躍する整形外科医によって執筆された,“Minimally Invasive Total Joint Arthroplasty”が,北里大学の糸満盛憲教授らによって翻訳され,『MIS人工関節置換術』として出版された。
欧米の第一線で活躍する整形外科医によって執筆された,“Minimally Invasive Total Joint Arthroplasty”が,北里大学の糸満盛憲教授らによって翻訳され,『MIS人工関節置換術』として出版された。
人工関節置換術は,数...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
