「見えない障害」に連続したケアを(中島八十一)
高次脳機能障害支援のために
インタビュー
2007.02.19
【インタビュー】
「見えない障害」に連続したケアを高次脳機能障害支援のために
中島八十一氏(国立身体障害者リハビリテーションセンター学院長)
外傷・疾病による脳損傷によって引き起こされる高次脳機能障害。早期のリハビリテーションが社会復帰に有効だが,医療から福祉への移行がスムーズに行われていない現在,復帰への課題は多い。厚労省は,高次脳機能障害者への適切な医療・福祉サービスの提供をめざして2001年より5年間「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施。当事業に携わり,『高次脳機能障害ハンドブック――診断・評価から自立支援まで』(医学書院)の編者でもある中島八十一氏(国立身体障害者リハビリテーションセンター学院長)にお話を伺った。
■社会問題としての高次脳機能障害
――高次脳機能障害とはどのような障害か,簡単にご説明いただけますか。中島 高次脳機能障害という言葉は,もともと定義のはっきりしない用語でした。研究者の間でも,個々の見解はあっても,具体的にどのような方を指すかは非常に曖昧だったのです。しかし私どものようにリハビリテーションという医療・福祉の両面にわたる業務をしている人間が,高次脳機能障害をお持ちの方に医療・福祉サービスを提供しようと考えた時に,まずその対象者を明確にする必要が出てきました。
厚労省モデル事業の立ち上げ
中島 その1つのくくりとなるのが「器質性精神障害」という言葉です。これは法令にも記載されている用語で,けがや病気による脳損傷に基づく精神症状を指し,高次脳機能障害はここに含まれます。しかし,そのようなくくりが,実際どのような症状で,どんな医学的リハビリテーションがあり,どんな支援策が取れるのかといった時に,これまで具体的なデータは乏しく,時には主観的な捉え方がされていました。したがって,まずモデル事業というものを立ち上げ,これら一つひとつについて,エビデンスが得られるような調査研究と試行的実践を始めたのです。このモデル事業は,平成12年に,当時の坂口力厚生大臣と宮沢喜一大蔵大臣が,大臣復活折衝で高次脳機能障害者を支援するという予算上の合意をしたことによって開始されました。
――国として高次脳機能障害の支援に取り組むことを表明したわけですね。
中島 ええ。つまりこれは厚労省の事業なのです。この背景として,日本では,後遺症としての高次脳機能障害をケアする方法が十分に確立していないという現状がありました。しかも,この障害はよく「見えない障害」と言われるように,退院後,社会に出て初めて顕在化することが特徴です。ですから病院ではそこそこ生活できていても,家に帰ってみると,対人関係,社会生活その他もろもろにおいて重大な障害があることにはじめて気づく。さらに,いったんは病院を退院したため,その後どのような施設に行けば,生活のための訓練や,職業に戻るためのアドバイスを受けられるのかがまったくわからない。そこでこのことが社会問題化したのを受けて,国を挙げて対策を打つことになったのです。
若い人をどのように社会復帰させるか
中島 図は,モデル事業で行った支援プロセスを示しています。われわれは,「常に連続したケア」というものを,モデル事業のサブタイトルに掲げました。サブタイトルというよりは,「旗じるし」かもしれません。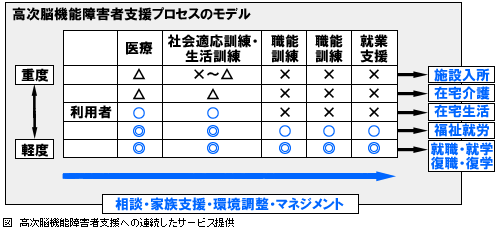
――患者さんの年齢が,非常に若いということが大きな特徴ですね。
中島 ええ。そのとおりで,意図的に18-65歳までに区切って,サービスの提供を考えています。ご高齢の方にも,特に脳血管疾患に基づく高次脳機能障害は多いのですが,その方たちは一般的には介護保険の対象になります。そして,社会に戻るといっても就労を考えることは少ない。したがって,このモデル事業では「若い人をどのように社会復帰させるか」ということに焦点を当てたと言えます。
障害の程度によって,最終的な目的が施設入所であったり,就労・就学であったりするわけで,そのためにクリアすべきステップが,「医療」「社会適応訓練・生活訓練」「職業訓練」など段階を追って示してあり,◎・○と△と×で評価されます。
――クリアすれば次にいける,と。
中島 そういうことです。
連続したケアが実行できるシステムを
中島 図の下に長い矢印がありますが,それらが1本の長い矢印として実行されてはじめて,最終目標に到達できます。これが「連続したケア」で,そのためには相談,家族の支援,職場や学校の環境調整などが必要です。しかしモデル事業以前は,病院では救急医療が済んで「命があってよかったね」というところで終わっていて,高次脳機能障害があるかどうかの診断を受けずに退院した例もありました。あとで重大な障害に気づいても,どこの訓練施設へ行けばいいかわからないし,そもそも相談窓口もなかったんです。しかも,福祉サービスを受けるためには障害者手帳が必要なのですが,どのような障害者手帳を取ればいいのか,誰が発行してくれるのかもわからない。そういうわけで,その1本の長い矢印で示した部分が,ステージごとにちぎれていたのです。したがって,「連続ケアを実行できるシステムを作りあげよう」というのがこのモデル事業のいちば...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
