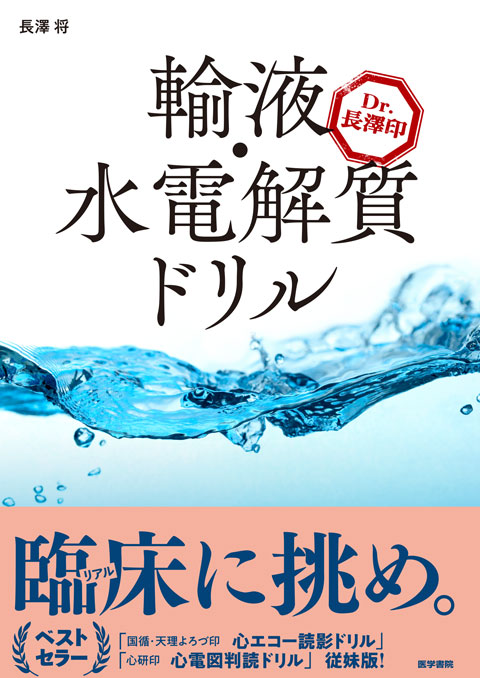- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2023年
- 医学界新聞プラス [第2回]Case 3 肝硬変・CKDで低Na血症を来している70歳代女性
医学界新聞プラス
[第2回]Case 3 肝硬変・CKDで低Na血症を来している70歳代女性
『Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル』より
連載 長澤将
2023.11.10
Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル
輸液・水電解質は難しい,一見わかったようでも,やっぱりよくわからない……。電解質異常の患者を診た際,何の検査をオーダーし,その結果はどう解釈し,どう対応すればいいのでしょうか?
『Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル』は1章の総論,2,3章(各論)の20にも上る珠玉の症例から輸液・水電解質の症例に対応する際の考え方をわかりやすく解説。経験豊富なDr.長澤の思考回路が1冊に詰め込まれています。
医学界新聞プラスでは,総論より「身体のバランスは『完璧なラーメンの味付け』である」,各論より「肝硬変・CKDで低Na血症を来している70歳代女性」「救急受診後の再診で低K血症を来していた40歳代女性」「腎機能低下を伴う高Ca血症を来した80歳代女性」をピックアップし,4回に分けて本書を紹介します。
水電解質・輸液の領域は正解にグラデーションがある(必ずしもエビデンスがない)ので, 問題集(2,3章)の解答には
正解 いかなる条件でも正答の可能性が高い選択肢
条件付き正解 確固たる理由があれば正答になりうる選択肢
の2パターンを用意しました.
条件付き正解の場合は,解説にその「条件」を示しています.
エビデンスが乏しい領域については,長年臨床を行ってきた私の感覚も入っているので, 正解・不正解で一喜一憂するのではなく,解説もあわせて珠玉の症例を紙上体験ください.
- 70歳代前半,女性.
- 現病歴
20年ほど前から肝機能障害を指摘され,脂肪肝としてフォローされていた.徐々に腎機能が低下したために当院紹介となった.一時期NASH(non-alcoholic steatohepatitis)に伴う肝硬変で腹水がたまり,体重が57kgと増えていた.利尿薬の内服で47kgまで減ったが,最近また増えてきて51kgとなり,お腹の張りも気になるようになってきた.今回は慢性腎臓病(CKD)の原因精査および体液量管理のため入院となった. - 身体所見
143cm,51.2kg,血圧145/81mmHg,心拍数72bpm(整),SpO2 96%(室内気),呼吸回数16回/分.JCS 0,心雑音を認めない,腹部に波動を感じる,下腿浮腫を認める. - 生活歴
飲酒歴:もともとは大酒家だったが,ここ半年は禁酒,喫煙歴:30歳で禁煙,20本×10年,ADL:自立,妊娠・出産歴:2妊2産,妊娠高血圧症候群なし. - 家族歴
特記事項なし - 既往歴
高血圧,糖尿病 - 内服薬
フロセミド 40mg,アルダクトンA 25mg,フェブリク 40mg,アムロジピン 2.5mg,ポリスチレンスルホン酸Ca 20%ゼリー 25g×2個,リーバクト 4.15g×3包.サプリメントなし. - 血液検査
Na 132mEq/L,Cl 105mEq/L,K 4.2mEq/L,Cr 1.95mg/dL, BUN 38mg/dL,Alb 3.3g/dL,Hb 8.3g/dL,Plt 17万/μL, T-Bil 1.2mg/dL,PT-INR 1.07,HbA1c 4.9% - 尿検査
尿比重 1.021,尿潜血−,尿タンパク5.6g/gCr. - 画像検査
腎臓サイズは右9.5cm,左9.5cm,皮質は低輝度.肝臓表面はirregular.胸部X線:右に胸水を認める.心胸比(CTR)53%.
- この患者の低Na血症の原因はどれか?
① CSWS(中枢性塩類喪失症候群)
② 低張性脱水
③ SIADH
④ 希釈性低Na血症
- この患者にするべき対応はどれか?
① 減塩
② 水制限
③ フロセミドの増量
④ トルバプタンの投与
- Learning Point
- ★体液量過剰の低Na血症は希釈性の診断になる.
- ★希釈性低Na血症と心因性多飲症との鑑別は尿浸透圧が有用である.
- ★心不全,肝硬変,ネフローゼ症候群などでは体液量過剰にもかかわらずADHが分泌され,しばしば臨床的に問題を起こす.
- ★上記のような症例ではADHをブロックするトルバプタンが有用なことがある(ただし,トルバプタンはコストがかなりかかる).
- 文献
- 1) 多飲症・水中毒─ケアと治療の新機軸,医学書院,2010
- 2) Nature 608:374-380, 2022[PMID:35831501]
- 3) 肝硬変診療ガイドライン2020(改訂第3版).p.xxi,84,南江堂,2020
- 4) World J Gastroenterol 23:8062-8072, 2017[PMID:29259382]
- 5) 臨床薬理 47:17-20, 2016
- 6) J Gastroenterol Hepatol 34:1231-1235, 2019[PMID:30370940]
解説
A1 正解 ④ A2 正解 ①,②,④ 条件付き正解 ③
さて,このような患者さんをきちんとマネジメントできるでしょうか? 今後は病院の統合ならびに集約化が進んでいき,特定機能病院や急性期病院は誰も彼もは受診できない時代が来るので,非専門医でもある程度のことはできるようになっていかないと職にあぶれてしまうかもしれません(軽度の検査値異常は自分でこなしてください,となると予想しています).
Q1の解説
さて本題に参りましょう.低Na血症においては,体全体の「Naの量」と「真水の量」を分けて考えることが第一歩でしたね(▶書籍『Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル』1章-5☞21頁).体液量の多寡とNa量の多寡によって本来は3×3の9通りの組み合わせがあるはずです(図1).
図1 体液量とNa濃度からみたNa異常
*8.4%メイロンや高張液の大量補液などではありますが,それは明らかに禁忌で医療事故のレベルです.
SIADH(syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone;抗利尿ホルモン不適切分泌症候群),MRHE(mineralocorticoid-responsive hyponatremia of the elderly;鉱質コルチコイド反応性低Na血症),CSWS(cerebral salt wasting syndrome;中枢性塩類喪失症候群),RSWS(renal salt wasting syndrome;腎性塩類喪失症候群)
これだけであればそれほど困らないですが,実際の臨床では「時間」というファクターが関与してきますし,患者さん自身の行動や医療行為に伴う修飾などが加わり複雑になることがしばしばあります.
さて,体液量の把握はできるようになったでしょうか? 「体の中の約60%が水分であり,細胞内液が2/3,細胞外液が1/3で,細胞外液は間質と血管内に3:1で分布する」というのが原則でしたね〔ここがパッと出てこない方は▶書籍『Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル』1章-3(☞14頁)を確認してください〕.さらに,細胞内液はKが豊富であり,細胞外液はNaが豊富です.
臨床上の検査値は,細胞外液の血管内の値をみており,体全体のNaなどを推定するのは診察した人の判断となります.そしてここが差の出やすいところで,内科医の腕のみせどころとなります.いわゆる「よい塩梅を測る」のが腕です.
さて,本症例はそれほど難しくはありません.腹水があり,浮腫があります.ただし,Pltも17万/μLありますし,PT-INRも延長していません.T-Bilも基準範囲内です.肝硬変だとしても代償されており,Child-Pugh分類でもGrade A程度のようです.そうなると,糖尿病性腎症⇒ネフローゼ症候群に伴い体液量過剰があると考えました.
本症例はほとんど一発診断ですが,他の選択肢も考えておきましょう.まずはCSWSです.通常はクモ膜下出血後などに起きますので,①は不正解にしておきましょう.低張性脱水はどうでしょうか? やはり,血圧や腹水,浮腫などを考えると脱水の所見はないため,②も不正解です.
SIADHはどうでしょうか? ぜひ▶書籍『Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル』Case 2(☞69頁)も参考にしてください.この患者さんの診断上は結構困る点が出てきますね.なぜならばSIADHは原則として「脱水が存在しないこと」が条件だからです.そうなると体液量過剰の場合にはどうするかが問題ですが,細かく診断基準〔▶書籍『Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル』Case 2,表1(☞72頁)参照〕をみると,鑑別診断として「細胞外液量の過剰な低Na血症を来すものを除外すること.肝硬変,心不全,ネフローゼ症候群など」とあり,本症例では前述のとおり,このネフローゼ症候群を来していたわけです.よって③は不正解で,希釈性の低Na血症であり④が正解となります.
実は希釈性の低Na血症は結構難しい面があると捉えております.「希釈性」ということは,相対的に真水が過剰ですので,
●真水の再吸収があった
こちらの2つの可能性があります.
前者でよくみるのは心因性多飲症(psychogenic polydipsia) です.意外と多い疾患ですので,ここで解説しておきましょう.ただ飲むだけであれば「多飲症」でよいのですが,ここで症候性の低Na血症などを来すと「水中毒」と呼ばれます.
水を大量に飲むと,腎機能が正常であれば真水をどんどん排泄しますので,通常,尿浸透圧は100mOsm/kgH2O未満 になることが多いです.しかし,それでも真水を排泄できない場合には,身体の中の真水が蓄積していき,低Na血症になります.
不思議なことに,水中毒であっても体重は増えるのですが,全身性の浮腫を来して困った人をあまりみたことがありません.これは水中毒が生じる背景として,統合失調症や抗コリン作用がある薬剤による口渇で飲水が多くなるためだと思います.それ以上に,私見ですが「患者さんが低Na血症になっている状態を
そのような背景ですので,精神疾患を診る方は水中毒をどこかで勉強しておく必要がありますが,それは本書の役割ではないので,文献1の書籍を推薦しておきます.最近の基礎研究では,低浸透圧がドパミン系を活性化するなどという報告があり,一部の人にとっては水が中毒物質というのもうなずけます 2).
Q2の解説
さて,低Na血症をみたら尿電解質・浸透圧の確認でしたね.この患者さんは,uNa 60mEq/L,uK 32mEq/L,uCl 39mEq/L,uUN 727mg/dL,uCr 117mg/dL,uOsm 480mOsm/kgH2Oでした.
低Na血症なのに尿浸透圧が高い,ということはADH(antidiuretic hormone)が分泌されている,だからSIADHじゃないか!とおっしゃるかもしれません.しかし,ネフローゼや心不全,肝硬変などでは,体液量が過剰であるにもかかわらず,しばしばADHの分泌が生じています.この病態を表現する適切な用語がないのですが「paradoxical secretion」と個人的に呼んでおり,先ほど▶書籍『Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル』Case 1(☞63頁)でご紹介したSIADなのかもしれません.このような事象は昔から観察されていて,「心不全患者はのどが渇いて水をほしがる」などは聞いたことがあるかもしれません.ADHの主な分泌調整機構は「血清浸透圧」と「体液量」であると▶書籍『Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル』Case 2(☞69頁)と1章-2(☞8頁)で解説しましたが(体液量減少のほうが強い刺激です),このような病態でもADHが関与しているようです.
さて,治療の選択ですが,やはりオプションをいくつか持っておくほうがよいでしょう.まずは体液量過剰があるために減塩は必須で,①は正解です.水制限をするならばどのくらいか?という問題はありますが,病態的には真水を吸収して悪化させているのは間違いないので,水制限はしてもよいでしょう.私は10〜15mL/kg/日程度の水制限がよいと考えており,この患者さんでは700mL/日と指導しました.よって②は正解です.
さて薬物療法をどうするべきでしょうか? すでにフロセミドが投与されており,腎機能的にはまだこの量でよさそうな印象がありますが,足りないと思うのであれば,フロセミドを80〜120mgなどに増量するのはアリだと思います.よって③は条件付き正解です.また,フロセミドはバイオアベイラビリティが安定しないので,「空腹時に飲んでもらう」という手もオプションになります.
これですめばよいのですが,私はこのような病態にはトルバプタンがよいのではと考えております.トルバプタンはV2受容体拮抗薬,簡単に言えばADHの集合管への作用をブロックする薬です.本症例は
この患者さんでは,このトルバプタン導入を狙って入院してもらいました.トルバプタンを導入後は体重が順調に減少して45kg程度となり,下腿浮腫や腹水もほとんどなくなりました.肝機能障害なども今のところなく,外来で処方を継続することとしました.この先はコスト面との兼ね合いになりそうです.
Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル
輸液・水電解質のリアルに挑め。経験豊富なDr.長澤の思考過程がみえる20症例。
<内容紹介>輸液・水電解質のリアルに挑め。経験豊富なDr.長澤の思考プロセスがみえる20症例!つまずきやすい輸液や水電解質をDr.長澤が初学者にもわかりやすく解説。1章(総論)で学んだあとは、2,3章(各論)の症例問題を解いて、どんどん実践すべし。わからないところがあったらいつでも1章(総論)に立ち返ろう。解き終えた後は付録の関連検査値・式、逆引き疾患目次、Learning Pointまとめもご活用ください。
目次はこちらから
タグキーワード
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。