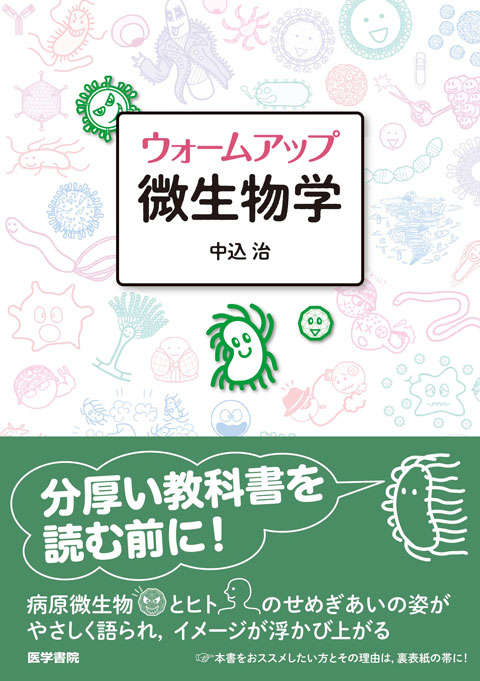医学界新聞プラス
[第1回]感染症と微生物学
『ウォームアップ微生物学』より
連載 中込治
2022.03.11
ウォームアップ微生物学
微生物学を勉強しようと思って教科書を手に取ってみたら,ずらりと並んだ専門用語やそのボリュームに圧倒された経験はありませんか? そんなあなたに,微生物学を本格的に学習する前段階,いわば準備体操として活用してほしい書籍が『ウォームアップ微生物学』です。微生物の伝播や病気を起こす仕組みを,身近な例を挙げながらプロの視点でわかりやすく解説しています。本書を最後まで読み終えてからもう一度教科書を手に取ると,病原微生物とヒトとのせめぎあいのイメージが浮かび上がり,理解が深まること間違いなし。
「医学界新聞プラス」では本書のうち“準備運動の準備運動”とも言える微生物学の基礎知識を前半2回で,宿主に病気をもたらす過程や伝播経路といった病原微生物の生き方を後半2回でそれぞれ紹介します。
今回お話しすること
微生物が起こす病気を感染症といいます。ですから,感染症の患者さんを診断し,治療し,また予防する土台をつくるために微生物学を学びます。ところが,「微生物が病気を起こす」という今の私たちにとっては当然のことが受け入れられたのはそれほど昔のことではありません。今回はそのいきさつについてお話しします。
武漢市は中国中央部にある近代的なメガシティです。また,この本のテーマである微生物学の分野では,中国初のBSL4実験室(危険度の高い病原体をあつかうための実験室)をもつ武漢ウイルス学研究所があります。この研究所が有名になったのは,10年がかりの探求の末,雲南省の山奥の洞窟のコウモリから2003年に突如出現した重症急性呼吸器症候群(SARS)の原因となったSARSコロナウイルスに酷似しているウイルスを発見したからです。
この武漢市で,2019年の暮れから年明けにかけて,原因不明の肺炎患者が立て続けに出ました。パンデミックに発展した新型コロナウイルス感染症のはじまりです。患者からはSARSコロナウイルスに似ているウイルスが見つかりました。これが新型肺炎の原因であると断定された新型コロナウイルス(SARSコロナウイルス2型;SARS-CoV-2)です。この新型コロナウイルスによって起こる病気は,世界保健機関(WHO)によって2019年型コロナウイルス感染症(COVID-19)と名づけられました。
このようになにか新しい伝染病が微生物によって起こることは,今日ではあたりまえの考えかたです。むしろ微生物の感染によって起こる病気であれば,ヒトからヒトへと伝染するかどうかとはかかわりなく,感染症といいます。ですから,感染症の患者さんを診断し,治療し,また予防するための知識の土台づくりのために,微生物学を学びます。
微生物が病気を起こすという私たちにとって当然なことがわかったのは,それほど昔のことではありません。それでは,微生物と病気との因果関係の発見に至ったいきさつをお話しします。
近代医学がわが国に入ってきたのは,江戸時代の末期,まもなく明治になろうとしていた激動の時期です。このとき徳川幕府はオランダ政府に日本人医師に西洋医学を教えるための軍医将校の派遣を依頼しました。その結果,陸軍軍医学校を卒業してまもない28歳の青年医師ポンペ・ファン・メーデルフォールト(1829-1908)が長崎に派遣され,1857年11月12日から5年かけて系統だった近代医学教育をはじめました。
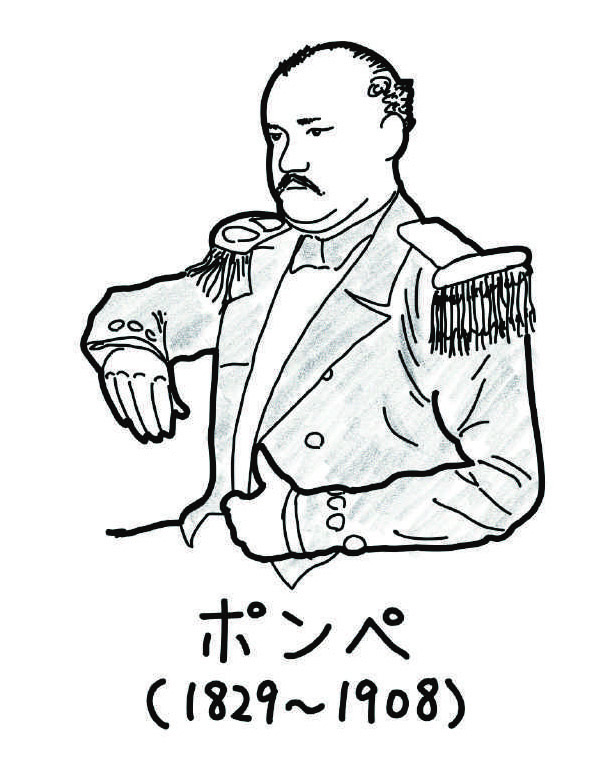
その翌年の1858年7月のことです。米国の船が清を経由して長崎に到着しました。するとこの船から持ち込まれたコレラにより流行がはじまり,全国へと広がっていきました。そこで,ポンペはコレラの治療と予防対策にも力をいれました。ところが,当時の西洋医学には病原微生物学はありませんでした。ですから,このヒトからヒトへと伝染していくコレラの原因が微生物であることは,ポンペを含めてだれも知りませんでした。
コレラが伝染病であるとわかっていながら,微生物が原因だとは思っていなかったとは,どういうことだったのでしょうか。微生物の存在が知られていなかったわけではありません。微生物は,オランダ人のアントーニ・ファン・レーウェンフック(1632-1723)によってさらに200年も前に発見されていました。余談になりますが,レーウェンフックと同じオランダのデルフトで,しかも同じ年に,画家のフェルメールが生まれています。レーウェンフックは自作の単レンズ顕微鏡を使って微生物の大きさがミクロン(μm)のレベルであるとほぼ正しく記載しています。しかし,レーウェンフックは,これらの微生物がなにをしているのかについては,あまり考えなかったようです。
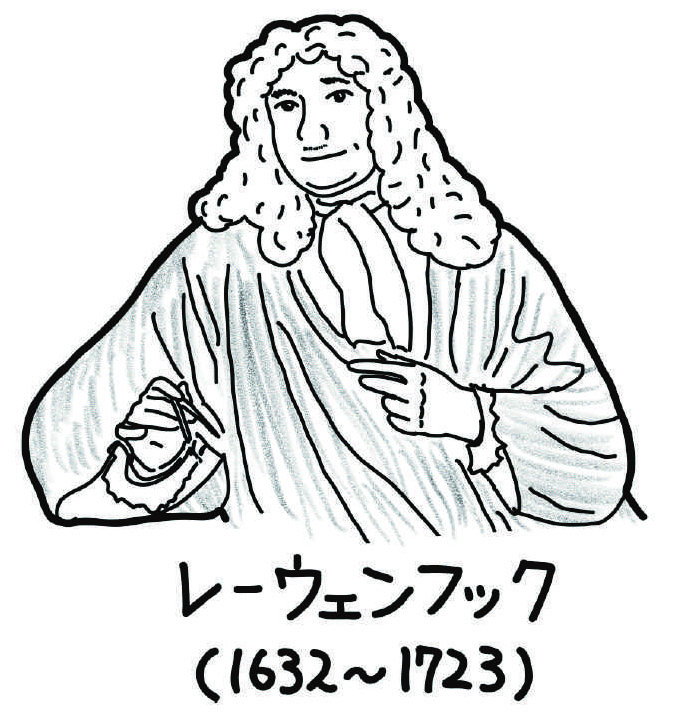
ポンペの時代のヨーロッパでは,7人にひとり,生産年齢人口にかぎれば3人にひとりが,不治の病である結核で亡くなっていました。結核が伝染病であるという考えもありましたが,体質説や遺伝説,気候による変調説など,その原因についてはいろいろ取りざたされていました。もっとも,結核の伝染病説にしても,当時の考えとしては「伝染病なので微生物が原因である」ということではありませんでした。現在の私たちには考えにくいのですが,病気が伝染することの説明に微生物を持ち出す必要はありませんでした。
有力な考えかたは,ものが腐敗するときに発生するにおい(汚れた空気)によって病気が伝染するというものでした。中世のヨーロッパではペストの流行があって,人口の1/4が亡くなったといわれています。当時の医師は防毒用のマスクとガウンを着用していました。これはペストにより汚染された空気による感染を防ぐためのものです。

鳥のくちばしのような格好をしているマスクは,病気を伝染する汚染されたくさい空気のにおいを除去するための香料を入れる場所です。病人や死体から発生する耐えがたいにおいがあったことは想像に難くありません。そのにおいそのものが伝染源であるとの考えに立てば,防毒マスクとして科学的にみて合理的なものだったといえます。こう考えると,危険な感染症の患者さんを診察し治療するときに現代の医師や看護師が着用するマスク,ゴーグル,防護服と比較して,着用する目的とその時代の理論からみた合理性は同じであるといえるでしょう。
微生物によって病気が起こるという病原微生物学の基礎は,フランスのルイ・パスツール(1822-1895)とドイツのロベルト・コッホ(1843-1910)によって築かれました。といってもふたりが肩を組んでおたがいを励ましあいながらこの新しい学問を確立していったということではありませんでした。パスツールは化学を学び,結晶の旋光性という分野で業績をあげた科学者として世にデビューしました。一方,コッホのスタートは地域医療に従事する医師でした。船医として熱帯地方を旅したいというコッホの夢想に困った妻から贈られた顕微鏡が運命を変えるきっかけとなり,微生物の世界に入っていきました。こういうおたがいの学問的バックグランドに加え,それぞれの故国がプロイセン=フランス戦争(1870-1871)に象徴されるライバル関係にあったことも,ふたりの交流の妨げになったことでしょう。
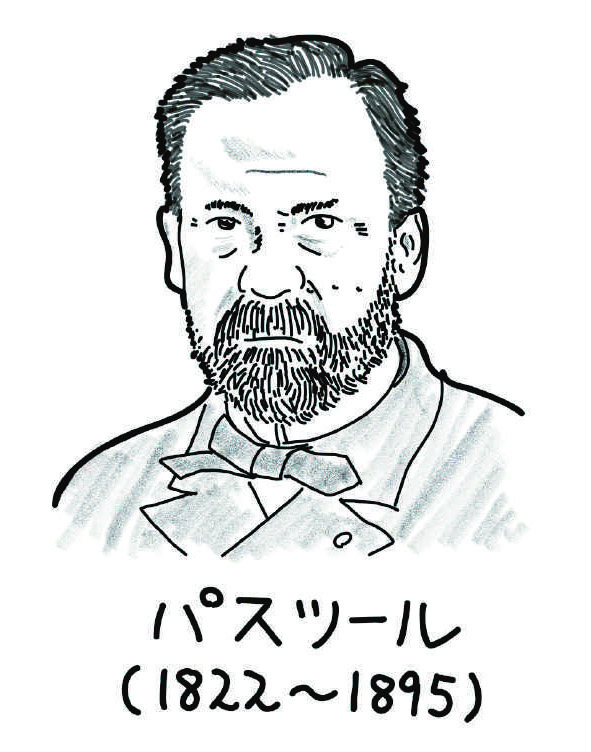
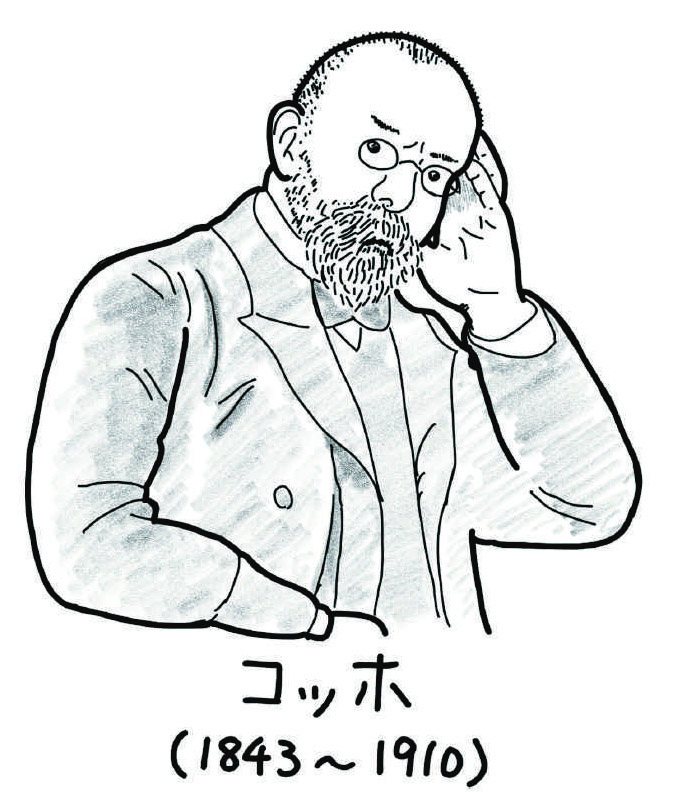
パスツールは,なにもないところからは微生物が発生してくることはないことを証明し,当時の常識であった生命の自然発生説を葬り去りました。また,ビールやワインなど醸造産業における腐敗菌混入の問題を解決しました。医学的には狂犬病のワクチンをつくったことが一番大きな貢献でした。
コッホは,病気の微生物原因説を確立する決定打を放ちました。それは1882年のドイツのベルリンでのできごとです。ここでコッホは,「結核は細菌の感染によって起こる」という結核の病因論を発表しました。彼は病原体としての微生物の役割を確立するために満たされなければならない条件を示し,従来の考えに固執する学者を説得しました。このコッホの努力により,微生物と伝染病が結びついて「感染症」という概念が成立したのです。
微生物学を勉強すると,コッホの条件を学びます。それは次のようなものです。
- ● 病気の病変部にいつも特定の微生物が見い出されなければならない。
- ● その微生物はその病気にかぎって見い出されなければならない。
- ● その微生物を純培養し,何代も培養したあとであっても,感受性のある動物に接種すれば,もとと同じ病気を起こさなければならない。
- ● 純培養を接種されて病気になった動物からふたたび同一の微生物が分離されなければならない。
ところで,このコッホの条件を覚える必要があるでしょうか。ありません。その理由は,みなさんが病気の微生物原因説,つまり,「微生物が原因になって病気が起こる」ということを受け入れているからです。しかし,コッホが結核の病因論を発表した当時の状況は違っていました。
微生物が病気の原因になるという考えかたに反対の学者は,病変部にいつも微生物が存在するのを否定していたわけではありません。しかし彼らは,病変部にいつも微生物がいても,かならずしもそれが原因ということにはならないのではないか,と考えました。病気がたどる一定の結果として,いつも病変部に特定の微生物が出てくるのだ,と考えれば不思議ではありません。
微生物の存在は原因であって結果ではない,という説得にコッホの条件が役立ったのです。たいていの学者はコッホの条件による説明で納得しました。いったん多くの人がなるほどと納得して新しい常識ができれば,世の中は一変して,もはやだれも疑わなくなります。
実は感染症の原因となっている微生物の多くが,このコッホの条件を満たしません。そもそもコッホ自身の発見であるコレラ菌もコッホの条件を満たしませんし,新型コロナウイルスもそうです。それでもコレラがコレラ菌によって起こることは,今やだれも疑いません。
コッホの条件には,微生物が病気を起こすことがあるという考え自体を拒んでいた19世紀のメインストリームの学者たちを納得させるという役割がありました。微生物によって病気が起こることをだれも疑わなくなった現代では,その歴史的使命を終えています。ですから,1つひとつの病気についてコッホの条件を厳格に適用して微生物との因果関係を証明する必要はありません。
微生物が病気を起こすということが病原微生物学の大もとにある考えかただといっても,今日では「コレラの原因はコレラ菌だ」というだけではだれも満足しません。私たちにとって「原因がわかる」というのは,コレラ菌がどうしてコレラという病気(大量の水様性の下痢による脱水症)を起こすのか,そのメカニズムがわかることです。
口から侵入したコレラ菌が小腸に達すると,小腸の内面をおおう粘膜上皮細胞に付着し,増殖し,毒素を分泌します。その毒素の作用によって大量の水分が腸管内へと失われていくことが,コレラでみられる下痢の原因です。コレラ菌は粘膜に侵入することも破壊することもありません。ですから,下痢は粘膜の破壊によって,水分の吸収ができなくなるために起こるのではありません。ではコレラ毒素はどうやってはたらくのか,その分子レベルでのメカニズムは……というように,1つのことがわかればさらに新たな疑問がつきることなく出てきます。
こういう疑問を追究し解決しようとする過程で,今までの説明では納得できないことや,現在の考えに不十分なところがあることに気がつくようになります。これが新しい発見につながります。このような知の先端は,いたるところにひそんでいます。微生物学には今もこれからも新しい発見や考えかたが生まれる余地がたくさんあります。
それでは,感染症の原因となる微生物にはどんなものがあり,どんな生物学的特徴があるのかというところから話をはじめましょう。
今回のお話のキーコンセプト
- ● 病気がヒトからヒトへと伝染することも顕微鏡で見なければわからない微生物の存在も古くから知られていましたが,病気の微生物原因説が確立したのは医学の歴史の中では最近のことです。
- ● コッホの条件とは,ある微生物がある病気の原因であるという因果関係を示すために満たすべき条件でした。その役割は結核の原因が細菌であることを受け入れなかった19世紀の学者たちを納得させるという歴史的なものでした。
- ● 病気がある微生物によって起こる,というだけではなにもわかったことにはなりません。私たちにとって「原因がわかる」というのは,その微生物がその病気を特徴づける症状を起こすメカニズムがわかることです。
ウォームアップ微生物学
本格的に微生物学を学ぶ前に,
まずは全体像と大事なトコロのイメージをつかもう!
<内容紹介>医療系の学生にとって病原微生物学の勉強って必須だけれど,覚えることがたくさんあって大変そう…。そこで,本格的に微生物学を学ぶ前にまずはアタマの準備運動をしましょう。本書で一足先に微生物学の全体像と一番大事なトコロのイメージをつかんでおけば,きっと大学の講義や分厚い教科書にもすんなり入っていけますよ。医学生やコメディカル学生はもちろん,病原微生物についてきちんと知りたい一般読者の方にもおすすめです!
目次はこちらから
タグキーワード
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。