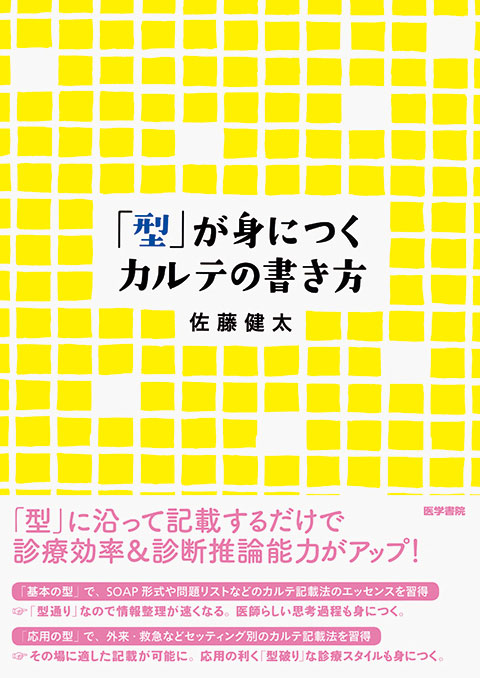- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2021年
- 医学界新聞プラス 「型」が身につくカルテの書き方 診療情報提供書
医学界新聞プラス
[第2回]診療情報提供書
『「型」が身につくカルテの書き方』より
連載 佐藤健太
2021.05.21
「型」が身につくカルテの書き方
日々のカルテ記載が「何となく」の作業になっていませんか? カルテの重要性は認識しているものの,系統立てて学ぶ機会もなく,独学に頼らざるを得ない場合も多いはずです。こうした状況に危機感を抱いた佐藤健太氏は,10年の歳月をかけて見いだしたカルテ記載法とその指導法を週刊医学界新聞の連載『「型」が身につくカルテの書き方』にまとめました。同連載を基に大幅加筆された書籍より,「おまけの型」を2回に分けて紹介していきます。
学生のうちは縁がないかもしれませんが,医師になれば「診療情報提供書」を書く機会が増えます。診療上必須であるカルテに比べると,「書く意義が感じられない」「書くのが面倒」「書き方がわからない」といったネガティブな印象が強いかもしれません。また,入院や転科をお願いしたかったのに丁寧なコメントの書かれた診療情報提供書とともに差し戻されたり,意見が欲しかっただけなのに勝手に投薬を始められてしまったりと,思うような対応をしてもらえずもどかしい思いをしたこともあるかもしれません。
これらの問題は,気が利かない紹介相手だから起きたというわけではなく,「診療情報提供書の書き方」を知らない自分の落ち度でもあります。ここでは,診療情報提供書の意義や紹介の形態について解説した後,具体的な診療情報提供書の書き方を提示します。
診療情報提供書の意義や種類
専門分化が進めば進むほど,質や効率改善のためにコミュニケーションが重要となりますし,コミュニケーションの失敗は患者にとって有害な転帰にすらつながりえます。最初に例に出したように,情報の伝え方に問題があったせいでこちらの意図と異なる介入がされるようであれば,患者に対して健康上の実害が発生する可能性があり,せっかくそれまで丁寧な診療とカルテ記載をしていても台無しです。目的通りに意図を伝えることのできるコミュニケーションスキルを身につけましょう。
医師同士のコミュニケーションの方法は口頭,電話,カルテ,電子メールなどいろいろありますが,ここでは記録に残って伝達ミスが少なく,忙しい相手の時間を奪わずにやりとりが可能な「診療情報提供書」に絞って話を進めます。また診療情報提供書には様々な種類があり,専門医・高次医療機関への紹介,セカンドオピニオンの依頼,患者転居などに伴う転医の依頼,退院時のかかりつけ医への逆紹介,X線写真などの資料請求依頼,診断書などがあります。ここでは,診療情報提供書の全ての要素が詰まっている「高次医療機関への紹介」について解説します。
診療情報提供書を記載する以前の注意点
1)患者への説明
紹介の理由は,事前に患者に説明すべきです。「患者を紹介する」という行為は,患者にとっては「診療拒絶」と捉えられる可能性が高いものです。その精神的ダメージのせいで自分と患者との信頼関係がギクシャクしたり,紹介先受診拒否につながったり,特に精神疾患のある患者では病状自体が悪化するといった悪影響が起こりえるため,それなりの配慮が必要です。説明するときには「紹介する」という事実だけでなく,紹介が必要な理由(病状が自身の専門範囲を超えているなど)や,患者にとっての意義(より質の高い診療が受けられる可能性など),拒絶ではなく今後も関係が続くというメッセージを意識的に添えましょう 1)。
2)費用負担
紹介には一定の費用負担が発生します。親切のつもりで紹介したのに費用が発生し,その上診療情報提供書の内容がまずくて,患者になんの利益も生じなかったのでは目も当てられません。
現在の制度では,特定機能病院を受診する際,初診患者が紹介状を持っていないと特定療養費を請求されます。一方で,診療情報提供料という制度もあり,診療情報提供書を作成するだけでも患者に経済的負担がかかります。特定療養費よりも診療情報提供料の値段のほうが高くなる場合もあり,事前に患者に対して費用負担について説明することと,その負担に見合う内容を記載できるよう意識しましょう。
普通の診療情報提供書作成⇒診療情報提供料Ⅰ:250点=2,500円(3割負担患者で750円)
診療情報提供書に検査結果も添付した場合⇒+200点=2,000円
セカンドオピニオン目的の場合⇒診療情報提供料Ⅱ:500点=5,000円
紹介の2形態
日本語では「紹介」という一つの用語しかありませんが,海外では二つの形態を意識的に使い分けています 2)。
●Consultation……いわゆる相談。「患者の主治医権は自分が持ったまま」で,他の医師に意見を求めること。その意見を取り入れるかどうか,実行するかどうかは自分に裁量権がある状態。
●Referral……いわゆる紹介。「患者の主治医権を相手に委ねる」行為で,実際に検査・治療するかどうかは相手の裁量となる。主治医権の譲渡と言ってもよい。
この違いが明確になるように,入院させてその間完全委任したいのか,退院後はこちらに戻してもらいたいのかや,外来併診を続けて相手には専門領域だけ関与してほしいのかなどを明記する必要があります。
なお,Consultation/Referralのどちらであっても,紹介する相手は「人」であって,病院や科ではありません。同じ科でも医師によって考え方が大きく異なるのは,臨床実習を経験していればわかるでしょう。適切な紹介相手を個人的に知っていて,相手のツボを突いた紹介をできるかどうかも医師として必要な能力の一つです。
また,紹介相手は医師に限らず,看護師や保健師,ソーシャルワーカーなどでも良いことになっています。実際に筆者もいろんな職種の方に対して,正式な診療情報提供書を作成し連携を取っています。電話やカンファレンスだけの関係だったころよりは診療方針の共有や情報交換がしやすくなり診療の質が高まったと感じています。
記載のポイント
以下3点を意識しながら,下記の診療情報提供書記載例を参照してください。
1)紹介目的を明確に……ConsultationなのかReferralなのか。具体的に何をしてほしいのかは書かなければ伝わらない。
2)自分の見立てもきちんと書く……自分なりの診断と,自分が持っている病歴を書く。フィードバックがもらえるかもしれない。
3)患者の希望や事情も記載する……基礎疾患や生活背景などはかかりつけ医が一番知っている。診療方針を左右することもある。
細かいポイントはカルテの解説欄で補足していますが,病院や診療科,指導医の慣例はさまざまなので,柔軟に形式を変えてください。自分が学生・研修医のときは,「総合医からの診療情報提供書は長いから読まずにイチから診察する」と言っていた医師や,「時候の挨拶や敬称,脇付を間違える奴はダメな医者だ」と判断して診療情報提供書を読まずに捨てる医師もいました。また,単刀直入すぎる診療情報提供書や,他科から具体的な要求を書かれるとプライドを傷つけられたと激高する医師も複数いました。一番重要な「相手」に合わせて適切な書き方を変えましょう。相手がどういう人かわからなければ,指導医や,勤務歴の長い看護師・事務職員に聞くといろいろ教えてくれるので参考になります。
診療情報提供書の実際
〇〇中央病院 呼吸器内科 〇山△郎先生❶ 御机下❷
問題リスト❸
#1.軽症市中肺炎,#2.慢性肺気腫,
#3.糖尿病,#4.認知症(軽度,せん妄歴なし),#5.家族介護力不足
紹介目的❹:#1について,入院治療のご依頼
平素より大変お世話になっております。また,ご多忙の中患者紹介を受けていただき誠にありがとうございました。❺
患者△岡○輔様(男性82歳)は,以前にも肺炎で貴科入院治療歴があり,普段は#3.4.5にて当クリニックに通院していました。このたび肺炎を発症したため,入院加療をお願いしたくご紹介させていただきました。❻
2日前から咳・痰と労作時息切れが出現し徐々に増悪したため本日午前当院外来を受診されました。受診時JCS 2(普段と同程度),BP 112/56,HR 98・整,RR 26,SpO 2 92%(室内気,普段は96~98%),BT 37.6度,身体診察では右背側にCracklesを認め,胸部X線検査にて右下肺野に浸潤影を認めたため肺炎と診断しました。A-DROPでは年齢・意識障害該当で2点であり入院適応と考えました(同封の検査結果用紙もご参照ください)。❼
短期間でかまいませんので入院の上で精査・加療をしていただければ幸いです。❽
特記事項❾:軽度ですが認知症があり,入院によるせん妄・転倒や廃用進行のリスクはありますが,過去の入院ではそのようなエピソードはありませんでした。ご家族は足腰の弱い奥様だけであり,病状説明への同席や同意書署名は可能ですが,自宅看病や外来通院は困難であるため急性期だけでも入院加療できればと考えました。
なお,当院は時間外対応は困難で,実施可能な検査は胸部X線のみ(採血は外注)になりますが,ADL不十分でも訪問診療等での対応は可能です。お呼びいただければ退院調整カンファレンス等への参加もさせていただきます。ご不明の点がございましたら,書面でお問い合わせいただくか,当院内科の佐藤(内線2824)までご連絡ください。❿
処方内容⓫ グリメピリド 1 mg分1朝食後,ドネペジル 5 mg分1朝食後
〒003-0804 北海道札幌市……
TEL 011-811-…… FAX 011-820-……
病院名 ○○ファミリークリニック
平成27年3月12日⓬
総合診療科 佐藤健太 拝⓭
❶相手の医師名:「○○病院 △△外来御中」ではなく,できるだけ個人名で送ろう。誤字や同姓異名に注意。
❷脇付:「御机下」や「御侍史」など。基本的にはどちらも不要で,医師の間でしか使わないもの。本来は机や侍史に対する謙譲ではないので「御」も不要だが,慣例なので病院のルール通り使っておいたほうが無難。脇付自体は相手への敬称ではないので,その前の「様」や「先生」は省略できない。また,「○○病院□□科外来担当先生」など具体的な相手がいない場合は,「御中」など特定の組織・部門宛てに使える脇付が正しい。
❸問題リスト:診療情報提供書でもやはり問題リストは大事。これを見るだけで何の紹介かほとんど分かるし,宛先を間違えた場合もすぐに気付く。
❹用件:「精査・加療のご依頼」など漠然として書き方ではなく,「抗癌薬治療についてのセカンドオピニオンのご依頼」や「#1に対する手術を前提としたご紹介」など,相手に何をお願いしたいのかを明記したほうがよい。
❺挨拶:筆者としては,業務連絡なので挨拶は省略してすぐに本題に入るべきと考える。形式的に付けたほうが無難だが,その場合もできるだけ短くして,相手をおもんぱかるような一言を毎回選びたい。
❻背景:「この患者はあなたに紹介されるだけの理由がある」ということがわかるように,紹介先への受診歴や,紹介相手の専門領域の疾患名などを記載しておくとよい。
❼医学的情報と自分なりの見立て:紹介先が高次医療機関の専門医や高名な医師だと書きにくいが,それでもきちんと書いたほうがよい。相手方を受診した時点で病状が変わっているかもしれないし,長くかかりつけ医をしていた自分だからこそ判断できた情報もあり,いずれにしても相手の参考になる。また,くどさや押し付けがましさがない範囲で適切に書けば,診断が合っている/いないにかかわらず,フィードバックをもらえることがある。なお,検査データをどう解釈するかは医師の技量による部分が大きいので,できるだけ検査値を印刷したものや画像データを焼いたCD-Rなどを同封したほうがよい(CD-Rだけだと受け取った側でパソコンがすぐ使えない場合に面倒なので,重要な所見は本文に書くべき)。また,略語や病型・病期分類は省略せず丁寧に記載する。
❽具体的な要望:❹の用件と同じ内容を繰り返す。これを省くと,本章の冒頭の例のように期待外れな対応をされてしまいがち。
❾特記事項:本人の性格,家族関係や経済的問題,臓器障害やアレルギーなど,相手が方針を決める上で重要な情報をここに簡潔にまとめる。本文の中で書くと膨大となって用件がぼやけてしまうので,「本筋とは関係ないが重要な参考資料」という位置づけでここに書くとよい。
❿連絡方法を具体的に明記しておくと親切。特にグループ診療をしている場合や研修医名で作成した場合,非常勤で緊急の問い合わせが来ても対応できない場合などは明記すべき。また,自院のフォロー体制(時間外対応状況や実施可能な検査・治療の範囲など)も記載したほうがよい。
⓫処方内容:病状の判断をしたり,今後相手方で診療を引き受ける場合はこの内容を元に引き継いだりするので,具体的な商品名+用量用法を明確に書く。
⓬日付:公的文書として必須。また,どの時点で書かれたものかで判断が変わることもあるので重要(退院時に書かれた診療情報提供書が3日後に届いたが,患者は退院2日後に急変してすでに当院に入院していた場合など)。
⓭自分の所属と名前:筆者が初期研修医のときは,差出人欄に自分の名前が自動印刷されても,それを二重線で消してフルネームで自筆し,さらに後ろに「拝」を付け,さらにハンコも押すように指導された。しかし,「拝」は自分の「姓名」ではなく「姓だけ」の後につけて敬意を表す語であり,「姓」だけ書けばよいくらい親しい(が少し敬意を示したい)相手にしか使えない。部活の親しい先輩や,昔同じ医局で世話になった一つ上の先輩くらいか。それよりはフルネームで自筆がいい。また,公式文書では記名(自動印刷やハンコや代筆)だけでは不十分だが,記名+押印か,署名(自筆でフルネームを書いてハンコなし)のどちらかで十分なので,自筆すればハンコは不要。
参考文献
1)望月亮:紹介状の書き方――紹介目的と自分の見立て,患者の希望を明確に書く.治療.96:592-3,2014
2)McWhinney IR, et al:Part III The Practice of Family Medicine 18:Consultation and Referral. Textbook of Family Medicine. 3 rd ed, Oxford University Press, 2009
「型」が身につくカルテの書き方
「型」に沿って記載するだけで診療効率&診断推論能力がアップする!
<内容紹介>「週刊医学界新聞」の人気連載を書籍化。「基本の型」の部で,SOAP形式や問題リストなどのカルテ記載法のエッセンスを習得(⇒医師らしい思考過程も身につく)。「応用の型」の部で,外来・救急などセッティング別のカルテ記載法を習得(⇒応用の利く「型破り」な診療スタイルも身につく)。「型ができていない者が芝居をすると型なしになる。型がしっかりした奴がオリジナリティを押し出せば型破りになれる」(by 立川談志)。
目次はこちらから
タグキーワード
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。