がんと感染症の関係(後編)(森信好)
連載
2016.07.18
目からウロコ!
4つのカテゴリーで考えるがんと感染症
がんそのものや治療の過程で,がん患者はあらゆる感染症のリスクにさらされる。がん患者特有の感染症の問題も多い――。そんな難しいと思われがちな「がんと感染症」。その関係性をすっきりと理解するための思考法を,わかりやすく解説します。
[第2回]がんと感染症の関係(後編)
森 信好(聖路加国際病院内科・感染症科医幹)
(前回からつづく)
前回(第3179号),がん患者の感染症に対応するためには ,「免疫が低下するから感染症が起きる」というぼんやりとした理解で挑むのではなく,免疫不全の状態を4つ(バリア・好中球・液性免疫・細胞性免疫)のカテゴリーに分けて考える方法を紹介しました。以下のような概念図を用いて,がん診療に関連する感染症について理解しようというものです。
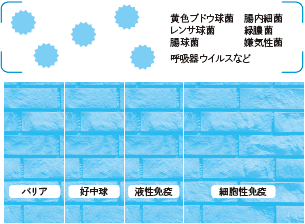
免疫の壁が崩れるとき
原疾患(がん種)によって,または化学療法の方法などによって,低下する免疫が異なってくるという点は,前回も簡単に触れました。今回はどのような場合にどの免疫が低下するのか,すなわち「免疫の壁」が崩れてしまうのかについて説明していきましょう。さらに,それぞれの「免疫の壁」が崩れることで,どのような微生物が姿を現し,どういった感染症を引き起こし得るかを提示したいと思います。
自然免疫
自然免疫には主にバリアによる防御と,マクロファージや好中球による防御システムがあります。これらの免疫が低下したとき,どのような微生物が感染症を引き起こす可能性があるのかを見ていきましょう。
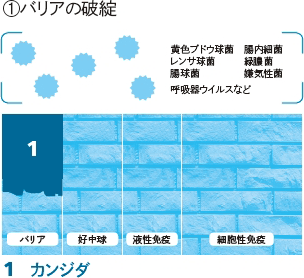
バリアとは,皮膚や消化管・呼吸器・泌尿器などの粘膜による防御システムです。がんそのものによる浸潤や閉塞,手術,放射線療法,化学療法,カテーテル挿入などにより,そのバリアが破綻すると,本来,自分の体表面や管腔内にいる微生物が体内に侵入し,感染を引き起こすケースがあります。例えば,中心静脈カテーテルにより皮膚のバリアが破綻し,皮膚に常在していた黄色ブドウ球菌やカンジダがカテーテル関連血流感染症を起こす。または,化学療法によって腸管粘膜のバリアが破綻して,腸管内に常在していた腸内細菌やカンジダがbacterial translocationを引き起こすといった具合です。
なお,bacterial translocationは,化学療法による好中球減少でも起こります。ですから,バリアの破綻はそれ単一で感染症が引き起こされることもありますが,他の免疫低下と相乗的に作用して感染症が引き起こされることも多いというイメージを持っておくとよいと思います。
②好中球減少および機能異常(低リスク群・高リスク群)
発熱性好中球減少症(Febrile Neutropenia:FN)はいわゆる「内科的緊急疾患」です。つまり,急速な経過で病状が進行し得るため,早期に適切な対応をすることが重要になります。
ただし,FNだからといって全てが「緊急」というわけでもありません。そこで重要なのが,FNのリスク分類です。リスク分類については次回以降に解説するとし,ここでは「低リスク群」と「高リスク群」に大別できると理解しておいてください。
おおまかに,低リスク群は固形腫瘍に対する化学療法で短期間の好中球減少,高リスク群は急性骨髄性白血病(AML)などの血液腫瘍そのものや,それに対する化学療法により1週間以上遷延する高度(100/μL未満)の好中球減少,と考えておくといいでしょう。なお,低リスク群は条件によっては外来治療が可能なこともありますが,高リスク群は緊急疾患であり入院による加療が必要になります。
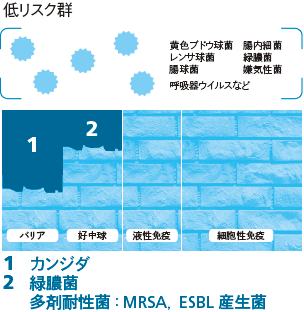
まず低リスク群では,化学療法によって「バリア」の壁が下がりますので,基本的にはbacterial translocationがメインになります。これまでに抗菌薬の暴露があっ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第1回]心エコーレポートの見方をざっくり教えてください
『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.04.26
-
医学界新聞プラス
[第3回]冠動脈造影でLADとLCX の区別がつきません……
『医学界新聞プラス 循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.05.10
-
医学界新聞プラス
[第1回]ビタミンB1は救急外来でいつ,誰に,どれだけ投与するのか?
『救急外来,ここだけの話』より連載 2021.06.25
-
医学界新聞プラス
[第2回]アセトアミノフェン経口製剤(カロナールⓇ)は 空腹時に服薬することが可能か?
『医薬品情報のひきだし』より連載 2022.08.05
-
対談・座談会 2025.03.11
最新の記事
-
対談・座談会 2025.04.08
-
対談・座談会 2025.04.08
-
腹痛診療アップデート
「急性腹症診療ガイドライン2025」をひもとく対談・座談会 2025.04.08
-
野木真将氏に聞く
国際水準の医師育成をめざす認証評価
ACGME-I認証を取得した亀田総合病院の歩みインタビュー 2025.04.08
-
能登半島地震による被災者の口腔への影響と,地域で連携した「食べる」支援の継続
寄稿 2025.04.08
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
