がんゲノム医療と緩和ケアの融合
進歩するがん治療をどう支えるか
寄稿 梶浦 新也
2025.09.09 医学界新聞:第3577号より
2019年に保険適用されたがん遺伝子パネル検査は,約5割のケースに治療提示をするに至っています。しかし実際に治療を受けられる方は検査実施者の1割とされ1),背景にはさまざまな問題があると言われています。
具体的には,検査実施から結果を得る約1か月の間に体調が悪化し治療を受けられないケース,提示された薬剤が保険適用外であり金銭面で断念せざるを得ないケース,大都市圏のがんセンターで治験が実施されているものの距離的な問題で参加ができないケースなどが挙げられます。治療アクセスの問題については愛知県立がんセンターでリモート治験が開始されるなど解決手段が登場しており,当院もリモート治験に参加し著効例を経験したことから,今後の治験の在り方として期待をしています。
しかしながら先ほどお伝えしたように,依然としてがん遺伝子パネル検査実施例における治療到達率は低いままであり,この数値を改善するための方策が多方面から模索されています。
がん遺伝子パネル検査実施による緩和ケア環境整備の遅れ
関連して意識しておかなければならないのは緩和ケアの話題です。がん遺伝子パネル検査の結果待ちの期間は,患者は化学療法が効果を発揮することに期待をしているため,在宅での緩和ケアなどの環境整備が進みにくい面があり,緩和ケアの提供側から不満が挙がることがあります。この問題に対し私は,緩和ケア外来で実施される内容を,患者ががんゲノム外来を訪れた際に紹介できれば解決するだろうと考え,診療を行ってきました。
もちろん一般的な施設においてがんゲノム外来医と緩和ケア外来医は別であり,そこに至るまでの医師としてのキャリアも大きく異なることが多いため,両者の役割を担うことを一般化するのは難しいかもしれません。しかし,積極的な治療と早期からの緩和ケアの提供を並行して行うことで患者に与えられるメリットは計り知れません。がんゲノム外来から緩和ケア外来に患者をつなぐ取り組みは今後ますます重要になるために,ぜひ各施設で検討をしていただければうれしいです。
当院にはがんゲノム外来と緩和ケア外来を併任する看護師も在籍しており,両外来の橋渡し役を担ってくれています。このような看護師の人員配置であれば,多くの施設で再現可能かもしれません。
悪い知らせを伝える場としてのがんゲノム外来
化学療法中の患者の多くは,自身のがんが治癒可能であると誤解しています。Weeksらによれば,治癒不能な肺がん患者の69%,大腸がん患者の81%が治癒可能だと認識していたと報告されています2)。またこの報告では,医師との関係が良好な方ほど治癒すると勘違いしているとも指摘され,正確な病状理解を求めると,医師―患者関係が悪化するリスクもあるようです。実臨床でもこの報告のとおりで,治らないことを患者に伝えるのは容易ではなく,治らないことの理解を求めようとすると,医師としての信頼を失ってしまい,通院が自己中断されることもあります。このような経験から,悪い知らせを伝えにくいと考えるがん治療医は多く,緩和ケア外来を紹介する場合もあるでしょう。しかしながら,化学療法中に緩和ケア外来を紹介されることに対して抵抗を示す方がいるのも事実です。
その点がんゲノム外来であれば,化学療法中でも抵抗感なく受診される患者が多く,がんゲノム外来で緩和ケア外来の役割が果たせれば,悪い知らせを伝える場としても機能する可能性があり,「治らない」という現実を初めて理解したという患者が当院でも実際に多くいらっしゃいます。また,厳しい病状を説明するときには,医師への信頼が揺らぎ通院の自己中断につながることのないよう,看護師とともに行うことも大切なポイントです。がん患者の看護に従事した経験を有する看護師とともに病状説明を行えばがん患者指導管理料イが算定できるケースもあり,多職種で...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
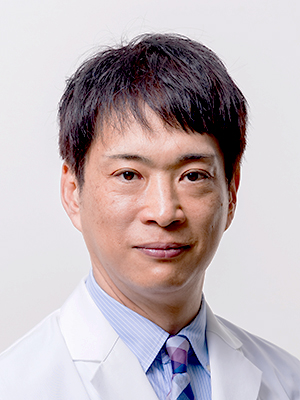
梶浦 新也(かじうら・しんや)氏 富山大学附属病院腫瘍内科・緩和ケア科 講師
1999年富山医薬大(当時)卒。同大病院や富山県内の関連病院,国立がん研究センター東病院での研修を経て,2008年より富山大病院第三内科医員。13年同大大学院医学薬学研究部臨床腫瘍学講座特命助教,14年同大病院集学的がん診療センター緩和ケア部門長,18年同臨床腫瘍部診療講師・副部長などを経て,24年より現職。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
