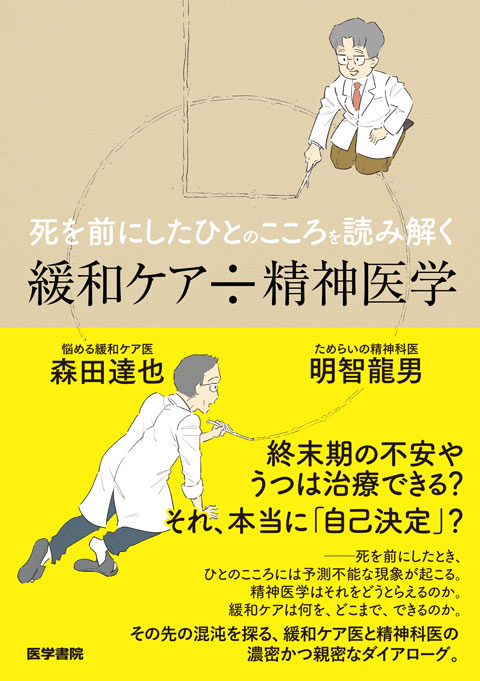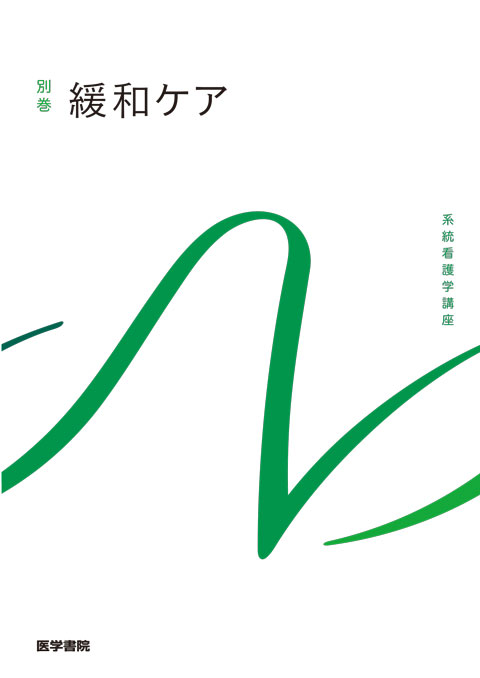患者報告型アウトカムを看護の臨床で活用する
対談・座談会 宮下 光令,松村 優子
2025.02.11 医学界新聞:第3570号より

近年,患者当事者の声を医療に反映するための方策として,患者報告型アウトカム(Patient Reported Outcome:PRO)への注目度が高まっている。PROに関するエビデンス構築は世界的に発展途上であるものの,日常的なPRO利用で患者の生存期間が延長するなどポジティブな結果が得られつつある。
このたび本紙では,緩和ケア領域でPROに関する研究に取り組む宮下氏,PRO評価スケールの一つであるIPOS(Integrated Palliative care Outcome Scale)の臨床への導入を経験した松村氏による対談を企画。PRO導入を成功に導くヒントを探るとともに,臨床にもたらされる効果について考えた。
宮下 松村さんとはもう長い付き合いになります。初めてお会いしたのはいつ頃でしたでしょうか。
松村 2011年頃,勤務先の在宅クリニックでの看取りケアのクリニカルパス導入に当たってでした。その後,私が通う京都大学大学院のゼミに宮下先生がいらした2018年頃,ちょうど当院は緩和ケア病棟を設置しようとしていて,提供する医療の質をどう測るかを検討していました。宮下先生からPRO,IPOSについて伺い,当院への導入を考えるようになった経緯があります。
宮下 貴院にPROが導入されたことで,本学大学院生の研究にもご協力いただくなどお世話になっています。PRO導入の経緯やその中でのご体験については,後ほど詳しく伺えれば幸いです。
医療者が一切介在しない評価方法であるPRO
松村 初めに宮下先生から,改めてPROについて簡単にご解説していただけますか。
宮下 PROの定義は「被験者の症状やQOLに関して,自分自身で判定し,その結果に医師をはじめ他の者が一切介在しないという評価方法」です。簡単に言うと,患者さんの主観的な症状や考えにしっかり耳を傾けるというだけのことなのです。ですから,看護師が日常臨床の中で当たり前のように行っていることでもあります。例えば患者さんに「今の痛みの程度は0~10点のうち何点ですか?」と質問し,点数を記録するといった痛みのスケールもPROと言えます。
松村 痛みは普段から患者さんに尋ねている施設も多いと思いますが,症状や症状以外の気がかりについてなど,系統的に漏れなく尋ねることがPROを運用していくに当たっては重要だと考えられていますね。
宮下 その通りです。国内外を問わず日常臨床ではそのときどきに関心のある症状について尋ねることが多く,系統的に漏れなく,ルーチンとして決まった質問項目に基づいてアセスメントを行うことがあまりなされてきませんでした。
松村 近年PROに注目が集まりつつある背景には何があるのでしょうか。
宮下 流行のきっかけになったのは,医療者は症状を過小評価する傾向があるとの結果を示す研究1)でした。副作用を評価するためにCTCAE(Common Terminology Criteria for Adverse Events)という基準が用いられますが,これは医療者が評価を行う尺度です。そのため実際に患者さん本人にも確認を行ってみると,症状の程度の認識にずれがあるということがBaschらの研究によって明らかになりました。その後,CTCAEに関しては患者による主観的な評価を行うバージョンとしてPRO-CTCAEが作成され,今では広く用いられています。
加えて,患者QOLを重視する傾向が強まってきたこともPROが注目される理由の一つに挙げられます。QOLの考え方自体は1990年代以前から存在しましたが,当時のがん医療においては治療薬による有害事象は耐えるべきものとの認識もまだ根強かったかもしれません。しかし,有害事象をコントロールすることは治療の完遂にとっても,その人の生活にとっても大事なことです。患者中心の医療を実現するには,症状の正確なアセスメントが欠かせません。そこで役に立つのがPROというわけです。
PRO導入に伴う負担ゆえの難しさ
宮下 とは言え,PROの臨床への導入には難しい側面もあります。私自身,一度失敗した経験があります。
松村 失敗の経緯を知りたいです。
宮下 25年ほど前,緩和ケア領域で研究を始めた頃に,STAS(Support Team Assessment Schedule)という評価尺度の日本語版(STAS-J)の開発に取り組んでいました。当時から緩和ケアの世界ではPROの考え方が登場していて,例えばカナダ・エドモントンではBruerらがESAS(Edomonton Symptom Assesment System)という症状評価スケールを用いて,1日2回の測定結果をベッドサイドに置くことで多職種による情報共有を図る取り組みを行っていました2)。そこで私もESASを導入する形で臨床でのPRO活用に取り組んでみたものの,どうにもうまく定着しなかったのです。
松村 原因はどこにあったのでしょう。
宮下 導入方法にあったと私は考えています。PROでは評価スケールを用いた患者への聞き取りが必須ですから,それを行う医療者はもちろん,患者側にも負担が生じます。病棟や施設が培ってきたカルチャーやそこにある人間関係といった微妙なニュアンスを読み取り配慮しなければ,受け入れてもらうことは難しいです。導入に当たってはそうした委細を...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

宮下 光令(みやした・みつのり)氏 東北大学大学院医学系 研究科保健学専攻緩和ケア看護学分野 教授
1994年東大医学部保健学科卒。国立がんセンター東病院(当時)などで看護師として臨床を経験後,97年東大大学院医学系研究科修士課程修了。同大大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻講師を経て,2009年10月より現職。博士(保健学)。専門は緩和ケアの質評価。

松村 優子(まつむら・ゆうこ)氏 京都市立病院 看護副部長 / がん看護専門看護師
2011年神戸市看護大大学院看護学研究科博士前期課程修了。修士(看護学)。日本バプテスト病院副看護師長を経て,12年より現職。がん看護専門看護師。18年の導入以降,院内でのIPOS普及を精力的に進めている。現在は京大大学院医学系研究科にて研究を継続中。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。