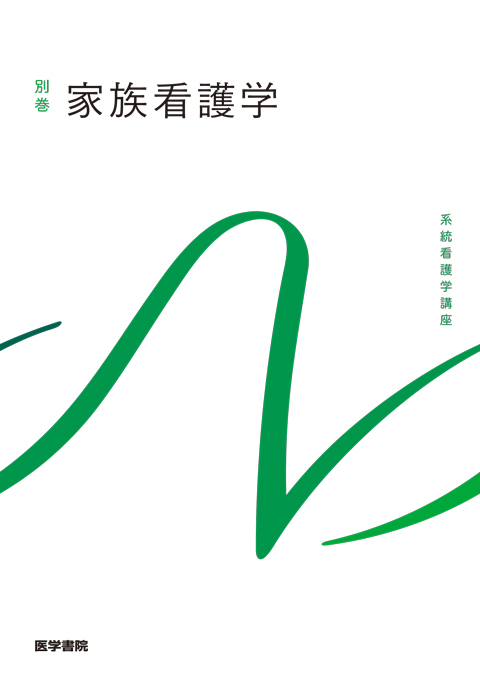家族看護の実践知
対談・座談会 藤井淳子,櫻井大輔,藤原真弓
2024.12.10 医学界新聞:第3568号より

第5次となる看護基礎教育のカリキュラム改正では,対象や療養の場の多様化に対応できるよう,「在宅看護論」が「地域・在宅看護論」に名称変更され,内容の充実が図られた。これを受けて家族看護に重きを置く養成校が増加している。しかし実際には,家族看護を系統的に学習した経験を持たない教員が講義を担当することもあるなど,その教授方法に戸惑う教員も少なくない。他方,コロナ禍以降,臨床現場においても家族看護を重要視する動きがあり,多様化する家族の在り方に対して,いかに支援していくかが模索されている。「これから家族看護を意識するシチュエーションはますます増加していくはず」と語る藤井氏を司会に,3人の家族支援専門看護師が臨床・教育への家族看護の実装に必要なエッセンスを共有した。
藤井 本日の収録に参加している3人は,全員が家族支援専門看護師の資格を有しています。それぞれ背景は異なるものの,臨床現場で患者の家族とかかわるうちにその存在の重要性に気付き,現在は管理者・臨床家・教員の立場から家族看護の普及・実践に携わっています。今回は,そんな皆さまの経験を共有していただきながら,臨床・教育への家族看護のさらなる実装に向けた新たな視点を紹介できればと考えています。
家族とのかかわりを希薄にしたコロナ禍
藤井 ここ数年のコロナ禍は,人々の家族観に影響を与えました。家族看護の実践にも多大な影響を及ぼしたと考えていますが,コロナ禍ではどのような問題が起こっていたのでしょう。
藤原 感染対策を目的に多くの病院で実施された面会制限により,家族に対応する機会が減ったことで,かかわり方がわからないと話す看護師が増えました。特に看護実習に与えた影響は大きく,実習期間中に家族とかかわることなく看護師になった方もいらっしゃいます。また,コロナ禍以前は看護師も同席して実施されていた病状説明も,医師が家族に直接電話して終わらせてしまうケースが増加しました。そのため電話上で交わされたやり取りがカルテに詳しく記載されない限り,どのような説明が家族になされたのか,家族はどのような反応をしたのかが読み取れなくなってしまい,現場に混乱をもたらしました。
藤井 当院も同じ状況で,特に病院と家族の間で認識のギャップが広がったように感じています。入退院支援で家族とかかわった際に「こんな状態で退院させるんですか!?」と言われて困ったなど,スタッフからの相談が多々ありました。
藤原 せん妄が起こっていることや入院によって体力が低下している状況を電話越しに伝えていても家族はいまいちピンと来ず,久しぶりの対面時に驚いてしまい,その感情が時に怒りへと変わることもありましたね。
櫻井 一方で,患者さんの状態に違和感を覚えていたとしても,「そういうものなのか」と家族側が暗に受け入れ,医療者側に感情を表出していない可能性もあったはずです。むしろそうしたケースが個人的には少なくないと感じており,看護師が意識的に目を向けなければ「何の問題もなかったね」とそのまま流れてしまいます。
藤井 そうした可能性も確かに拭い切れませんね。コロナ禍を経て私が抱いている違和感は,患者さんよりも家族の反応を気にして萎縮してしまっているのではないかということです。「この家族を面会させると,制限をかけている別の家族に何か言われてしまうかもしれない」「家族にこう言われたらどうしよう」と防御的に考える方が増えてきた印象です。この考えへの変化は,提供するケアの公平性を担保するという意味では必要な変化とはとらえています。しかし以前はもっと柔軟に対応していたように思うのです。病院の方針も多分に影響する部分ですが,提供できる看護が窮屈になっています。
櫻井 家族に対する恐れから看護師が萎縮してしまっているとの指摘には,少し悲しさを覚えますね。
藤原 当院では,患者さんの入院中のイメージが湧かず転院や退院に難色を示す家族には,リモート面会を繰り返し行いました。その上で,どうしても必要な場合は感染に配慮しながら短時間の面会の機会を設けることもありました。機会を設けることで,たとえ面会時間がごくわずかであったとしても,家族の態度が和らいでいく雰囲気を感じました。
藤井 それは素晴らしい取り組みですね。うまく家族とコミュニケーションを図り,意思決定につなげられた実例と言えるでしょう。けれども柔軟に対応できる施設はそう多くないはずです。この点は,施設全体で意識を変えていくべき部分なのかもしれません。
カリキュラム改正で看護基礎教育にも家族看護の波が
藤井 最近は「家族看護学を教えてもらえませんか」とのリクエストを養成校からよく受けるようになりました。これは一つの良い流れだととらえています。
櫻井 第5次カリキュラム改正によってこれまで「在宅看護論」とされていた枠組みが「地域・在宅看護論」に変化したことで,より地域を見る目が意識され,家族看護の視点を取り入れようと考える養成校が増えているのだと思われます。看護基礎教育の段階から,家族看護を必要と認識していることの表れと言えます。
藤井 それはうれしいですね。
櫻井 ただ,養成校によって家族看護の内容の取り入れ方はさまざまです。地域・在宅看護論の中の一部を家族看護に特化した内容にしたり,地域・在宅看護論の講義全てに家族看護の色を強めに入れていくようにしたりなどのバリエーションがあります。家族看護学として系統立てて教えている養成校の割合は,まだそこまで高くないと思われます。
藤原 先日開催された日本家族看護学会学術集会においても,「家族看護の教え方がわからない」「アセスメントモデルをどう教えていいかわからない」と困っている先生方が多くいらっしゃいました。櫻井さんは教授方法に関する交流集会を企画されていましたね。
櫻井 ええ。参加者には同じような悩みを抱えた方が多かったです。その中で気になったのは,「何を教えるべきかわからない」という家族看護を系統的に学んだ方からの悩みでした。恐らく深く学んできたからこその悩みなのでしょう。
藤原 どう回答されたのですか。
櫻井 「現場に出てからでも学べるコミュニケーション法といった枝葉の知識ではなく,本質的な家族の関係性に関して,学生たちの生活体験とも紐づけながら説明をしています」と,自身の実践を交えてお伝えしました。具体的には,事例を取り上げる際に「この患者さん,誰と生活しているんだっけ?」という声掛けをすることです。この一言で,意外と家族に対して目が行くようになります。もちろん,「誰と」の部分が,血縁者であろうが...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

藤井 淳子(ふじい・あつこ)氏 東京女子医科大学病院看護部 看護副部長
1995年東京女子医大看護短大(当時)卒。同大病院ICUで勤務する中で家族看護に関心を持ち,東海大大学院健康科学研究科へ進学。2013年に修了し,翌年に家族支援専門看護師の資格を取得する。22年国際医療福祉大大学院医療経営管理分野修了。23年より現職に就き,現在は看護部全体のマネジメントと,家族看護の教育やコンサルテーション等の活動を行う。

藤原 真弓(ふじわら・まゆみ)氏 堺市立総合医療センター 患者支援センター入退院支援課
看護師免許を取得後,二次救急を担う病院へ入職し救急領域の研鑽を積む。救急の現場で出会った患者・家族に心を動かされ,家族支援の道へ。2013年大阪府立大大学院看護学研究科修了後,淀川キリスト教病院に勤務。20年より現職。家族支援専門看護師,救急看護認定看護師。家族相談士。

櫻井 大輔(さくらい・だいすけ)氏 東海大学医学部看護学科 講師
2000年国際医療福祉大を卒業後,神奈川県立足柄上病院に入職。手術室・内科病棟で勤務する中で家族とのかかわりを意識するようになり,東海大大学院健康科学研究科に進学。11年に家族支援専門看護師の資格を取得する。その後は資格を生かし同院にて教育専従看護師,救急外来看護師長を兼務しながら,組織横断的な活動を展開。18年より東海大で看護基礎教育と家族支援専門看護師の養成に携わる。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。