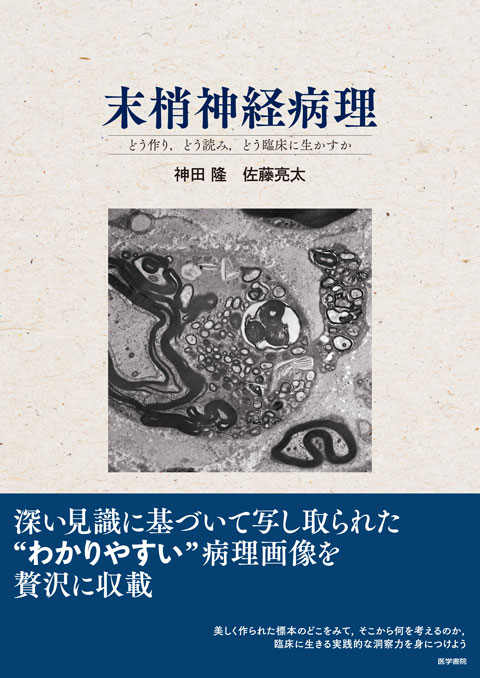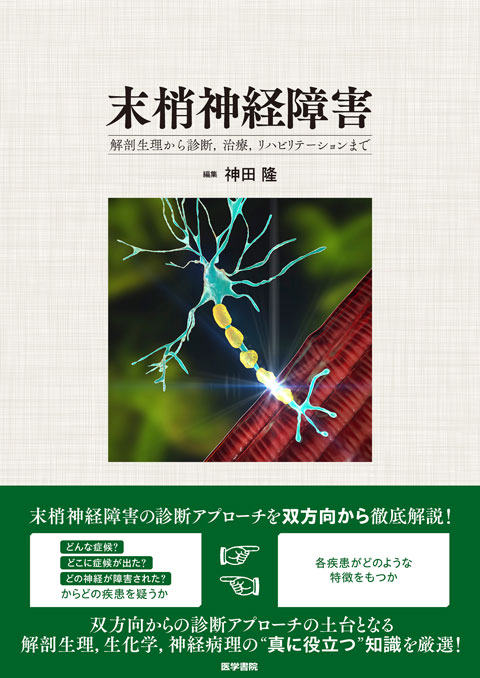神経病理の未来はどこへ向かうのか?
脳神経内科医と病理医の有機的なコラボレーションをめざして
対談・座談会 神田隆,西村広健
2024.10.08 医学界新聞(通常号):第3566号より

「カタチが美しいこと,それが形態学の何よりの魅力です」。そう語るのは末梢神経の専門家として蓄積してきた自身の知見を『末梢神経病理――どう作り,どう読み,どう臨床に生かすか』(医学書院)にまとめた脳神経内科医の神田隆氏です。
遺伝子や画像を用いた検査技術が発展する中で,病理形態像から病態を読み解く神経病理学は今後どのような価値を生み出していくのか。病理医でありながら,末梢神経・筋生検を含めた神経病理学的検索に注力する西村広健氏との対談を通じ,この分野の未来について考えました。
西村 『末梢神経病理――どう作り,どう読み,どう臨床に生かすか』のご出版おめでとうございます。本書を読みながら,神田先生が主催されていた末梢神経・筋病理の勉強会に初めて参加した時のことを思い出しました。あれから15年以上がたちましたが,あの時に末梢神経生検の病理学の奥深さに触れられたことが,その後もこの分野で働く大きなきっかけになったと感じています。
神田 ありがとうございます。私の専門は臨床神経学ですが,神経病理学の領域とはかれこれ40年以上の付き合いになりますから,本書の出版は私にとっても感慨深いものがあります。神経病理学について脳神経内科医と病理医がそれぞれの目線で意見を交わす機会は普段なかなかありませんので,西村先生とお話しできることを楽しみにしていました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
神経病理に携わる医師の減少背景にある事情とは
神田 私が医師になったばかりの1980年代と比べると,神経病理に携わる臨床家は近年非常に少なくなっているように感じます。いわゆる一般病理医の先生方は,神経病理学の存在をどのようにとらえているのでしょうか。
西村 病理医の仕事の中で比重が大きいのはがんの診断,すなわち組織や細胞が悪性かどうかを診断することです。病院病理部/病理診断科で働く病理医が,末梢神経・筋疾患を含めた非腫瘍性神経系疾患の病理診断を日常業務の中で求められることはほとんどありません。病理医からすると,神経病理学はとっつきにくい印象を持たれていると感じます。
神田 悪性診断に重きが置かれるのは社会的なニーズによるものですから仕方ないと言えます。けれども経験する機会がそもそも少ないとの表現は気になりました。
西村 近年の医師国家試験では神経疾患について問われることが多いので,若い世代は医学部卒業時点・初期研修修了時にはかなり詳しい知識・経験を習得しているものの,せっかく病理医になってもそれを実際に活用する機会がなかなかなく,残念です。神経病理学におけるこうした事情は歴史的なものがあり,日本の神経病理学は神田先生のように臨床で活躍する脳神経内科医がこれまでけん引してきた分野でもあるわけですが,脳神経内科医側の人材も今は減ってきていますよね。
神田 ええ。医療の発展とともに神経領域の守備範囲が遺伝学や生化学,生理学などの領域に広がるにつれ,神経病理を専門とする脳神経内科医の母数は減りました。こうした流れは神経領域全体で考えれば新たな治療法や技術の開発につながっているので悪くないことなのですが,神経病理学分野の研究のアクティビティが段々と落ちてきたことは否めません。
神経病理学に欠かせない「きれいな標本」を作り,診る力
西村 以前は多くの病院・大学で末梢神経・筋肉の標本が作製されていました。しかし,今は標本作製ができる施設自体が少なくなっています。採取された末梢神経や筋肉の検体は,限られた一部の施設に送られ,標本の作製・検査をしてもらうことが大半です。
神田 効率化の面では特定の機関に集中させることは歓迎すべきことですし,研究促進に向けた症例蓄積の面でも合理的です。ただし,神経病理のように形態学的な考察が重要となる分野は,「きれいな標本を作る」という技術のもとに成り立っています。医師が自分の手で標本を作り,それを見て診断するという経験を何度も積まないと,病理医としてだけでなく神経の臨床家としての能力の向上はありません。将来的な担い手が少なくなることで,これまで培われてきた技術の学習・継承の場が失われていくことを憂慮しています。
西村 神経病理学,特に末梢神経・筋生検分野の持つ課題として,技術の標準化が十分なされていない点も重要だと感じています。通常病理診断の現場では,標準化や精度管理に力を入れており,例えば遺伝子診断やがん治療におけるコンパニオン診断で使用されるパラフィン切片の作製は,どこで誰がやっても同じ質が保たれるような体制の整備が進められてきました。しかし神経・筋生検に関しては検体の固定や染色を含めた標本作製方法は施設ごとにバラバラであり,また技術の継承は一子相伝のスタイルが続いているのが現状です。
神田 標準化がなされない原因...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

神田 隆(かんだ・たかし)氏 脳神経筋センターよしみず病院 院長
1981年東京医歯大卒。米南カリフォルニア大神経学教室リサーチフェロー,米バージニア医大生化学・分子生物学教室研究員,東京医歯大神経内科講師,助教授などを経て,2004年山口大医学部神経内科教授。23年より現職。神経内科学を専門とし糖尿病性ニューロパチーの病理学で医学博士の学位を取得するなど,末梢神経の病理に40年以上携わる。近著に『末梢神経障害――解剖生理から診断,治療,リハビリテーションまで』(医学書院),『脳神経内科 改訂5版』(中外医学社),『末梢神経病理――どう作り,どう読み,どう臨床に生かすか』(医学書院)など。

西村 広健(にしむら・ひろたけ)氏 川崎医科大学附属病院病院病理部 医長
2001年川崎医大卒。03年年から同大附属病院病理部シニアレジデント・病理学教室臨床助教を経て,13年より現職および川崎医科大学病理学講師。神経病理学に興味を持ち,末梢神経・筋生検の検索とともに,神経変性疾患などの剖検脳検索を含めた非腫瘍性神経疾患の病理診断に力を入れる。病理診断業務とともに,川崎医大の医師卒後臨床研修部門の運営にも携わる。日本病理学会認定病理専門医,日本神経病理学会指導医,川崎医大附属病院良医育成支援センター長補佐・卒後医師臨床研修プログラム副責任者。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。