私を変えた,患者さんの“あのひと言”
寄稿 吉岡成人,小倉加恵子,金子祐子,余宮きのみ,多胡雅毅,能瀬さやか
2024.09.10 医学界新聞(通常号):第3565号より
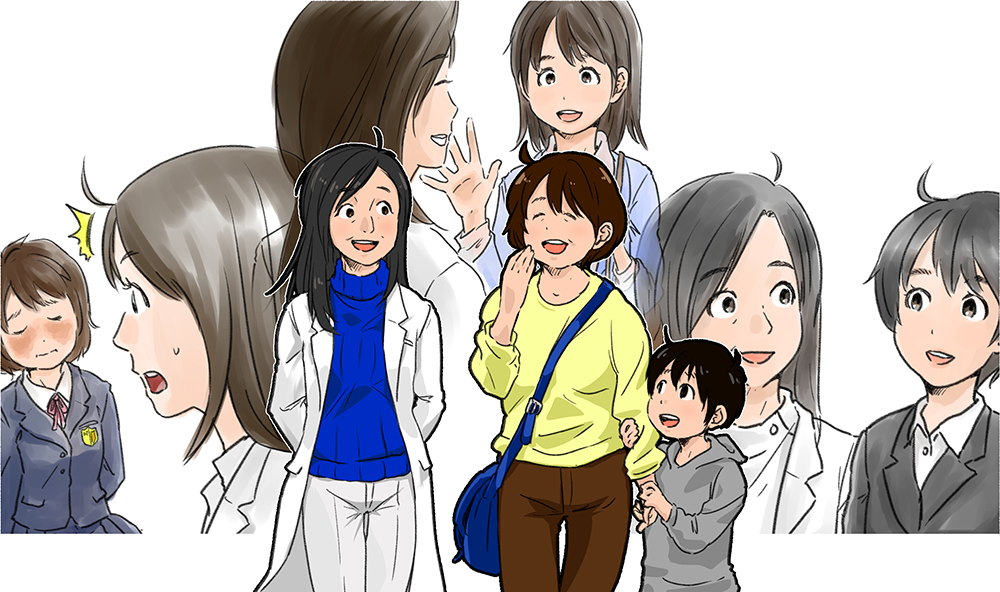
日々の臨床現場で交わす会話が患者さんにとって励みや救いとなり,生きる力につながることは少なくありません。同じように,患者さんの何気ないひと言が,時として医療者の心やその後の道に大きく影響を与えることもあるでしょう。
本企画では,これまで多くの患者さんたちと言葉を交わしてきた先生方に「今も心に残り,自分の医師人生に影響を及ぼしている患者さんの“ひと言”」にまつわるエピソードをお寄せいただきました。

「先生,私悔しい……」
吉岡 成人
NTT東日本札幌病院 院長
ナースステーションで診療記録を記載しているときのことです。病棟の受付を担当しているスタッフから受話器を受け取ると,電話交換手が「患者さんからのお電話です。おつなぎします」と伝えました。20年以上も前のことです。当時は不審電話もあまりなく,患者さんから主治医に直接連絡があることは珍しいことではなかったように記憶しています。
20歳代前半の女性で1型糖尿病の患者さんからの電話でした。
「吉岡です」と答えると,「先生,私悔しい……。忙しいときに電話をしてごめんなさい。でも,先生に聞いてほしいの……」とのことでした。わずかな沈黙の後で,市役所の採用試験の面接の席で人事担当者から「あんたは糖尿病でインスリンを注射しているんだよね。糖尿病は自己管理能力のない人がなる生活習慣病で,しかもインスリンは低血糖を引き起こす危ない薬だ。それを1日に4回も注射しているなんて危険極まりない。幸いあんたは見てくれもいいし,仕事なんて考えないで,同じ病気の男を見つけて,早く結婚でもしたほうが良いんじゃないか」と言われ,とても悔しかったと涙ながらに伝えてくれました。話を聞いていて,途中から吐き気を催すほどの嫌悪感を覚え,激しい怒りが湧きました。
1型糖尿病の発症に生活習慣は関連がありませんし,内因性インスリン分泌能が枯渇した状態で,インスリンの頻回注射を行うことは生命の維持に必須な治療です。かわいい顔をしているから,同じ病気の男と結婚して家事をしていろというのは暴言以外の何ものでもありません。しかし,当時の私には「つらかったね……。誤解だよね。あまりにもひどい……」と繰り返すことしかできませんでした。
患者さんを力づけることもできなかった私は,ある新聞社の編集局宛てに,1型糖尿病の患者さんに対しての社会におけるいわれのない差別の現状について知ってほしいという内容の手紙を書きました。すると数日後に新聞社から連絡があり,500字程度の短い文章にまとめてもらえれば,読者からの「声」という欄で掲載したいとのことでした。やり場のない憤りを原稿用紙1枚程度にまとめることは難しかったのですが,感情を抑えたコンパクトな原稿を送付しました。翌々日には新聞社から電話があり,担当者が若干の手を加えた形で掲載されました。
私が医師となり内分泌代謝分野の専門医となった1990年代はインスリン製剤も注入デバイスも不十分なもので,血糖の管理状況を良好に保つことは極めて困難でした。若い1型糖尿病の患者さんは常に低血糖,高血糖を気にかけ,1型糖尿病であることを隠さなければ就職が難しい時代でもありました。いまでも,生命保険に加入することが難しい,住宅を購入しようと思っても銀行でローンを組めないことがあるなどの現実があります。
日本糖尿病学会では2020年頃から糖尿病を持つ人たちへのスティグマが大きな社会問題であるとして,2024年の年次学術集会においては患者さんたちと共に考えるセッションが設けられました。しかし現実の社会には,いくつもの解決すべき大きな問題が横たわっています。
40年を超える臨床医としての毎日の中で,「先生,私悔しい……」というひと言は忘れられない言葉です。“Language matters, language reflects attitude, language creates reality (言葉は重要であり,言葉は態度を反映し,言葉は現実を創り出す)”などとも言われますが,患者さんとの言葉のやりとりを大切にする感性は,臨床に携わる医師にとっては欠くべからざるものではないかと思います。

「先生,大好き」
小倉 加恵子
鳥取県福祉保健部・子ども家庭部 /
中部総合事務所倉吉保健所 / 鳥取県立鳥取療育園
小児医療に携わる者であれば,幼い患者からこうした言葉をかけられることは少なくないだろう。たくさんの語彙を持たない時期である。「大好き」にもいろいろな意味が内包されている。また,彼・彼女らの評価ポイントは,提供した医療に関係しないことが多い。が,どんな意味,評価にせよ,一医療者としてその言葉をうれしく思い,仕事のやりがいをも感じるものである。
ありがたいことに私も,こうした声をかけてくれた患者さんが幾人かいる。その中に,胸の深くに刺さった「先生,大好き」がある。
私は卒業大学にある小児神経の専門診療科に入局した。研修は小児神経学の臨床から始まり,半年後からは小児科ローテーターとして身体疾患の臨床を学び始めた。大学附属病院のため,腎臓グループ,血液・がんグループ,肝臓グループなど,専門チームを回りながら研修を積む。
研修医がベッドサイドで提供できる医療は限られている。疾病や治療に関する勉強はもちろんしたが,目の前にいる「この子」に何かできることはないだろうかと,はやる気持ちが抑えられず,時間を作ってはベッドサイドに赴いた。その中に,固形腫瘍に罹患したAちゃんがいた。
Aちゃんは,よくしゃべり,よく笑う明るく人懐っこい就学前の子であった。いつものように他愛のない話をしていた時,Aちゃんはベッドの上から外を見て,「ここのお空は三角なんだよ」と教えてくれるように言った。田舎の空は遮るものがないのだが,例外的に高い建物である病院,その外壁が空の縁を切り取っていた。何か月も,遊びたい盛りの子が暗い病室から角ばった空をただ見上げていたのか……。臨床現場に出たばかりの研修医にとって,ある種の心的衝撃であった。それからは,以前にも増して病棟に足を運ぶようになった。
私がAちゃんを担当したのは,一連の治療の終わり近くであったため,その後まもなく寛解,退院となった。軽やかな夏服を着て,はつらつとした声でお礼を言い,明るい日差しの中に駆け出した様子が印象に残っている。
翌年,私は関連病院で研修することになり,大学附属病院から離れた。ある日,かつての指導医から連絡があった。Aちゃんが腫瘍を再発し,再入院しているが回復が見込めない状態であると。すぐに会いに行かねばという衝動が湧き上がった。一方で,会っても何ができるわけでもなく,どのような立場で顔を合わせばよいのかわからない不安や,何様のつもりで会いに行くのか?という理屈っぽい自分がブレーキをかけ,病室を訪問できたのは連絡から数日たった週末だった。
案内された病室はクリーンルーム仕様の個室で,ビニールカーテンが二重にかけられていた。その向こうに,Aちゃんが見えた。たくさんの管がつながり,ガーゼや包帯が顔や体を覆っている。私に気づいたAちゃんは,出血斑がいくつもある青白くか細い手をこちらに伸ばした。そして私にかけた言葉が「先生,大好き」であった。
あれから年を経て立場も変わり,いろいろな役職もいただくようになった。ややもすると惰性や慢心が顔を出してくる。そんな時,胸に刺さったあの言葉が,私を立ち止まらせ,自省させる。これまで多くの患者さん・ご家族から,得難い多くのことを学び,経験させていただいた。与えられるばかりになっていないか,何...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
