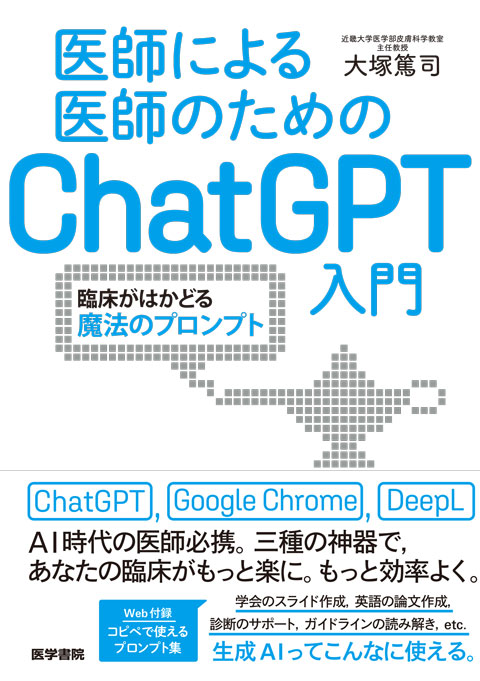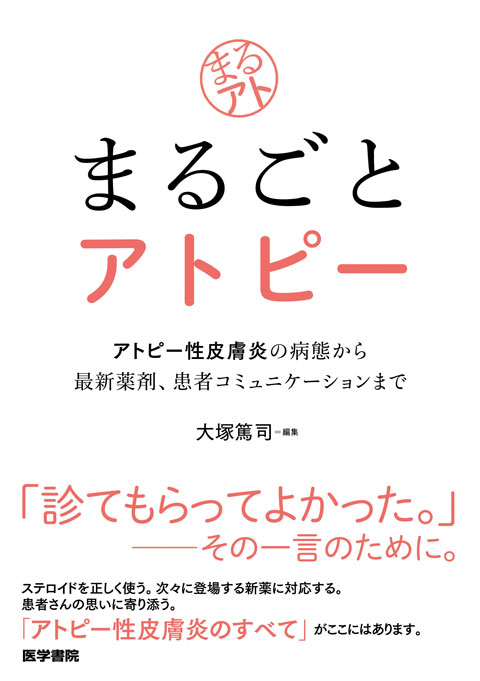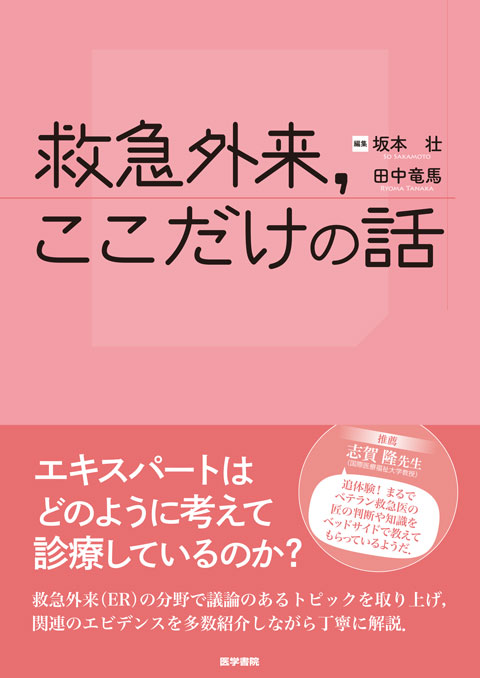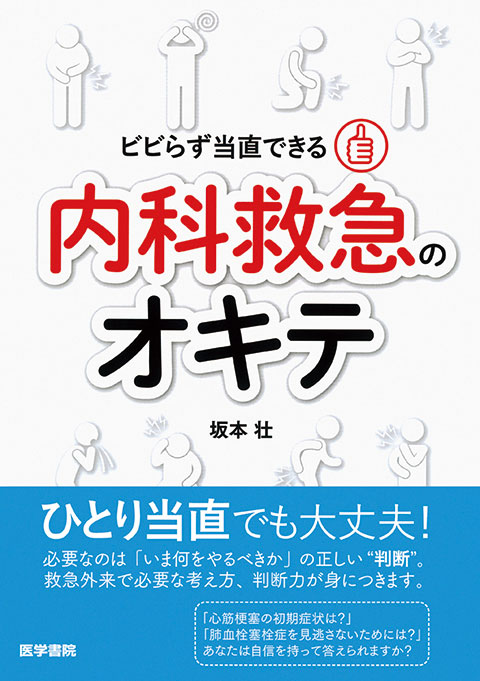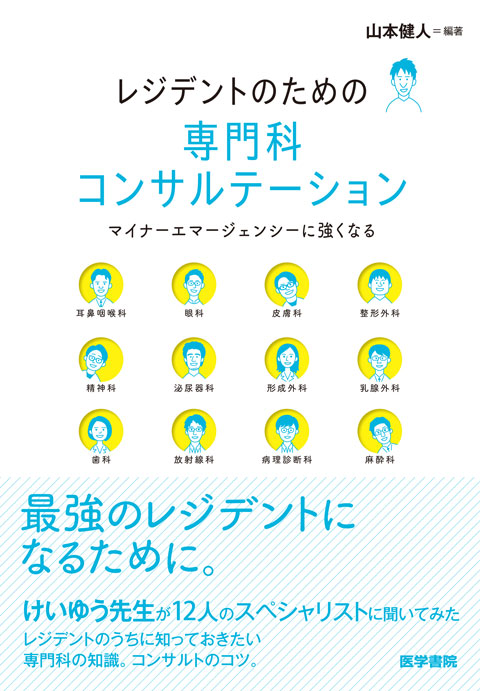手技ってどう学ぶ? どう教える?
対談・座談会 大塚篤司,坂本壮,山本健人
2024.07.09 医学界新聞(通常号):第3563号より

「いまだに苦手に感じる手技があります」。こう語るのは,不安を抱きながらも上級医の見よう見まねで手技を覚えていくしかなかった研修医時代の体験に基づき,書籍『皮膚科手技大全』(医学書院)を編集した大塚篤司氏。同書はベテラン皮膚科医が編み出した正しい「型」を紹介することで,手技習得に励む若手医師の理解度を深められるよう工夫されています。今回は同書の発刊を記念し,手技を行う機会の多い救急領域,外科領域から,それぞれ坂本壮氏,山本健人氏に参画していただき,手技教育にまつわるあれこれをお話ししてもらいました。
大塚 私が研修医の頃は,皮膚科手技に関して体系的な勉強をする機会がなく,上級医の行う手技を観察し,見よう見まねで実践していました。それほど侵襲性が高くないという皮膚科の手技の特性はあるものの,上級医の実践する手法が本当に正しいのだろうかとの不安が拭えず,皮膚科手技に特化した成書もなかったため,何を参考に勉強すべきかも当時はわかりませんでした。『皮膚科手技大全』(医学書院)をこのたび出版したのも,そうした若手時代の体験に基づいています。
一期一会の技術を盗んだ時代から,何度も動画を見返して学ぶ時代に
大塚 皮膚科で行われる主な手技には皮弁や植皮,レーザー治療などがありますが,救急科はどのような手技が代表的なのでしょう。
坂本 研修医が押さえなければならない主な手技と言うと,まずは気管挿管が挙げられます。あとは胸水や腹水に対する穿刺や中心静脈(CV)の確保といった挿入手技ですね。これらは最終的にどの診療科に進んだとしても,医師として最低限身につけておくべき手技の代表例とも言えます。
大塚 最低限マスターしておかなければならない手技の数は,従来と比較して増えているのでしょうか。というのも,医学の進歩に伴って覚えなければならない知識は年々増加しています。
坂本 数自体に変化はありません。しかし実施するためのハードルが高くなっている印象があります。
山本 同感です。昔はトライ・アンド・エラーで実践していく空気感がありましたが,そのハードルが年々高くなっています。この傾向は安全面を考慮してのものでしょう。
坂本 CVカテーテル挿入を例に挙げると,施設による違いはありますが,シミュレーターを用いた試験を行って合格した人が行うこと,まずは首から挿入すること,挿入時にはエコーを用いることなど,複数の条件が課されています。
山本 手技を学ぶ際の近年の外科領域の大きな変化を付け加えるとすれば,多くの人が動画で手技を学ぶようになったことが挙げられます。手術中に一期一会の技術を盗んだ時代から,何度も動画で手技を見返せる時代に変わってきました。動画コンテンツも増え,当然ながらその映像も高画質になり,最近ではVRで手技を学ぶ人も登場しています。以前に比べて手技が上達しやすい環境になっていることは間違いないでしょう。
若手が手技に集中できる環境を上級医が作り出す
大塚 全国各地で研修医を対象に勉強会を開催されている坂本先生は,どのようなポイントを意識して手技を教えているのでしょうか。
坂本 目の前で起こる全ての事案をいかに自分ごととしてとらえてもらうかです。特に救急の場合だと突発的に対応しなければならない事案が多く,いざという時に動ける医師に育ってもらいたいためです。
外科の場合は予定手術が主であることが多いために,事前準備は念入りに行われていると想像しますが,手技を教えるに当たって救急科との違いはあるのでしょうか。
山本 手術中は患者さんが全身麻酔下にあることが多く,患者さんの覚醒下で手技を教えなければならない救急科をはじめとした他の診療科とは異なる部分と言えるでしょう。限られた手術時間の中ではありますが,「上級医が手技をレクチャー⇒若手医師が実践⇒フィードバック」というフローを繰り返し行いやすいです。
坂本 なるほど。手技を教える際のリカバリーについてはどうでしょうか。経験の浅い若手医師が行う基本的な手技は,よほどのことがない限り患者さんが一大事に陥ることはありません。実施に当たっては安全面が配慮され,なおかつハイリスク症例は上級医が行うためです。リカバリーをどこまで事前に考慮していますか。
山本 実施に伴って発生するエラーには,フルリカバリーできるもの,リカバリーできるけれども患者さんに何らかのマイナスが発生するもの,リカバリーできないものの3段階があると考えていますが,フルリカバリーできるエラーに関しては,許容範囲を広げて腰を据えて教育しています。言い換えれば,上級医がリカバリーできる範囲にエラーをとどめる必要があるということです。何かエラーが起きた場合にはすぐにサポートに入れるよう,常に先読みしながら手術に参加しています。
坂本 実施前の準備は大事なポイントですよね。例えば外傷患者の搬送連絡を受けた時に,気管挿管といった処置が必要だと予め想定ができていれば,手技に必要な物品を揃えるよう指示しています。その場であれもこれもと追加で対応していく足し算の対応よりは,不要なものを取り除いていく引き算で考えるほうが迅速かつ柔軟に対応できるからです。
大塚 研修医の頃からそうした意識を持たれていたのですか。
坂本 吸引機器の準備をしていなかったり,気管挿管を行いやすくするために頭の位置を調整する枕の準備を怠っていたりなど,至らない部分も多々ありました。こうした細かな部分を上級医や看護師が知らず知らずのうちにフォローしてくれていたのだなと,年次を重ねてから気が付きましたね。若手時代に手技だけに集中できていたのはそのおかげでしょう。今では,その役回りを私がするようになったので感慨深いです。
手技に自信がないなら積極的に具体的な質問を
大塚 坂本先生,山本先生のような指導医からの手厚いサポートがあると手技を勉強する際に安心感を得られるものの,「本当に自分はできるようになるのか」「独り立ちできるのか」との不安も同時によぎります。先生方も若手の頃は不安を抱いていたのでしょうか。
坂本 研修医の頃は自信がなく怖かったです。不安が80,自信が20ぐらいの割合でしょうか。けれど,どんな手技でも一例目を経験できると達成感を味わえます。「CVをやった」「Aラインを確保できた」「挿管した」。そうした積み重ねが自信につながっていきました。自信がついたと口にできるようになったのは,状況に応じて幾通りもの対応が提案できるようになってからです。
大塚 先ほどの事前準備の話にもつながってきますね。
坂本 その通りです。ですが,気管挿管や腰椎穿刺といった基本的な手技を一発で決められない時が今でもあります。うまくいかなかった際の対処法はいくつか持ち合わせているものの,それらを実践しても思うようにいかない時は,潔く手を変えるようにしています。どれだけ研鑽を積んでもうまくいかない時があるというのは身をもって伝えていきたいですし,最後の砦のように扱われてしまうと私自身も少しつらい部分がありますからね。
山本 私も不安が多いほうで,独り立ちできる日が来るのだろうかと,研修医の頃はいつも考えていました。大塚先生はどうでしたか。
大塚 いまだに苦手に感じる手技があります。その一つが直接検鏡という顕微鏡で病原体を確認する手技です。この手技で困るのは,病原体が見つからなかった時。「おかしいな……」と思いながら顕微鏡を何度のぞいても見つからず,検体の採取が不適切だったのか,それともプレパラート上にたまたまいないだけなのかと,疑心暗鬼になって時間があっという間に過ぎていきます。病原体がないことを証明するのは至難の業であり,苦手意識が募っていきました。経験を積み重ねる中で,「上級医もこの辺で線引きをしているのかな」との感覚に気づいてからは苦手意識も薄まりましたが,ある程度感覚で対応しなければならない手技は勉強しにくいと言えます。何か解決策はあるでしょうか。
山本 手技に自信がない時代は,質問上手になることが上達への近道です。こんな簡単なことを聞いていいのかなと遠慮せずに,積極的に質問していくべきでしょう。その際に気を付けたいのは質問の仕方です。上級医に言語化を委ねる「どうやればいいんですか?」といった大まかな質問ではなく,「この部分がこういう理由でうまくいかないのですが,先生はどのような点を意識されていますか?」と,具体的な質問をすると良い回答が返ってきやすいです。
大塚 確かに重要なポイントですね。器用な人ほど感覚的にできてしまいがちであり,教える時に細部の説明が省略されやすいため,教わる側の先生が「ここがわからないです」「できないです」と切り出してくれたほうが,教える側もハッと気づくきっかけになります。
山本 多くの後輩に手技を教えていると,手技習得に際してのラーニングカーブが一様でないことがよくわかります。カーブが緩やかな人ほど,上級医が積極的に関与し,手技の向上に努めていく必要があるでしょう。
進む,手技教育の標準化
大塚 今話題に上がったように,手技の習得に当たっては皆が同じ部分でつまずくとは限らず,学ぶ側も教える側も個別的に対応を考えなければなりません。そうした中で,手技教育の標準化は実現し得るのでしょうか。今回,書籍を編集する時に悩んだポイントでもあります。簡単な手技でも個性があって,流派も存在するからです。皮膚科の手技の標準化はこれからですが,先生方の領域ではどうでしょう。
山本 外科領域ではずいぶん前から標準化に向けて動いてきました。特に腹腔鏡手術が全盛になってからは手技書の作成を行う施設も多くなり,学会主導で術式の標準化が進められてきました。例えば日本内視鏡外科学会が技量を認定する「技術認定制度」では,審査を受ける際に手術動画を無編集のまま提出する必要があり,合格には標準的な手技の習得が必須です。
坂本 救急領域で近年話題なのは,エコー手技の標準化です。今はポータブルエコーが当たり前で,聴診器代わりにマイエコーを持つ人も増えてきました。こちらも日本救急医学会主導によって診療指針となる『救急超音波診療ガイド』(医学書院)が発行されましたので,診療時に最低限確認すべき項目などの統一がめざされています。
大塚 そのような動きが進んでいるのですね。しかしながら,全ての手技が標準化できるわけではないとも感じています。
山本 特に私の専門とする消化器外科領域は疾患人口が多いこともあり,誰もができる手技を広く普及させることが命題になります。「この人しかできない手技」を,「誰もができる手技」に変えていくことが大切ではないかと思います。たとえ高難度の手術であっても,誰もが安全かつ確実に行える手法をめざすべきなのは同じです。
先手を打って,少ないチャンスをものにしていく
大塚 そろそろ時間が迫ってきましたので最後の話題です。指導する立場になった坂本先生,山本先生も,技術のさらなる向上に向けて日々手技を磨かれている最中かと思います。何に気を付けて研鑽に励んでいるのでしょう。若手時代とは意識が変わっていますか。
坂本 最近はレアケースへの対応を意識して日々の臨床に従事しています。具体的には,毎週のように出合うわけではない輪状甲状靭帯切開などの対応です。まだまだこれらの手技については研鑽の機会が足りていないと感じており,そうした手技を適用しなければならない患者さんが運ばれてこないことを内心祈りながら過ごしています。
大塚 先生でもそう思うんですね。
坂本 ええ。ただ,そうも言っていられないので,手技動画を見てイメージを膨らませたり,不測の事態が起こった場合の他科との連携体制を定期的に確認したりして備えています。
大塚 山本先生はどうですか。
山本 外科領域の技術の研鑽は,頂上が見えないぐらいに高い山を登り続けるようなものだと私は感じています。昨日よりも今日,今日よりも明日,さらに向上したいと思って研鑽に励んでいます。幸か不幸かコロナ禍でWebセミナーを通じてエキスパートのレクチャーを見られる機会も格段に増えたために, デバイスの使い方や手術の進め方を学びやすくなりました。また,中堅外科医になると,助手として術者にどのようなサポートをするか,といった指導者の視点を学ぶことも大切です。
大塚 ありがとうございます。それではそんなお二人から,これから手技を向上させていこうと研鑽に励む若手の先生方へアドバイスをもらえますか。
坂本 冒頭で触れたように,昔に比べて手技の実践に至るまでのハードルが高くなっています。そのため「手技にトライさせてもらうには何をすべきか」を常に考えて動く必要が出てくるでしょう。何のために手技をするのか,そしてその説明を患者にできるかは重要です。また,客観視によって気が付くこともたくさんあるので,同期が実践している姿を観察することも成長の糧になります。
その一方で,働き方改革の事情もあり,研鑽の時間を確保しにくくなっているのも現実です。限られた時間を最大限活用するべく,身の回りで入手可能な手技動画を活用して事前にイメージし準備しておくのは一手であり,実践後には必ず復習の上,フィードバックをもらうべきです。その繰り返しが,手技の向上につながります。
山本 坂本先生と同じことを考えていました。やはり近年は若手に与えられるチャンスが少なくなっています。だからこそ,少ない機会を自分のものにするための予習と復習が必要なのです。この反復の有無でその後の成長度合いが大きく異なります。もちろん,そうした営みの中でも患者さんの安全性への配慮は非常に大切です。手技にトライすると言っても,その対象にあるのは患者さんの体です。もし自分が患者さんだったらと考えながら手技に当たってほしいですし,自信がない時,不安な時は必ず上級医を呼び,指導を仰いでほしいと思います。
*
大塚 本日は救急科の立場から坂本先生,外科の立場から山本先生をお呼びして手技に関する話を伺いました。近年はAIやロボット技術の台頭も目覚ましく,今後手技に与える影響も少なくないでしょう。特に皮膚科領域においては,診断能の面では皮膚科専門医よりもAIのほうが優れているとする報告(PMID:38744955)も発表されており,皮膚科医として生き残るには手技が必要不可欠です。そうした文脈の中で,今回出版した書籍『皮膚科手技大全』が多くの方々に役立つものになればこの上ない喜びです。手技動画も収載されていますので,視覚的にも勉強になると思います。ぜひ活用してみてください。
(了)

大塚 篤司(おおつか・あつし)氏 近畿大学医学部 皮膚科学教室 主任教授
2003年信州大卒。スイス・チューリッヒ大病院客員研究員,京大医学部外胚葉性疾患創薬医学講座(皮膚科兼任)特定准教授を経て,21年より現職。がん・アレルギーのわかりやすい解説をモットーとし,コラムニストとしても活躍する。『まるごとアトピー』『医師による医師のためのChatGPT入門』(いずれも医学書院)など著書多数。若手時代,手技に苦手意識を持っていたことから,このたび『皮膚科手技大全』(医学書院)を上梓した。
X(旧Twitter)ID:@otsukaman

坂本 壮(さかもと・そう)氏 総合病院国保旭中央病院 救命救急科 医長
順大を2008年に卒業後,同大附属練馬病院救急・集中治療科へ入局する。救急科専門医,集中治療専門医を取得した後,在宅医療・地域医療を学ぶため西伊豆健育会病院内科へ。19年より現職。救急診療の最前線で活躍する傍ら,後進の育成にも尽力する。編著書に『救急外来,ここだけの話』『内科救急のオキテ』(いずれも医学書院)など。
X ID:@Sounet1980

山本 健人(やまもと・たけひと)氏 田附興風会医学研究所北野病院 消化器外科
2010年京大卒。後期研修までの5年間を神戸市立医療センター中央市民病院で過ごし,その後北野病院で外科医として勤務する。17年京大大学院医学研究科消化管外科学へ進学し,21年に博士号取得。同年より現職。研修医時代は内科医志望だったが,手技好きが高じて外科医の道へ。『レジデントのための専門科コンサルテーション』(医学書院)など編著書多数。
X ID:@keiyou30
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。


![皮膚科手技大全[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6817/1688/3829/05483_w480.jpg)