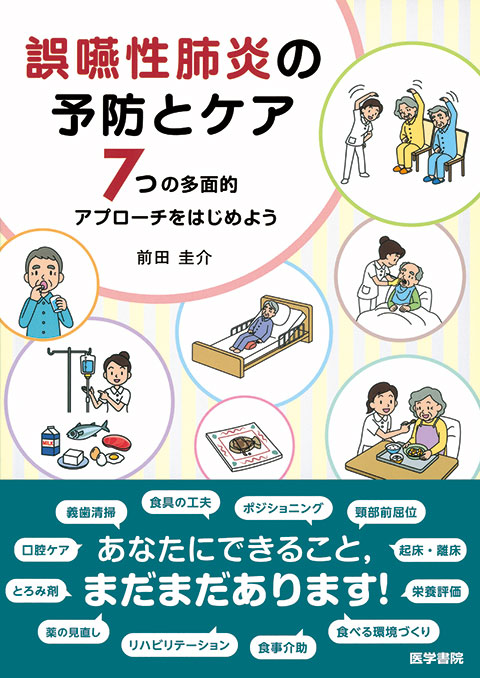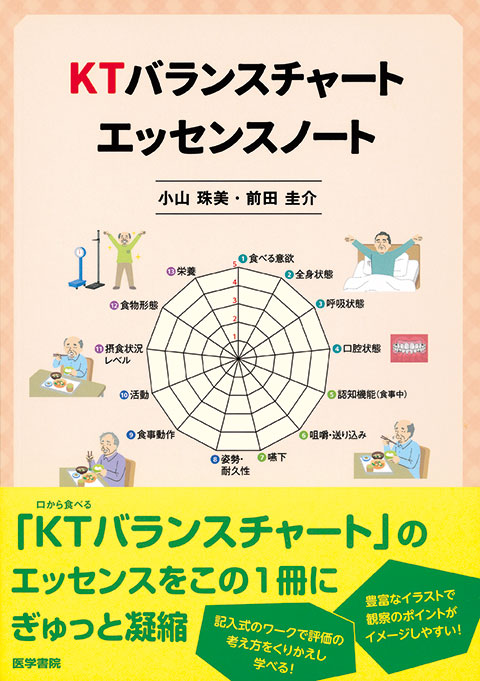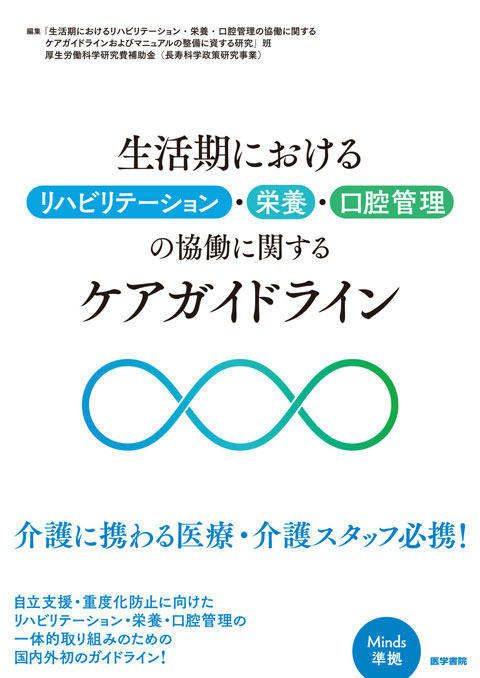災害時の「食べる」支援を考える
対談・座談会 前田圭介,坪山(笠岡)宜代,中久木康一
2024.05.14 医学界新聞(通常号):第3561号より

「災害時には,日々の暮らしの中で意識されることなく行われている『食べる』という行為が突然途絶えてしまうことによって,栄養上の問題を抱えていなかった高齢者に問題が生じる可能性が高くなる」と,災害時支援に注力する老年科医・前田氏は語ります。続発症としての肺炎等を防ぐには,「食べる」支援を通した包括的で多面的なケアが必要です。
本紙では,前田氏と同様にそれぞれの専門性から災害時支援に携わる管理栄養士の坪山氏,歯科医師の中久木氏を加えた3氏による座談会を企画。災害時における「食べる」支援とはどういうことなのかを確認するとともに,課題や展望も含めて幅広く議論してもらいました。
前田 私は老年科医で,対象者の生活全体を見ることに注力するという意味で臓器別の診療科とはやや異なる視点で医療に携わってきました。熊本県に住んでいた2016年に熊本地震に遭い,避難所支援に携わる中で本日のテーマである災害時の「食べる支援」の重要性に気がつきました。お二人はどのような経緯で災害時支援にかかわるようになったのでしょうか。
中久木 私の場合,災害時支援にかかわり始めたのは新潟県中越地震が最初でしたが,歯科の立場からではなく避難所の保健ボランティアでした。その後,東日本大震災時に歯科の立場から支援に携わったのをきっかけに,「食べる」というカテゴリーで多職種が連携して動けるプラットフォーム作りに向け,日本災害医学会内に継続的な検討の場を設けるようになって今に至ります。
坪山 私はもともと管理栄養士の研究者として,魚介類に多く含まれるタウリンに肥満抑制効果があることを明らかにするなど,分子生物学を手法に基礎研究に携わってきました。しかし,基礎的な研究ばかりではなく,実際の人や食事にもっとかかわりたいとの思いがありました。東日本大震災時に栄養士として支援にかかわり,被災地の食事に問題意識を覚え,災害時の食と栄養に研究テーマをシフトしてきたという経緯があります。
避難所における高齢者の栄養問題
前田 まずは災害時の栄養問題がどういったものなのかについて確認できればと思います。大きな災害が起こると,その地域にいる住民のほぼ全員が避難所に身を寄せることになります。そうした住民の大半は,入院したり介護施設に入ったりしている人を除いて,基本的に栄養上の問題を抱えてはいません。ですが,そうした問題のない人たちのうち,高齢者に関しては,避難所に生活の場を移すことで栄養問題を抱えるリスクがぐんと上がると個人的に確信しています。
坪山 私もそう思います。リスク上昇の原因についてはどうお考えですか。
前田 避難所への入所が生活環境を一変させ,食行動を大きく変えるためでしょう。高齢者の場合,食行動の変化は「食べない」という方向に出ることが多いです。摂取栄養量が減るわけですね。加えて,避難所生活では動く機会が減少します。活動量が下がると栄養状態はさらに悪くなります。また,高齢者はもともとフレイル,そこまでいかなくともプレフレイル状態にある人も結構な数いますから,そうした人たちが避難所でリスクにさらされることで栄養問題が顕在化する側面もあります。
中久木 避難所生活が,栄養面に関する負の連鎖を引き起こすといったところでしょうか。
私が気になるのは,避難所では高齢者は静かに,おとなしくしがちだということ。大規模災害が起こって住民の大半が避難所に入るようなケースでは,現場は非常に混乱しています。声の大きい方がいる一方で,遠慮してしまって普段なら周囲に伝えられる困り事を抱え込んでしまう高齢者も少なくないです。
坪山 遠慮をしてしまう高齢者は本当に多いです。例えば高齢者は排尿回数が増えると言われていますから,限られた数のトイレを自分が何度も使うことや夜間に移動することで周囲に迷惑をかけていると考えてしまうなど,いろいろな意味で我慢してしまっているのだと思います。
前田 排尿回数を減らすために飲む水の量を減らしているという話は毎度耳にします。
中久木 被災時に骨折してしまい,付き添いなしではトイレに行けなくなってしまったから,1日2回の排尿で済むようにコントロールしながら水を飲んでいるという話を聞いたことがあります。
坪山 水だけでなく食事を制限する方もいます。皆さん,なるべくトイレに行かずに済むようにと工夫をするのですよね。これまでの災害でも不衛生なトイレや仮設トイレを使いたくないために,同様に飲水・食事の制限をしている避難者がいたことを論文でも報告しています1)。体重減少もみられました。
前田 そうした状況に鑑みても,避難所での栄養サポートは必須です。高齢者にケアの目が行き届かなくなると水分・栄養摂取が足りずに栄養問題が発生し,口腔衛生も悪くなります。低栄養と口腔衛生の悪化が組み合わさると,続発症として肺炎を起こし得ますし,その他感染症や血栓症も起こしやすくなるのです。栄養サポートがスタンダードなものになる必要があると強く思います。
COLUMN 災害時の避難所における食事提供
指定避難所における食事は,避難所を管理している自治体が中心となり提供されます。災害初期の食事は,避難者自らが持参した食料や自治体の備蓄で対応するため保存性の高い食品が中心です。大規模災害時には,要請を待たずにプッシュ型支援で食料が届き,その後,被災地からの要請に基づいて,プル型の食料支援が行われます。炊き出しや弁当等で栄養改善が図られ,災害救助法が適用されると1日1人当たり1230円が給与されます。この金額には燃料費や調理器具等も含まれますが,困難な場合には特別基準も適用され増額される場合もあります。支援者の食事は対象となりません。避難所等での炊き出しが長期化する場合には,できる限りメニューの多様化,適温食の提供,栄養バランスの確保等,質への配慮や管理栄養士等の専門職の活用も重要となります。
生活の一部としての「食べる」を支える
坪山 栄養サポートと言うよりも,「食べる」サポートと表現したほうが良いかもしれません。
前田 そうですね。「栄養」という語と「食事」という語では示す範囲が異なり,栄養(nutrition)への介入方法の1つとして食事(diet)があります。「栄養」と表現すると栄養士だけが処理すればいいとの勘違いをされがちなところを,「食べる」と表現することで,食べ物それ自体についてはDietitianである栄養士が関与して,食べることにまつわるその他の部分については他職種のかかわりが必要であるとのニュアンスが出るわけです。
坪山 その意味で,中久木先生が日本災害医学会内に立ち上げた「災害時『食べる』連携委員会」の存在意義は大きいです。「食べる」ことの連携を前面に打ち出してくれましたから。
中久木 食べるという行為は,多くの...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

前田 圭介(まえだ・けいすけ)氏 愛知医科大学 栄養治療支援センター 特任教授
1998年熊本大医学部卒。2005年よりへき地病院,急性期病院,介護施設,回復期リハビリテーション病院等で診療。11年玉名地域保健医療センター摂食嚥下栄養療法科NSTチェアマン。17年より現職。著書に『SMARTなプレゼンでいこう!』(医学書院)など。

坪山(笠岡) 宜代(つぼやま(かさおか)・のぶよ)氏 医薬基盤・健康・栄養研究所 国際災害栄養研究室長
1997年高知医大(当時)大学院卒。99年国立健康・栄養研究所に入所後,米ハーバード大医学部,米国立衛生研究所(NIH)へ研究留学。2018年より現職。管理栄養士。博士(医学)。監著に『災害・緊急時の食と栄養――いますぐ知りたいアクションQ&A』(医歯薬出版)など。

中久木 康一(なかくき・こういち)氏 東北大学大学院歯学研究科 特任講師
1998年東京医歯大卒。2009年同大大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野助教などを経て,24年より現職。博士(歯学)。編著に『災害歯科医学』(医歯薬出版),共著に『災害時の歯科保健医療対策――連携と標準化に向けて』(一世出版)など。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。