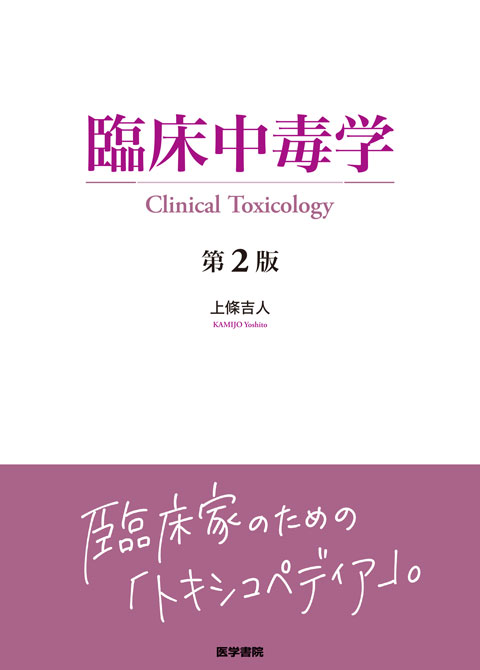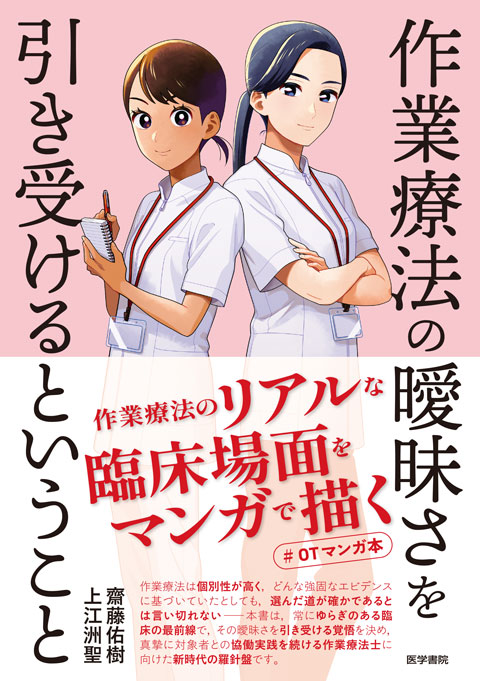MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2024.01.15 週刊医学界新聞(通常号):第3549号より
《評者》 松本 俊彦 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長
著者自身のキャリア最高到達点を軽々と更新した第2版
今日,臨床医学においてself-poisoning(毒物もしくは過剰量の医薬品を故意に摂取すること)は重要課題の1つだ。その行為は,自殺目的から行われる場合もあるし,心理的苦痛を紛らわせるため,あるいは,居場所のない者同士が孤立を解消し,仲間との絆を深めるために行われる場合もある。誤って服用するといった事故として発生する場合もあろう。いずれにしても,self-poisoningという現象は,救急医療・自殺予防・依存症医療を横断する問題であり,その治療や再発防止には救急医療と精神科医療との緊密な連携が欠かせない。
本書の著者は,当初,自身の医師としてのキャリアを精神科医から開始し,途中で救急医へと転じ,評者の認識では「臨床中毒学」という医学分野の創始者だ。実際,自殺予防と薬物乱用・依存に関する研究において,著者は文字通り「余人をもって代え難い」存在であり,評者も何度となくさまざまな研究プロジェクトで著者の助力を仰いできた。
最近十年を振り返っても,刻一刻と乱用薬物が変遷する中で,著者と協働して行った研究は少なくない。危険ドラッグやベゲタミン錠による健康被害,そして最近では市販薬過剰摂取による健康被害……。こうした研究活動の中で,私たちは,精神科医の安易な多剤大量処方への憤りや,危険な成分を含有する市販薬を販売し続ける製薬企業への疑問を共有してきたのみならず,問題解決を求めて,一緒に厚生労働省へと陳情に出向いたこともあった。もはや「同志」もしくは「戦友」と言って良いだろう。
言うまでもなく,そのような活動を展開してきた著者にとって,2009年に刊行された『臨床中毒学』はそのキャリアにおける最高到達点だった。同書は,診療の中で遭遇し得るあらゆる毒物や依存性物質を網羅し,その薬理学的特徴のみならず,典型的症例や治療法まで提示されていたのだった。どう逆立ちしても薬学の基礎研究者には書くことのできない無双の書,かつてない唯一無二の書として,刊行以来,多くの臨床医に愛されてきたのだった。
そして今回,満を持しての第2版刊行であるが,決して誇張ではなく,著者は軽々と自身の最高到達点を更新しているのだ。それもそうだろう。この14年間,わが国にはあまりにも多くの出来事があった。危険ドラッグ乱用禍と,その鎮静後に増加した急性カフェイン中毒,さらに近年では,若年女性を中心に増加する市販鎮咳薬・感冒薬の過剰摂取,そして,「大麻グミ」(大麻成分類似物質)のような新たな脱法的薬物の登場……。第2版には,これらの問題と最前線で向き合ってつかみ取った最新の知見が,ふんだんに盛り込まれている。
全ての臨床医必携の書だ。既に初版をお持ちの方は急ぎ第2版を購入し,知識のアップデートを図っていただく必要がある。まだお持ちでない臨床医の先生は,現代医学における重要課題の1つ,self-poisoningと向き合うべく,直ちに本書を入手しなければならない。
《評者》 酒向 正春 ねりま健育会病院長 / 回復期リハビリテーションセンター長
リハビリテーション医療の曖昧さと患者との距離感が学べます
表紙を見て,すぐ読みたくなった。「作業療法の曖昧さを引き受けるということ」を漫画で理解させるのか,すごく楽しみである。しかし,タイトルからして,何となく複雑そうな予感もした。
作業療法とは,人々の健康と幸福を促進するために,作業に焦点を当てた治療,指導,援助と定義されるが,作業がなんであるかがわかりにくい。私たちの臨床現場で作業療法と言えば,上肢戦略,生活戦略,精神・高次脳機能・復職戦略の3本柱の実践である。その実践には,患者との信頼関係の構築が前提となる。本書は,まさに患者との信頼関係の構築方法を丁寧に漫画と解説文で説明していた。まるで,ソーシャルワーカーの教育書ではないかと感じるほどに,患者の心と気持ちを大切にしていた。
本書の特徴は,患者のリハビリテーション入院という闘病生活の一瞬にどうかかわり,寄り添い,共に考え,人間力を回復させて,新しい人生を行くための作業の在り方に視点が置かれている。作業療法士は一人ひとりの患者,その人らしさを大切にした患者の理解者であってこそ,初めて作業療法という協働医療が...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。