自宅にいながら入院診療を受ける
急性期医療の新たな形態,Home Hospital
インタビュー 大内啓,佐々木淳
2024.01.15 週刊医学界新聞(通常号):第3549号より

救急外来を受診し,急性期治療のため入院が必要と判断された患者が「自宅に入院する」――。米国では今,急性期病棟と同等レベルの診療を在宅において提供する動きが拡大しており,home hospital(もしくはhospital at home)として注目されている。Brigham and Women's Hospitalにおいてhome hospitalプログラムの立ち上げに関わったのが,日本人医師の大内啓氏だ。普及の背景や取り組みの実際,さらには日米における将来展望について話を聞いた。
――最初にhome hospital(以下,HH)とは何か,特に在宅医療との相違について教えてください。
大内 HHとは,急性期病棟と同等レベルの診療を在宅において提供することを指します。対象となるのは,これまでならば外来や在宅では診ることができず,入院が必要とされてきたケースで,日本の在宅医療においてイメージされるものとはやや異なるかもしれません。
――対象者に制限はないのでしょうか。
大内 ICU管理が必要であったり手術の適応となったりするケースは対象外です。逆に言えば,内科系の急性期疾患および術後管理ならば選択肢となり得えます。重症度で考えると,ICU管理と従来の在宅医療の間にHHが位置付けられるでしょう。
HHの普及を後押ししたランダム化比較試験とCOVID-19
――HHが米国で生まれた背景には何があったのですか。
大内 HHの歴史は案外古く,そのコンセプトは1990年代に提唱されました1)。その理由として,特に高齢者にとっては,入院自体がせん妄や院内感染,身体機能低下のリスクとなることが挙げられます。しかも米国の場合は,病院機能の集約化が進んだ結果として入院アクセスが制限されると同時に,入院できたとしても多額の費用がかかります。こうした背景もあって,Johns Hopkins大学や退役軍人病院においてHHの試みが始まったそうです。その後に小規模な研究でHHの効果が示されました。これを受けて,米国の公的医療保険であるメディケア・メディケイドを管理するCMS(Centers for Medicare and Medicaid Services)が主導し,テストプロジェクトが全米各地で実施されるようになりました。
――大内先生ご自身もその頃からHHに携わったそうですね。
大内 ええ。研修医時代にテストプロジェクトに関わり,2014年にボストン(Brigham and Women's Hospital)に移った後,友人から共同研究に誘われたのを契機として本格的に取り組むようになりました。「HHが米国中に普及してスタンダードとなることに,自分のキャリアを賭ける」と熱心に誘われたのを覚えています。
――勝算はあったのでしょうか。
大内 本音を言えば,私は半信半疑でしたよ(笑)。というのも当時はまだ,医療者の間でHHは全く認知されていませんでしたから。保険点数が付くわけではないので,病院経営の観点からも推進する気運が高まらないのは当然ですよね。ただ患者側のニーズが大きいのは自明ですし,やってみる価値はあると思いました。
――その成果のひとつが,2020年1月のAnnals of Internal Medicine誌に掲載されたランダム化比較試験ですね。
大内 はい。2017~18年に実施した研究の結果,HHは通常の入院診療と比較して,コストを4割削減しながら,身体活動を増加させ再入院率を低下させることが示されました2)。それまでもHHの効果を示す研究はありましたが,今回はランダム化比較試験によってエビデンスを示せたのが大きなインパクトを与えました。
――その結果,HHが普及したと?
大内 いえ,残念ながらエビデンスだけでは医療政策は容易に変わりません。さらに大きな転機が訪れました。COVID-19のパンデミックです。
入院患者の急増と重症化によって,米国の病院がキャパシティを超えてしまったのです。CMSはこの緊急事態を受けて対応会議を開き,私たちのグループを含む全米各地のHH関係者を招集しました。そしてCOVID-19患者をHHで診療するという結論に達し,CMSは2020年11月25日,一定の要件を満たすことを条件として急性期の在宅診療をHHとして保険償還することを発表するに至ります。私たちの施設はこの時点で米国でCMSが認定を出した10施設のうちのひとつでした。
保険点数が付いたことによってHHは急速に普及しました。2020年時点ではHHに取り組むのは56施設に過ぎませんでしたが,現在は280施設を超えています。入院診療と同等の保険点数が算定でき,なおかつ病院を建てるような多額の設備投資が必要ないこともあって,HHを専門とする民間企業の参入も始まっています。
――パンデミックの前後に臨床研究の実施と論文発表があって,同時期に医療政策が動くというドラスティックな変化が起きたのですね。
大内 もしCOVID-19がなかったら,保険点数が付くまでの道のりはもっと長かったに違いありません。不幸中の幸いではありますが,COVID-19を契機としてHHの恩恵を受ける患者さんが増えたのも事実です。
タスクシフトとテクノロジーの活用が鍵
――では次にHHの具体的な実践について,大内先生の取り組みを例にご紹介ください。
大内 私たちのチームの場合,ボストンにある病院から半径16キロの範囲内でHHのサービスを提供しています。対象疾患としては慢性心不全や尿路感染症,肺炎,CO...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
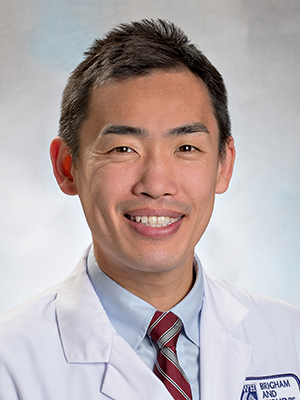
大内 啓(おおうち・けい)氏 Associate Professor of Emergency Medicine, Harvard Medical School / Brigham and Women's Hospital
12歳で渡米し,2009年Georgetown大医学部卒。Long Island Jewish Medical Centerにて内科・救急の二重専門医認定レジデンシーを2014年に修了(米国内科専門医・米国救急専門医)。その後にBrigham and Women's Hospital医療政策リサーチフェローシップ,Dana-Farber Cancer Institute精神腫瘍学/緩和医療研究フェローシップ,Harvard大学公衆衛生大学院を修了。共著に『新訂版 緊急ACP――悪い知らせの伝え方,大切なことの決め方』(医学書院)など。その他,受賞歴や論文業績は下記URL参照。
https://connects.catalyst.harvard.edu/Profiles/display/Person/125411
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
