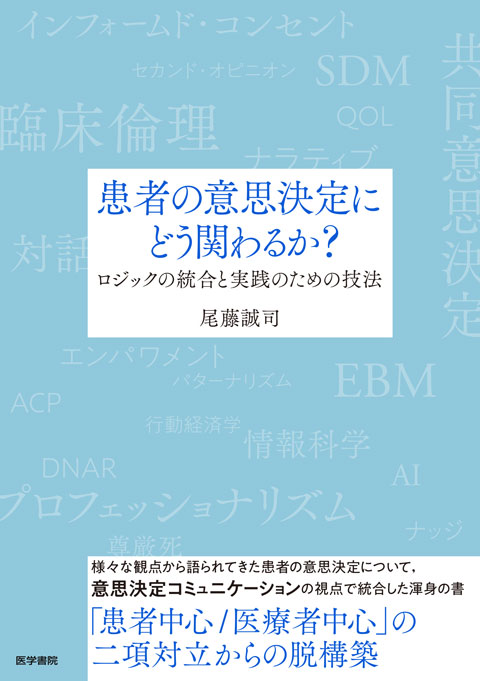- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2023年
- 医学界新聞プラス [第1回]価値観とナラティブに基づいた臨床意思決定(前編)
医学界新聞プラス
[第1回]価値観とナラティブに基づいた臨床意思決定(前編)
『患者の意思決定にどう関わるか?――ロジックの統合と実践のための技法』より
連載 尾藤誠司
2023.09.15
患者の意思決定にどう関わるか?
ロジックの統合と実践のための技法
臨床上の意思決定ジレンマに専門家として関与する仕事が持つ魅力について,体系化してまとめたい――。
書籍『患者の意思決定にどう関わるか?――ロジックの統合と実践のための技法』の「はじめに」でこう想いを記した著者の尾藤氏は,臨床倫理,EBM,プロフェッショナリズム,SDM,ナラティブなど,これまでさまざまな切り口で語られてきた意思決定の理論をもとに,「患者にとって最善の意思決定に医療者としてどう関わるか」をまとめた。「医学界新聞プラス」では本書の中から4つの項目をピックアップして,そのエッセンスを紹介していきたい。
SDMモデルにおいてなお欠けているもの
理解・認識・価値は本当にシェアできるか?
歴史的には,西洋においても専門家のパターナリズムに基づく意思決定が主流の時代がありました。しかし,意思決定スタイルや専門家の価値観によって当事者の物事が決まっていく問題が指摘されたことから,解決策としてインフォームド・コンセントのモデルが提示され,普及した経緯があります。さらにインフォームド・コンセントの限界として,意思決定の主体者を患者自身にすることでベストな選択がなされないことが少なからず起こり,そもそも意思決定はクライアントと専門家がチームとしてアプローチしていくべきであろうという揺り戻しからSDMの意思決定モデルが紹介されました。
次に,SDMのモデルは当事者である患者の意思決定スタイルとして理想的なのかという問いが立ちますが,私自身は,SDMは理想の意思決定スタイルではなく,そこにはまだ限界があると思っています。そして,その限界を超える1つの鍵となるのが,患者のナラティブに着眼した意思決定スタイルだと考えています。本項では,その主観的価値およびナラティブ的な視座を意思決定にどのように取り込むかについて解説します。
情報としての「言葉」
「共同意思決定(SDM)の構造と課題」(▶書籍『患者の意思決定にどう関わるか?――ロジックの統合と実践のための技法』p57)では,患者と医療者は大きく3つのレベルで互いに理解しあうと述べました。理解,認識,価値のそれぞれのレベルで物事のとらえ方についてシェアされ,医学的事実とともにそれらを有益な情報や根拠として尊重することによって,患者にとっての最善の利益となる意思決定につながるというのが基本的な考え方ですが,ここで着目すべきは,それらのやり取りは“言葉”で表象されるということです。言葉による表象は,意思決定の中で単なる情報や根拠として分断されると,その一部が摘み取られ,消し去られてしまう懸念があります。患者が医学的事実に対して持つ理解・認識・価値は,そこに至るまでの物語性を帯びているのですが,物語性を帯びたテキストをそのまま理解するのではなく,情報として分断してしまうことで,尊重されるべき言葉として取り扱われなくなるかもしれません。
患者の「荒唐無稽な理解」をどう理解するか?
荒唐無稽な認識の例
医療者としてヘルスケアに携わっているとしばしば経験する事例を,ここで2つ提示します。
事例1
脇の下にぐりぐりしたものが触れ,がんかもしれないと心配になって受診した患者。クリニックに行っていろいろ調べたところ,「脇の下にリンパ節がありますね。同じようなものが右の首にも2個ぐらいあります」と言われて,怖くなって大病院を受診した。その「ぐりぐり」は医学的に腫れているわけではなく,詳細な診察をするとようやく触知するくらいの結節だった。そこで医師は,「これは正常なリンパ節で,特に腫れているわけではないので検査をする必要はないでしょう」と説明したが,患者は自分ががんに侵されているという不安がとても強く,精密検査を希望した。医師はその要請を受けて全身のCTスキャンなどを撮影したが,やはり異常なリンパ節腫大はなく,血液検査などでも悪性腫瘍や結核などの深刻な病気を示唆するような結果は検出されなかった。そこで医師は,「特に問題はなく,大きな病気はありませんから安心してください」と患者に説明したが,患者は「今までこんなものに触れたことはなかったし,クリニックでは首にも脇の下にもあると言われて,まだとても不安です」と医師に伝えた。医師は,患者の状況を「CTまで撮ったけれど正常で,病気がないことは医学的にはほぼ明確なのに,まだ心配しているこの患者は理解が乏しい」と認識し,患者の「誤解」を解くためにさらに説得を続けている。
事例2
60代で気管支喘息に罹患し,その後,症状にさいなまれている患者。夜間の息切れや息苦しさなどがあり,医師はステロイドの吸入を提案したが,「ステロイドを使うと,副作用で皮膚がボロボロになったり,血管がボロボロになったりすると聞いているから,絶対にステロイドは使いたくない」と認識しており,医師からの提案を受け入れられない状況である。医学的には気管支喘息に対するステロイド吸入療法は極めて安全かつ非常に効果が高いとわかっているので,医師は「その考え方は荒唐無稽です。そんな心配はいりませんし,ほかの薬よりもステロイド吸入療法は圧倒的に効果が高いので,あなたにとっては最善ですよ」と説明し,半ば強制的にステロイド吸入薬を処方した。
次の診察のとき,患者の症状に軽快はなく,患者に確認したところ,やはり「処方されたけれども使いませんでした」とのことだった。医師が「使わないとダメじゃないですか」と言うと,「2日使ったけれど,3日目の朝に手の血管が浮き出ていて,これは絶対ステロイドのせいだと,とにかく怖くなってやめてしまった」と返答した。医学的には姿勢によって静脈の見え方が変わるのは当たり前のことなので,そのことについて医師は時間をかけて説明し,「それはステロイドの副作用ではなく人間としての生理的な作用なので,勘違いせずにしっかり使用してください」と指導し,その日の診療を終えた。結局,患者はその後の外来を中断し,その医療機関を受診することはなかった。
なぜ専門家は患者の理解を「誤解」とするのか?
この2つの事例で共通するのは,まず患者の理解を荒唐無稽だと医師は判断しているということ。そして,荒唐無稽な理解を矯正しなければいけないと考えて,医学的に正しい事実,医学的推奨を患者がきちんと受け入れ,納得してくれるように,繰り返し,丁寧に説明しているということです。そして,その努力が実を結ばず,結果として状況が破綻してしまっているところが共通点といえるでしょう。
ここでの私の問いは,「なぜ専門家は患者の理解を誤解とするのか?」というものです。医学的視座に立てば,この患者の理解は明らかに誤解です。そして,それを「誤解」としてとらえ,「正解」を患者にわかってもらうアプローチが果たしてうまくいくのか,と考えたとき,そこに新たな意思決定関与のコミュニケーションが発動するかもしれません。
当事者においてすべての事実は「主観的事実」である
患者の理解を,患者の経験に基づいて紐解くと,実はこの2つの事例における患者の認識パターン,あるいは医療に対する考え方は,患者の主観的な体験においては十分に合理的であり,誤解とはいえないのではないか,と考えられます。
事例1では,実は大切な友人が,半年ぐらい前からしこりがあることに気づいていたけれど,病院に行くほどでもないだろうと受診せずにいたところ,しこりがどんどん大きくなり,受診したときにはがんで,もう手遅れだった経験があるのかもしれません。あるいは,今までとても健康に暮らしていて体調不良や慢性疾患を患ったことのなかった人が,突然脇のしこりに気づき,クリニックの医師に「首にもある」と言われたのかもしれません。そこで人生で初めての大変なことが起こったと理解することは,十分に正当だともいえます。大病院での検査で「正常ですよ」と言われたとしても,医師から情報をもらっただけでは「自分が大変な病気に侵されているかもしれない」という不安を払拭できないことも正当だと理解できます。それに対して,医療者が誤解だとか不良な理解だと位置づけてアプローチを繰り返しても,患者にとって最善の意思決定に向かう言葉のやり取りにはなりにくいでしょう。
同様に事例2においても,もしこの患者が過去にステロイドを利用して,あるいは子どもがアトピー性皮膚炎でステロイドを使い続けた後,リカバリーが難しい状況になった体験をした人であったならば,その経験からステロイドに対する恐怖感を持ち,皮膚の問題と直結させてしまうのも十分に理解できます。そのような主観的な体験と紐づいた認識を,医師からの「それは誤解です」というコメントだけで変容させることは難しいでしょう。
(後編へつづく)
患者の意思決定にどう関わるか?――ロジックの統合と実践のための技法
さあ、意思決定のテーブルへ
「患者の意思決定」の理論と実践を1冊にまとめました
<内容紹介>意思決定の連続である医療職の仕事。臨床倫理、EBM、プロフェッショナリズム、SDM、ナラティブなど、これまで様々な切り口で示されてきた理論をもとに、「患者にとって最善の意思決定」に専門家としてどのように考え、関わっていくかをまとめた渾身の書。AIの発展、新型コロナの流行など、社会が変わっていくなかで、これからの患者-医療者関係の在り方を示す1冊。さあ、意思決定のテーブルへ。
目次はこちらから
タグキーワード
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。