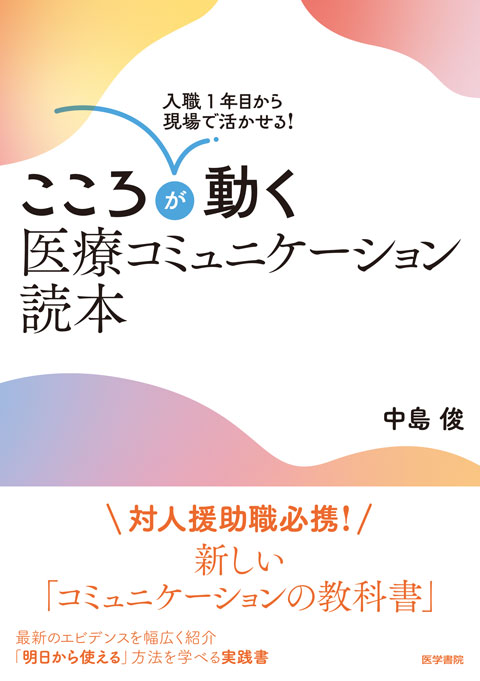MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2023.10.23 週刊医学界新聞(看護号):第3538号より
《評者》 石川 ひろの 帝京大学大学院公衆衛生学研究科/医療共通教育研究センター・教授
コミュニケーションの“型”を身につけ柔軟に運用する
この20年ほどの間に,日本の医療者教育においても,コミュニケーションは医療者が身につけるべきコンピテンシー(能力)の一つとして広く認識されるようになってきた。客観的臨床能力試験(OSCE)の導入などと相まって,コミュニケーションは教育可能,評価可能な能力としてとらえられるようになるとともに,そこでは特にスキルの教育に焦点が当てられてきた。時に「マクドナルド化」と揶揄されながらも,学生だけでなく教育に携わる医療者の意識を大きく変え,全体としての医療者のコミュニケーション能力を底上げしてきたことは間違いないだろう。一方で,卒後のコミュニケーション教育はそれほど系統立って行われてはおらず,それぞれの現場に依存しているのが現状である。本書は,学部教育の先のコミュニケーションについて,何をどう学んだらよいかの手がかりになる一冊である。
本書は,臨床心理士でもある著者による「週刊医学界新聞」の連載「こころが動く医療コミュニケーション」に大幅な加筆,書き下ろしを加えてまとめられたものである。「入職1年目から現場で活かせる」ような場面やトピックを取り上げ,基本的かつ実践的なコミュニケーションのスキルがバランスよく紹介されている。患者さんとのコミュニケーションだけでなく,医療者同士のコミュニケーションも含め,コミュニケーション研究のエビデンスに基づくスキルや対処方法が具体例とともにわかりやすくまとめられているという点で,まさに明日から使える実践書と言える。
それでいて,「こうすれば必ずうまくいく」という押しつけがましさがないのは,エビデンスに基づいた“型”を身につけることの重要性を知りつつ,その柔軟な運用こそが本質であるという著者自身の思いが根底にあるからだと思われる。結局のところ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。