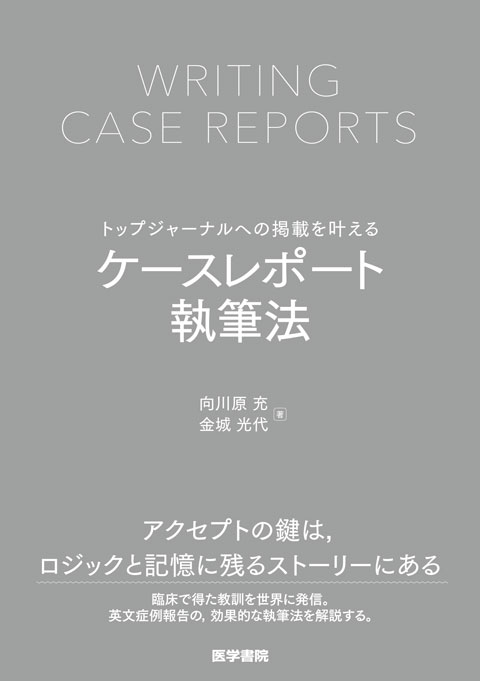忙しい研修医のためのAIツールを活用したタイパ・コスパ重視の文献検索・管理法
寄稿 中島誉也
2023.09.11 週刊医学界新聞(レジデント号):第3532号より
文献検索や論文執筆は医師にとって重要なスキルです。ただしその目的は,新しい知識を臨床に生かすため,研究成果を共有するため,自身のキャリアを築くためと,人によってさまざまでしょう。中でも研修医は,学会発表や症例報告,サマリー考察のために文献検索に取り組むことが多いはずです。しかし,忙しい日々を送る中で適切に文献検索を行うのは容易ではありません。そこで提案するのがAIを活用することです。本稿では,便利なツールの活用方法に焦点を当てたタイムパフォーマンス,コストパフォーマンスの高い文献検索・管理法を共有します。
医療界の新たな助手――AI技術の可能性を探る
近年のAI技術の発展において,特筆すべきはChatGPTの登場です。自然言語処理技術の進歩により,人間の言葉を理解し,人間らしい文章を生成できます。最近では,米国医師国家試験(USMLE)に合格できるほどの正答率を叩き出す1)など,まさに時代を動かす画期的なツールになりました。医療においては,診断や治療の支援,業務の効率化といったさまざまな応用が考えられています2)。
こうした大規模な言語モデルのAIは,論文執筆の各ステップ,つまり文献検索・管理,要約,ライティング支援などにも活用ができ,研修医の限られた時間とリソースを最大化する強力なツールとなるはずです。紙幅の関係上,文献検索・管理に関連したAIツールだけになりますが,その活用方法を以下で紹介していきます。
研修医が活用すべき文献検索・管理ツール
文献検索に当たっては,Mutually(お互いに),Exclusive(重複せず),Collectively(全体に),Exhaustive(漏れがない)というMECE(ミーシー)を意識して,モレなく,ダブりなく行うことが重要です。しかし,文献検索の方法(例えば,PubMedのMeSH用語の使い方など)に関して研修医の時代に体系立...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
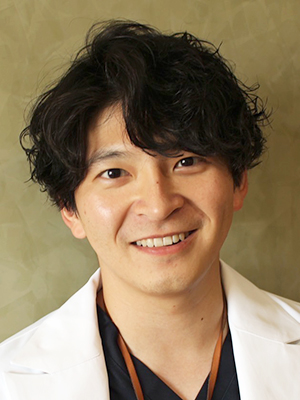
中島 誉也(なかしま・たかや)氏 長崎大学病院初期研修医/長崎大学大学院医歯薬総合研究科麻酔科学専攻
長崎大医学部医学科在籍時代から医療AIや臨床研究に興味を持ち,ベンチャー企業でのインターンや複数の臨床研究を手掛けてきた。2022年に同大を卒業。現在は卒後2年目の初期研修医として同大病院にて研修に励む傍ら,麻酔・集中治療分野の大学院で臨床研究を行う。
X(旧Twitter) ID:@naka_takaya
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。