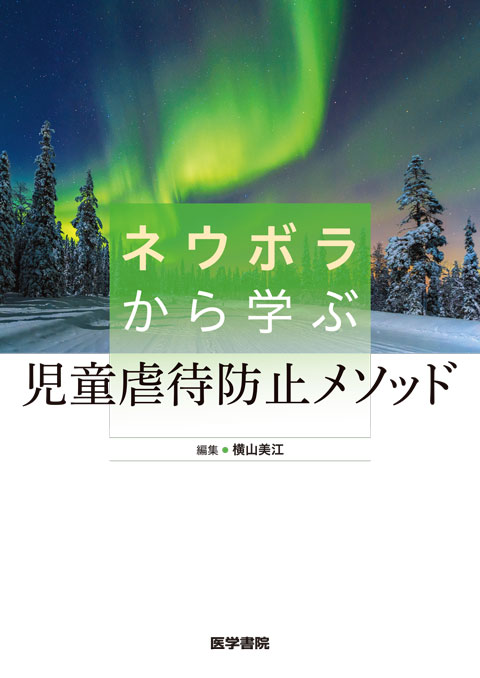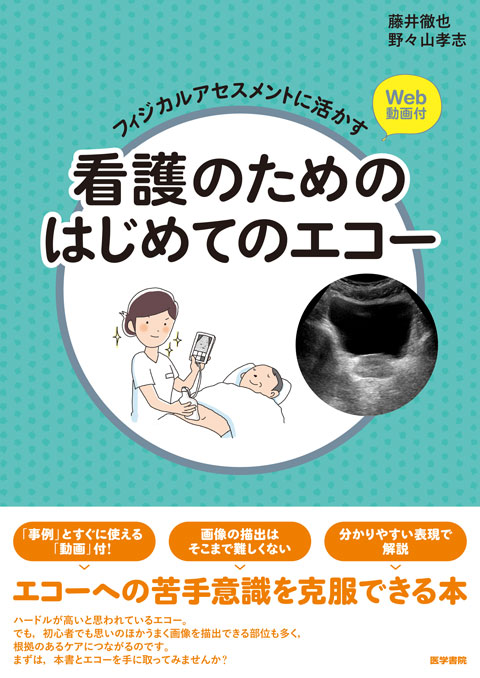MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2023.08.28 週刊医学界新聞(看護号):第3530号より
《評者》 堀内 都喜子 ライター/フィンランド文化・社会
ネウボラを知らない人も知識がある人も学びを得られる一冊
ネウボラはフィンランド語で「アドバイスの場」を意味し,フィンランドのどの自治体にもある無料のプライマリケアシステムの一つである。家庭環境や経済的背景を問わず,ほぼ国民全員が利用する制度(場所)として,約100年前から赤ちゃんと母親,さらには家族全体の健康とウェルビーイングを支えてきた。
そんなネウボラがこの10年ほど日本でも注目されるようになり,ここから妊婦・子育て家庭への伴走型支援実現のヒントを得ようとしている自治体は多い。しかし,本当の意味でフィンランドのネウボラを理解している人はまだそれほど多くはない。また,大事な要素を生かしきれないまま形だけの導入もみられる。
本書は,ネウボラを全く知らない人から知識がある人まで,皆が学びを得られる一冊となっている。第1章ではネウボラの基礎をわかりやすく解説。第2章では,主に児童虐待に対してどのような予防的支援を行っているかが,具体的な問いかけやアンケートの事例を交えながら紹介されている。何かが起きてからでは遅く,起きる前にリスクや課題を早期発見して予防していくという「予防的支援」は,フィンランドの社会保障には欠かせないアプローチである。したがって,子どもへの虐待だけでなく,パートナーとの関係や教育など幅広い分野の記事がこの章には含まれる。
第3章では家庭内暴力や虐待の疑いがある場合の対応,さらには加害者への支援も紹介されている。この部分では,フィンランドもまだまだ試行錯誤していることが見て取れるが,第2章と合わせ総じて幾重にも早期発見の機会やセーフティーネットが張り巡らされていることがわかる。また,子どもの安全とウェルビーイングを第一に,さまざまな人たちや機関が連携支援をしている。問題解決は一筋縄にはいかないが,民・官・学がともに努力する姿がうかがえる。
さらに最終章では,日本への示唆が多く含まれる。フィンランドとは人口規模も医療制度も異なる日本で,どう工夫すれば導入可能なのかが,具体的な事例に基づいて紹介されている。これだったら実現できるかもしれないと希望を抱かせてくれる。
ネウボラは少子化対策のためではなく,子ども一人ひとりの心身の健康を保障する制度である。そのために,母親だけでなく,父親,きょうだい,家族皆の健康と幸せを観察し,「誰もがいつか問題やリスクを抱え得る」ことを前提にしている。この本は,自治体の母子保健に携わっている方はもちろん,教育関係者,医療従事者,子育てを支援する団体など幅広い人たちに気付きをもたらすだろう。
《評者》 藤井 晃子 名大病院看護部長
患者さんにもチーム医療にもなくてはならないツールに
『フィジカルアセスメントに活かす 看護のためのはじめてのエコー』というタイトルをご覧になって,「えっ,看護師がエコーを実施しても良いの?」と思う方が多いかもしれません。ところが実は,看護師が超...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。