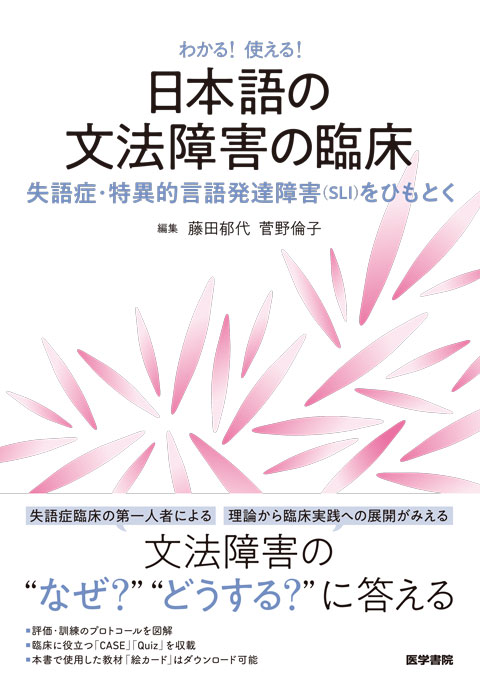FAQ
失文法を持つ失語症患者診療のポイント
寄稿 金野竜太
2023.06.19 週刊医学界新聞(通常号):第3522号より
脳梗塞などの脳の病気によって「話す」や「理解する」といった言語機能が障害された状態を失語症と呼びます。有名なものとしてブローカ失語(主に話すことができない)やウェルニッケ失語(主に言葉を理解することができない)などがあります。今回は失語症の症状の1つである「失文法」について解説します。
FAQ 1
失文法の患者にはどのような症状が現れるのでしょうか。
失文法とは文法機能の障害であり,ブローカ失語の患者で観察されることが多いとされる言語症状です。失文法の患者では,格助詞などの機能語の使用や複雑な文構造の作成が困難になります。日本語を例にとると,発話時の格助詞(が,を,に,など)の欠如や誤用が起こります。また,発話される文の長さが短くなるという特徴もあります。さらに,失文法が顕著な場合は,「今日,ごはんを食べる」と発話するべきところが「今日,ごはん」のように助詞や動詞が脱落した発話(いわゆる電文体発話)になります。このような言語産生における症状は発話だけでなく,書字においてもみられることがあります。
また,文法機能が障害されると文の理解にも影響を及ぼすことがあり,統語理解障害と呼ばれます。統語は「単語と単語をつなぐ規則」と考えるとわかりやすいです。例えば,「警察が泥棒を捕まえる」は統語的に正しい文ですが,「警察が捕まえるを泥棒」は統語的に正しくない文です。統語理解障害を有する患者では,単純な構造の短文は文法機能に頼らなくてもある程度単語から意味を推測できるため理解が保たれるものの,文構造が複雑な長文(隣町からやってきた警察が泥棒を捕まえた記事を私は読んだ)になると理解が困難になります。また,「警察」「泥棒」など,関係性が推測できる意味的な手掛かりがない文(例:太郎が次郎を捕まえる)では,文法機能に頼らないと理解が難しいため,理解が困難になります。ウェルニッケ失語の患者でも文の理解障害を呈しますが,こちらは単語理解や文構造が単純な文の理解も障害される点で統語理解障害とは異なります。
Answer
失文法とは文法機能の障害であり,発話面では助詞の欠如や電文体発話などがみられます。また理解面では,単純な構造の文理解は保たれるものの複雑な構造の文理解が障害される症状が起こります。
FAQ 2
失文法が疑われる失語症患者へはどのようにアプローチすればいいでしょうか。
失語症は,脳血管障害・脳外傷・脳腫瘍・神経変性疾患などで発症することが多く(後述),まずは原疾患に対して適切に診療を行うことが大切です。その上で,言語機能評価と言語リハビリテーションを行います。失文法の評価に関しては,まず患者の言語症状をよく観察して,FAQ1で解説した失文法の特徴がないか検討することが重要です。失文法では長い文章の理解が苦手であることが多いですが,失文法以外の要因でも文理解障害は起こります。その患者の理解障害が失文法によるものか否かを明らかにするた...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
金野 竜太(きんの・りゅうた)氏 昭和大学横浜市北部病院 内科(神経) 准教授
2002年昭和大医学部卒。07年同大大学院修了。同大神経内科に入局後,東大大学院総合文化研究科で神経言語学研究に従事。昭和大病院,昭和大藤が丘病院での勤務を経て,21年より現職。専門は臨床神経学,神経言語学。分担執筆に『わかる! 使える! 日本語の文法障害の臨床』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。