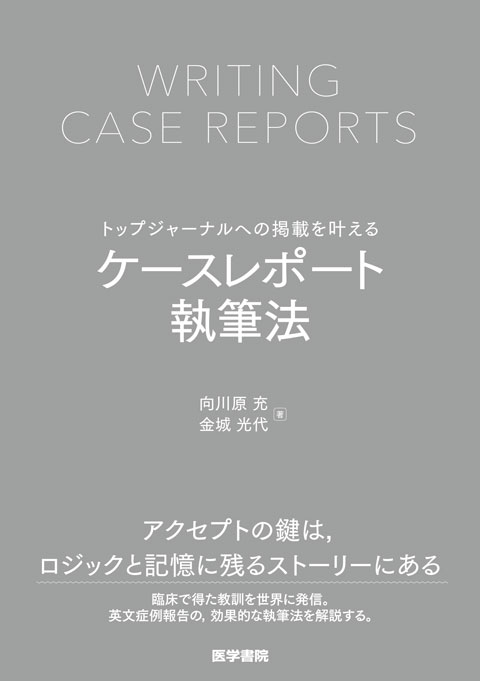医療格差に対する“治療法”を探して
向川原 充氏に聞く
インタビュー 向川原充
2023.03.20 週刊医学界新聞(通常号):第3510号より

「もしこの国に生まれていたら恐らく今日まで生きていられなかっただろう」。医学生時代に訪れたカンボジアでこう直感し,医療格差是正に向けた研究を進めるべく,現在は米ハーバード大学政治学部博士課程に在籍中の向川原氏。同課程を修了した医師は世界的に見ても数人しか存在しないという。異色のキャリアを歩む向川原氏に,その原点とめざす未来について話を聞いた。
「政策レベル」から医療にかかわりたい
――沖縄県立中部病院での内科・感染症科研修,そして宮古島で離島・僻地医療の経験を積んだ後,公共政策について学ぶため米ハーバード大学ケネディ行政大学院へ進学。現在は同大学政治学部博士課程に在籍されています。医師でありながら上記のキャリアを歩むようになった背景を教えてください。
向川原 英語を生かして仕事をしていた両親の影響もあり,幼少期から海外で働きたいと考えていました。とりわけ外交官になりたくて,国際政治に興味・関心がありました。
転機が訪れたのは小学生の頃。当時,青森県に住んでいた祖父ががんで亡くなったことでした。「都心に住んでいれば治療がうまくいったのではないか」との気持ちがどうしても残った。医療技術が発達した日本でも医療格差が存在するのではないかと考えるようになり,何よりもまずは現場を見るべく医師をめざすに至ったのです。しかし国際政治への興味関心は捨てきれず,両立できるキャリアはないかと,医学部入学後も模索していました。
次なるターニングポイントは,大学生の頃にカンボジア・プノンペンを訪れた経験です。結核に関連したフィールドワークをカンボジアで行うとの話を偶然伺い,現地調査のメンバーに加えていただきました。
――どんな出来事があったのでしょうか。
向川原 自身と同じ年頃の方が目の前で命を落としかけている姿に衝撃を受けました。幼少期の私は体が弱く,入退院を繰り返した時期もあったために,「もしこの国に生まれていたら恐らく今日まで生きていられなかっただろう」と直感し,「医療格差をなくしたい」との想いを強くしたのです。その一方で,途上国で医療を提供する一人の臨床医として活動するのでは,助けられる数に限界があるだろうとも思いました。そこで,格差をなくすという「政策レベル」から医療にかかわれないかと考えるようになったのです。
――大学生の頃にはWHO本部でのインターンも経験されたそうですね。グローバルヘルスの最前線ではどのような学びがありましたか。
向川原 WHOでは,どの地域やプロジェクトにどれだけの予算を分配するか,どの人材をあてがうべきかなど,自身がこれまで想像していた「医療」の枠組みを越えた議論が展開されていました。言わば,医療が国際政治の中に組み込まれていた。医療は人類が共通して考えなければならないイシューであることに疑いようはないものの,政治に翻弄される姿を垣間見ました。こうした経験を経て,将来の進学先として視野に入ったのが米ハーバード大学ケネディ行政大学院でした。
公衆衛生と公共政策の違い
――なぜ「行政」大学院だったのでしょう。「公衆衛生」大学院に進学する選択肢もあったように思うのですが。
向川原 基本的に公衆衛生学は「医療」という枠組みの中で物事を考えます。しかし行政大学院で主に学ぶ公共政策学の場合,安全保障や財政などの数ある政策の中で「なぜ医療に重点を置かなければならないのか」が焦点になります。すなわち議論の起点が異なるのです。どちらを学びたいかと天秤に掛けた私は,公共政策学を選択しました。
――学生時代に志を抱きつつも,卒業後に一度臨床の道へ進まれています。何か狙いがあったのですか。
向川原 医師として最前線で経験を積み,一人の独立した臨床医になりたかったからです。沖縄県立中部病院での臨床研修中は研修に専念していましたが,休暇を利用し医療ボランティアとしてイン...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

向川原充(むかいがわら・みつる)氏 ハーバード大学政治学部博士課程
2013年東京医歯大卒業後,沖縄県立中部病院で初期研修,内科(感染症)後期研修を修了。沖縄県立宮古病院にて離島診療にも従事する。19年に渡米。米ハーバード大ケネディ行政大学院公共政策学修士課程を修了し,21年より同大政治学部博士課程に在籍。専門は国際関係論,計量政治学,公共政策学,グローバルヘルス。NEJMのClinical Problem-Solving(PMID:32877587)やJAMAをはじめ,トップジャーナルに症例報告が複数掲載された経験から,そのノウハウをまとめた書籍『トップジャーナルへの掲載を叶える ケースレポート執筆法』(医学書院)が発売中。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。