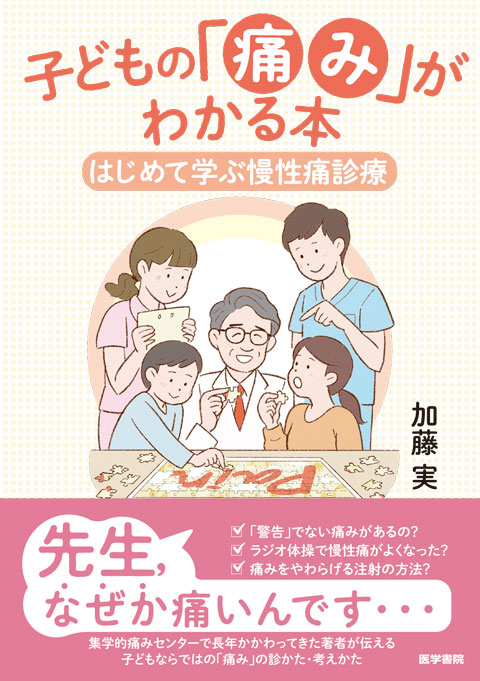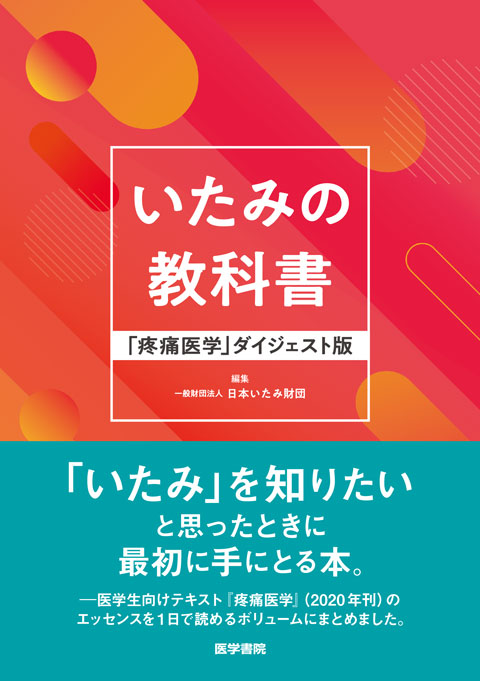治療の伴走者として子どもの痛みと向き合う
加藤 実氏に聞く
インタビュー 加藤実
2023.01.16 週刊医学界新聞(通常号):第3501号より

治療の前後に感じる不安・恐怖感を含めた痛みの体験が,その後の痛みの感じ方の増大や成人後の慢性痛の発症など,長期的に影響を及ぼすことが近年明らかとなり1),子どもの痛み対策の重要性が叫ばれている。しかし,「痛いのは一瞬だけだから」「検査・治療のためには仕方ない」などと,いまだに子どもが感じる医療行為にまつわる痛みは過小評価されやすい。
書籍『子どもの「痛み」がわかる本――はじめて学ぶ慢性痛診療』(医学書院)では,子どもの痛みに関する基礎知識や臨床現場で生かせる痛みの予防法が紹介され,子どもの痛みへの理解を深められる。本書を上梓した加藤実氏に話を聞いた。
――なぜ今,子どもの痛み対策に注目が集まっているのでしょうか。
加藤 2020年にWHOより子どもの慢性痛の管理に関するガイドライン2)が発表されたことや,「治療を受ける子ども自身の意思を最大限尊重すべきだ」という子どもの権利に関する意識が高まっていることが理由だと考えます。私は長年子どもの痛みへの対策は急務だととらえていたため,今回子どもの痛みについて系統的にまとめた書籍を出版できたことは感慨深いです。
――子どもの痛みへの対策を急務ととらえる契機はありましたか。
加藤 きっかけの1つは,2000年に日本大学医学部附属板橋病院へ異動し,NICUやPICUで麻酔を担当していた時の経験です。手術時の麻酔に携わった際,「子どもは大人と比べ痛みに敏感であり,より積極的に痛みを抑えるための取り組みが必要だ」と強く感じました。
――違いに気付いたのはなぜでしょう。
加藤 新生児と大人の痛みへの反応の差を目の当たりにしたためです。痛みなどの刺激によって血圧や心拍数が上がった後,上昇した心拍数が平常に戻るまでの時間が新生児では大人に比べ長かったのです。こうした情報は周知が進んでおり3)知識として知ってはいたものの,実際の出来事として目にしたのは初めてでした。
――知識と目の前の事実とが結び付いた瞬間だったのですね。
加藤 痛みは普段目に見えないからこそ,貴重な体験でした。そもそも新生児をはじめとした子どもは,痛みをうまく言語化できなかったり,年齢や個人の特性によって痛みのとらえ方が変わったりもします。新生児・子どもの痛みに医療者は注意して対応しなければなりません。
痛み治療の主役は患者自身,医療者はあくまで支援部隊
加藤 それ以降,ストレス度と術後の痛みの相関関係についての研究をしたり,子どもの痛み評価のスコアリングを用いながら有効な鎮痛法を探ったりといった研究活動にも取り組むようになりました。日々試行錯誤しながら痛みを抑える,あるいは予防する方法を探し,実践していましたね。
――担当した中で心に残っている患者さんはいらっしゃいますか。
加藤 小児専門病院から紹介されてきた10歳代の女の子です4)。足首をねんざした痛みが全身に広がり,私が初めて診た時には痛みで服も着られないほど。多くの整形外科,小児科で原因不明と言われ,当院を受診されたとのことでした。
そこで,小児科医・整形外科医・精神科医・心療内科医などの医師,また心理士・看護師・薬剤師も含めて議論し,最終的に複合性局所疼痛症候群(Complex Regional Pain Syndrome:CRPS)と診断しました。さまざまな方法を試した中で奏効したのが,以前がん患者の鎮痛のために開発したケタミン持続点滴治療です。
――それで治ったのですね。
加藤 いいえ。痛みが引いて歩けるようになった直後,ワクチン接種の注射の痛みが引き金になり,痛みがぶり返してしまいました。彼女と知り合ってから半年後のことです。ケタミン持続点滴治療を再度行うも奏効せず,次に考えられる持続神経ブロック治療は,「こんなに痛い状態で注射なんか怖くてできない」と初回時に拒否されていたため,途方に暮れました。
――...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
加藤 実(かとう・じつ)氏 春日部市立医療センターペインクリニック内科 主任部長
1983年日大医学部を卒業後,駿河台日大病院(当時)麻酔科へ入局。96年加トロント大麻酔科留学。2000年日大板橋病院に着任。NICU・PICUでの手術麻酔や術後鎮痛に対応した経験を契機に,子どもの痛み対策に注力するようになる。13年日大医学部麻酔科学系麻酔科学分野診療教授などを経て,22年より現職。日々患者さんと二人三脚で痛みの治療に取り組む伴走者を務めている。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2025.12.09
-
寄稿 2026.01.13
-
2026.01.13
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。