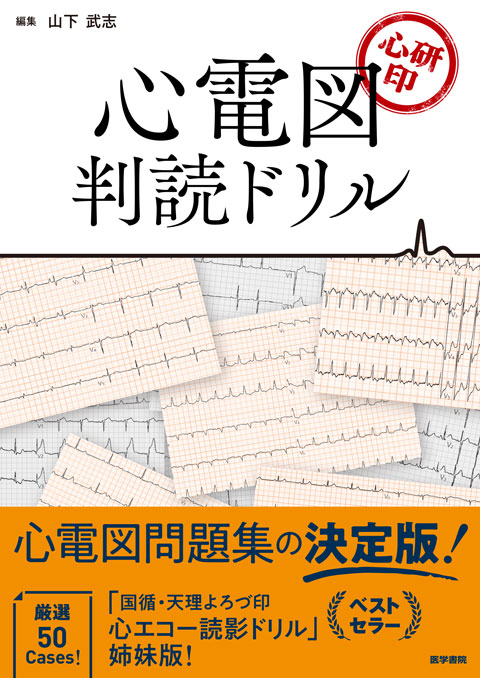MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2023.01.09 週刊医学界新聞(レジデント号):第3500号より
《評者》 村川 裕二 村川内科クリニック院長
病態,診療の手順,考え方を問う心電図ドリル
心電図のドリルです。
循環器診療の経験を積んだ人を念頭に置いて書かれています。
六本木の心臓血管研究所の先生たちの共著です。
初めから終わりまで1人の人が書いているような語り口。
共著の本は語調がギクシャクしているものもありますが,本書には一貫したトーンがあります。
症例は幅広く網羅されています。
問題の出し方は,よく言えば「自由度が高い」ですが,「あいまいで,どっちとも言いにくい」と感じる読者もいるかもしれません。
専門医試験でも大学の定期試験でも最近の選択問題では「択一式」が優先されますが,本書では「誤っているものをすべて選べ」というのがやたらと出てきます。
サラサラとは読めません。
それぞれの症例が濃いからです。
シンプルな心電図判読ではなく,「病態の本質は何か」とか,「診療の手順や思考法」まで,入口から出口まで視点は広くなっています。
「p波の形」の解釈は古典的な心電図の読み方ですが,p波みたいな小さな波形に惑わされると人間が小さくなるから,あまり気にしないほうがいいと思っていました。
本書ではかなりp波の形が取り上げられています。
「両心房負荷」という言葉も出てきます。
「波形から心臓の形の変化を察する」という基本姿勢をきちんと学んでほしいという意図かと思います。
解いてみると楽しめました。
とはいえ,半分しか正解できませんでした。
不正解には,「難しくて間違ったもの」「“誤っているもの”という設問に惑わされたもの」「そうかなあと思うもの」があります。
ST上昇の判定はあいまいですし,QT時間延長の有無などは「補正式をどの程度の心拍数まで当てはめていいか」という見解の差も影響します。
アミロイドーシス,甲状腺疾患,不適切洞頻脈などは,病態と心電図の考え方が簡潔にまとめられて印象に残るケースでした。
医学書はおざなりな中身だと引用文献が大きなスペースを占めています。
本書は隅っこに小さなフォントで2,3個付け加えられているだけで,控えめで奥ゆかしい。
手だれの循環器の専門医が腰を据えて解いても正答率70%に達するのは難しいでしょう。
パッと見て30~50%ほど解ける方には面白く勉強になりますが,ベースラインで20%しかわからないと半分も読み進められないでしょう。
興味のある方は,まず本屋さんや出版社のWebページで,第2章「実践編」をいくつか解いてみることをお勧めします。
-
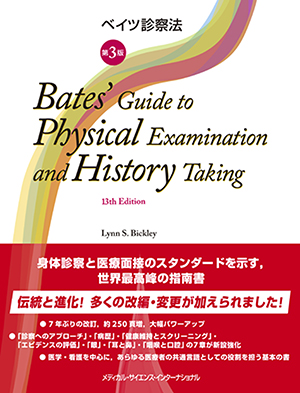
ベイツ診察法 第3版
- 有岡 宏子,井部 俊子,山内 豊明 日本語版監修
-
A4変型・頁1264
定価:12,100円(本体11,000円+税10%) MEDSi
https://www.medsi.co.jp
《評者》
大滝 純司
東医大兼任教授
北大名誉教授
多磨全生園内科医師
“厚みを増したベイツ”
今から40年近く前,私が研修医だったころ,内科学書など臨床医学の日本語の教科書は充実し始めていたものの,身体診察の教科書はまだ不足していました。そんな時に,米国留学から帰国して間もない指導医が,こんな話を聞かせてくれました。
「あちらの医学部の生協には,臨床医学の授業が始まる時期になると,ハリソンとベイツが積み上げられて,医学生がそれらと(北米では臨床実習に必須の)携帯式の検眼鏡(眼底鏡)を次々と買っていくんだよ。」
都市伝説のようなその話にひかれて,洋書のベイツを研修先の大学の図書館で探しました。それはちゃんと図書館の片隅にありました。たしか原書第3版で,そのころからお世話になっています。
現在,英語で書かれた原書はもう13版になりました。それだけ版を重ねてきている理由は,医学生や看護学生から教員まで多くの医療関係者が学ぶのに適した基本的な身体診察について,網羅的,実践的にわかりやすく,そして過不足なく記述していることにあります。
「ベイツ」は人の姓ですが,このベイツさんが女性で既に故人であることはご存知でしょうか。米国でも女性の名前が書名になった教科書は珍しく,内容の素晴らしさと共に広く知られているのです。
初版は身体診察に限定され,後に医療面接に関する記述が加わりましたが,ずっと診察のバイブルとされています。北米の医学校の臨床系某教員によれば,教授回診でのプレゼンで,例えば「腸蠕動音は正常です」と述べたのに対して「その根拠は?」と問われたら,「ベイツに〇〇と書いてありました」と言えば大丈夫なのだそうです!
ここで紹介する日本語版の『ベイツ診察法』は2008年に...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。