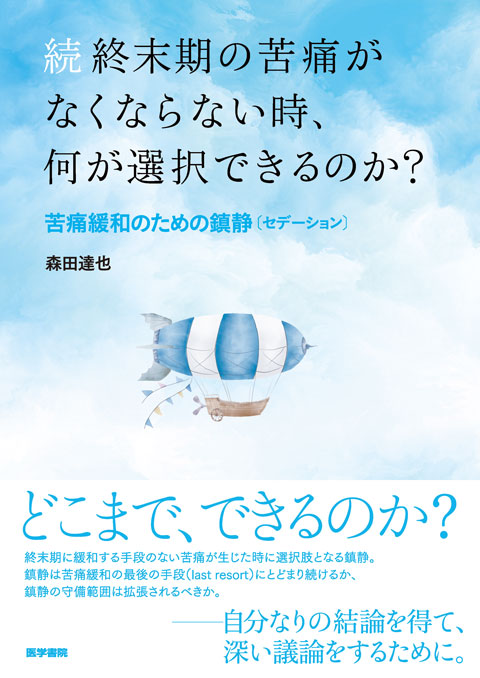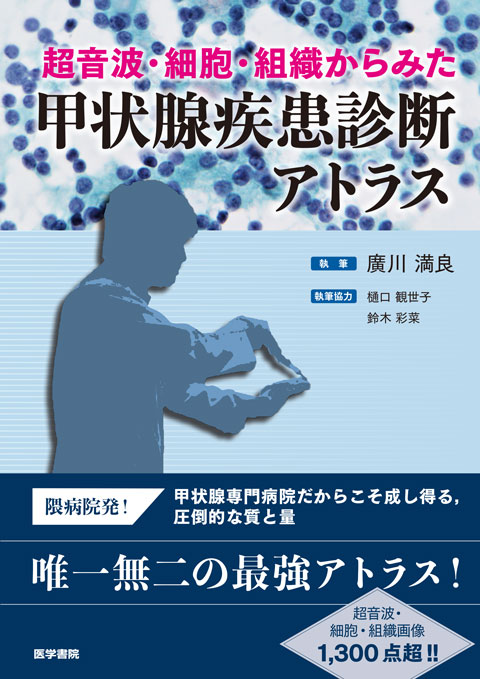MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2023.01.02 週刊医学界新聞(通常号):第3499号より
《評者》 今井 堅吾 聖隷三方原病院ホスピス科部長
終末期の苦痛と鎮静に関するモヤモヤを解き明かす
終末期の臨床では苦痛がなくならない時があり,最後の手段として苦痛緩和のための鎮静がしばしば必要となります。鎮静により苦痛は軽減するものの意識が低下したまま最期を迎えることや,余命の短縮が懸念されることで,鎮静は医療行為にもかかわらず,その実施は各医療者の信念に大きく依存する場合があります。そして鎮静の議論をすると何かモヤモヤした気持ちになったり,議論が噛み合わなかったりすることが多くありますが,本書はそのすっきりしない部分に焦点が当てられています。
著者の森田達也先生は,20年以上前から終末期の鎮静に臨床・研究両面で携わり,鎮静の定義を世界に提案し,鎮静ガイドラインの作成に取り組んでこられました。鎮静を深く考えるためには,医療のみならず,倫理,社会,法律的側面の理解が必要です。本書には,医療以外も含めて各分野の専門家や海外の研究者との勉強会や交流から得た知見も盛り込まれており,おそらく世界で最も包括的に終末期の苦痛と鎮静を俯瞰した一冊ではないかと思います。各分野の勉強会に森田先生と一緒に参加しましたが,印象に残っているエピソードを本書の内容と絡めてご紹介します。
Episode1:法律家との事例検討で,「この鎮静を行うと余命が縮まることを予想はしていたが,意図していなかった」と伝えたところ,「1分でも余命を縮めた場合は,殺人罪に該当する可能性がある。余命は縮まるかもしれないと認識していたなら未必の故意はあり殺人罪,認識していないなら過失致死罪が成立する可能性がある」と回答があり,大いに汗をかきました(もちろん即刻有罪という訳ではありません)。鎮静が生命を短縮するのなら,鎮静をすることは何らかの罪に問われるのではないかと漠然と不安に思っている医療者にとって,法律家のこの一言は衝撃的です。刑法で罪になるとはどういうことなのでしょうか。そして,そもそも鎮静は生命を短縮するのでしょうか。
Episode2:緩和ケア医は,「鎮静は安楽死とは違う!」と普段から強調しているのですが,法曹界での安楽死とは,「苦痛を緩和し安らかに死を迎えさせる行為」全般を指すと教えてもらいました。もし鎮静が余命を短縮するなら「間接的安楽死」とされ,これが法的に許容されるためには「積極的安楽死(致死性薬物を投与して死期を早める)」とほぼ同じ条件が必要とのことでした。余命を短縮しない場合は「純粋安楽死」と呼ばれることを知り,「法的には私たちは日々純粋安楽死(時に間接的安楽死)を行っているんだー」と苦笑いしていました。法律における「安楽死」の定義と,医療者がとらえるそれはどこまでが同じで,どこからが異なっているのでしょうか。「安楽死」というだけで私たちはぐっと身構えてしまいますが,そのあたり法律では少し異なるようです。
Episode3:鎮静の倫理的中核をなす相応性原則について,例として湾岸戦争が妥当かの判断にも相応性が用いられると,倫理の先生が教えてくれました。相応であるためには,方法(米軍のイラク攻撃)が目標達成(より良い世界平和を達成する)をもたらすと見込まれる選択肢の中で最も害が少なく,必要を超えない最小限でなければならない(イラク全土にミサイルを撃ち込むのはやりすぎ)といった話でした。相応性の考え方は他分野でも多様に用いられているわけですが,さて,鎮静を妥当化する倫理を相応性に求めた場合にはどうでしょうか。苦痛が緩和されれば,どの程度まで意識の低下や生命の短縮が許容されるのでしょうか。倫理的な深い議論が必要となるところです。
こういったエピソードが整理されて本書には盛り込まれています。終末期の臨床にかかわる方々に特にお薦めしますが,誰もが経験する人生の終末期がどのようであってほしいかを考えるために,多くの皆さまにご一読をお薦めします。
《評者》 坂本 穆彦 大森赤十字病院顧問
甲状腺疾患に興味を持つ全ての人へ
隈病院(神戸市)はわが国の甲状腺疾患の診療をリードしている専門病院です。この病院で多年にわたり病理診断(細胞診,組織診)を担当されているのが,本書の執筆者である廣川満良先生です。廣川先生は自身で超音波ガイド下穿刺吸引細胞診の検体採取もルーチンで行っている稀有な専門家です。このたび,これまでの幅広い活動の集大成として完成したのが本書です。
廣川先生が育成し,共に活動している細胞検査士の方々も共同執筆者などに名を連ねています。彼女らは英文論文の執筆や国際学会での発表もこなすスーパー細胞検査士です。活動の一端は巻末の文献リストにも垣間見ることができます。
本書の執筆陣のお名前を見ただけでも,強力な布陣であることがわかりますが,実際に本書を前にすると,一般の書籍よりも大きいA4判というサイズと本の重さによって,内容における重量感が予感されます。
本書の内容は大きく5つの章に分かれています。全体を通しての記述は全て箇条書きで,とても読みやすく理解しやすい配慮がなされています。
第Ⅰ章「診断における基本的知識」では,超音波検査などの画像診断,細胞診・組織診の検体採取・標本作製,甲状腺腫瘍の分類が示されています。免...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。