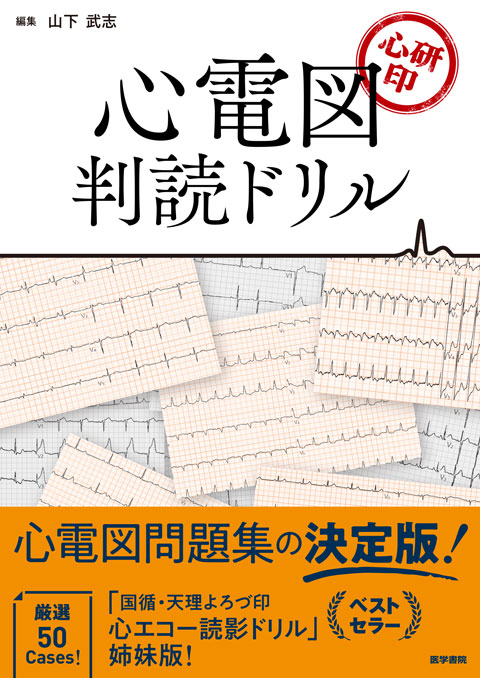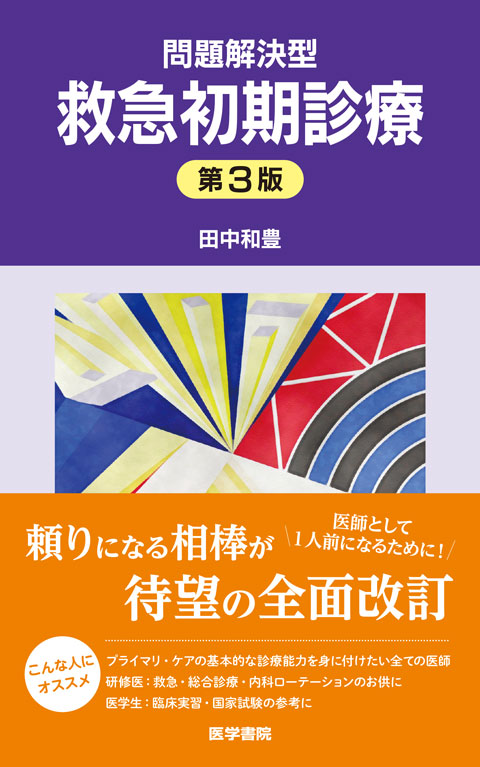MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.11.14 週刊医学界新聞(レジデント号):第3493号より
《評者》 井上 博 富山大名誉教授
山下塾で心電図判読スキルアップ!
「心電図が読めるようになるにはどうしたらよいですか?」という質問はいつの時代にもある。小生が現役時代,医学生や研修医諸君に答えていたことは,「まず何でもよいから一通り心電図の本を読んで基本的事項を理解し,その後は一例一例の心電図を読んで専門家に教えてもらう」であった。本書の編者はまさに同じことを序文で述べている。しかし周囲に心電図の専門家が必ずしもいるとは限らない。そのような場合どうすればよいか? この難題に応えてくれるのが本書である。心臓血管研究所の山下武志先生とその5人のお弟子さんの手で上梓された。
基礎編(小手調べ)7例,実践編(いよいよ本番)43例の計50例から成る。まず簡単な病歴と心電図が提示され,多肢選択形式で質問に対する回答を読者が考えるという形式である。解答としては心電図所見の場合もあれば,疾患名の場合もある。解説では心電図所見が丁寧(重要な部分にはアンダーライン)に説明され,必要に応じて胸部X線写真,冠動脈造影,心エコー図などが示され,読者の理解を容易にする工夫がされている。心電図や,提示されている画像は鮮明で見やすい。解説に続いてLearning Pointとして,その心電図所見で注意すべき要点が示され,最後に深く学びたい読者のために参考文献が引用されている。本編に続いて逆引き疾患目次があり,心電図所見,疾患名から検索できるようになっている。最後にLearning Pointのまとめが50例分示され,心電図所見のカルテへの記載例が英語で示されている。痒いところに手が届く工夫が随所になされている。
本書を通読すれば代表的な心電図所見,不整脈,疾患が網羅的に学べる。甲状腺機能亢進症や気胸など臨床現場でしばしば遭遇する疾患についても取り上げられており,一昔前には想像できなかった新型コロナウイルスワクチン接種後の副作用や心房細動既往例のAI診断などup-to-dateな話題も取り上げられている。AIによる心房細動既往例の診断では4症例が提示されているが,全くお手上げであった。AIが重要と判断した心電図所見の中には,これまでの知識でなるほどと思わせられるものもあるが,心房細動発生とどう結びつくのか理解に苦しむものもある。今後,心電図のAI診断が普及してくるのであろう。
心電図に関して基礎的な知識を持っており,さらに臨床的な心電図判読力を増したいと願っている若手医師,医学生に本書を薦めたい。通読するもよし,折に触れて(受け持ち患者さんの疾患に応じて)ひもとくもよし。全国どこにいても,あたかも心臓血管研究所で山下先生から心電図判読スキルを学ぶことができる,このような本を企画し形にまとめ上げた編者,著者,そして出版社に敬意を表したい。
最後に1つだけお願いをしたい。提示されている心電図はきれいであるが,惜しむらくは一部の心電図では上下の胸部誘導のQRS波が重なっていて見にくい。版を改める機会があれば,ぜひとも感度が半分の記録も並列して提示していただきたい。30年以上前に山下先生に心電図判読を少しばかり教えたことのある先輩からのお願いである。
《評者》 増井 伸高
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。