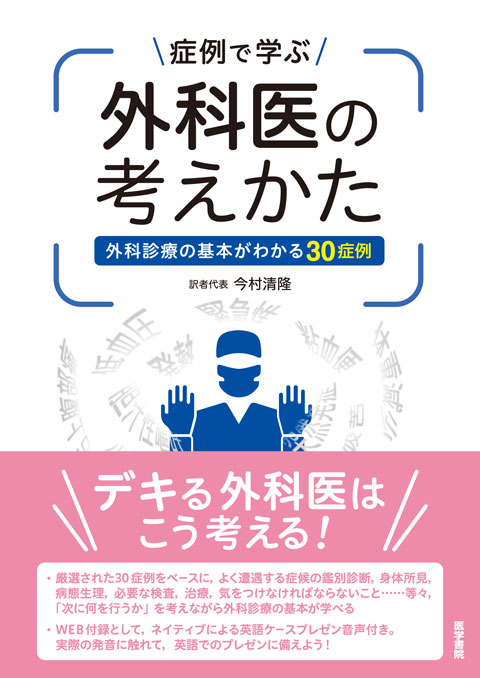外科系志望の医師を増やす戦略
対談・座談会 鈴木研裕,髙見秀樹,磯部真倫
2022.11.14 週刊医学界新聞(レジデント号):第3493号より

日本外科学会は2022年4月,「外科医希望者の伸び悩みについての再考」と題したメッセージを発信した。背景には,18年に新専門医制度が導入されて以降,22年度の専攻医採用者数が初めて減少に転じたことがある。そうした中,独自に開始した外科専門研修プログラムにより志望者数を大きく伸ばしているのが聖路加国際病院だ。同院で外科専門研修プログラムの副統括責任者を務める鈴木氏を司会に,名古屋大学医学部附属病院で臨床実習や研修医教育に携わる外科医の髙見氏,産婦人科医としての顔を持ちながら新潟大学医歯学総合病院全体の教育を統括する磯部氏による座談会を通じて,外科系志望の医師を増加させるアイデアを検討する。
本当に外科は不人気なのか?
鈴木 2022年度の外科専攻医採用者数は846人と,ここ数年増加してきた採用者数が減少(昨年度比58人減)に転じました1)。専攻医全体に占める割合(9.0%,2022年度)も低下しており,対策は急務です。
髙見先生は医学生と交流する機会が多いと伺いました。やはり外科は人気がないのでしょうか。
髙見 外科に実習をしに来た医学部5年生に対して「将来どの診療科を考えていますか?」とアンケート(複数回答あり)を行うと,外科にチェックを付ける方は4割程度存在します。臨床実習終了後に再度アンケートをしてみても,「思ったより良かった」「臨床実習開始前に比べて外科に興味を持ちました」との回答が意外と多いです。リップサービスが含まれていることを差し引いても,人気が全くないわけではないととらえています。しかし,1学期に比べて2学期,3学期と,外科を将来の選択肢に挙げる医学生が減っていく傾向がみられます。さまざまな診療科を見て回る中で,相対的に外科の魅力が負けてしまっているのでしょう。
鈴木先生は外科の人気が低迷している原因をどうとらえていますか。
鈴木 外科医のキャリアパスに問題があると考えています。何年もかけて下積みをした結果,最終的に執刀医の座を勝ち取れる医師は一握り。勝ち残れた人にとっては面白い領域であるのは間違いないのですが,それが難しいと早い段階で判断してしまえば,わざわざ外科に進もうとは思わないはずです。
髙見 組織としての構造的な問題ですね。若手に手術の機会が与えられる施設には志望者が増える傾向にあります。リクルートという観点からみても,若手が安全に手術経験を積める環境の担保は重要でしょう。聖路加国際病院では初期研修医が手術を担当することはありますか。
鈴木 はい。「体腔内結紮で2分を切ること」などを条件にして,全てにクリアすれば虫垂切除術や胆嚢摘出術を行ってもらいます。ただ,ローテートする初期研修医約20人の中で,執刀できるのは毎年2~3人程度です。
髙見 昔からそのくらいの人数ですか?
鈴木 近年は明らかに減っています。腹腔鏡手術の件数が増えたことにより,手術参加へのハードル自体が上がってしまいました。
髙見 本来経験の浅い時期に行うはずであった結腸切除術や胃切除術などが,腹腔鏡手術に置き換わってしまっていることが,この問題に拍車を掛けているように感じます。高い技術力が求められるがゆえに,若手が参加しにくくなりましたよね。
磯部 学生時代や医師としてのキャリアの早い段階で,チームの一員として医療に貢献している感覚が育まれにくいことは,志望者を減らしてしまう要因となってしまいます。内科であればdecision makingに携わって治療方針の検討にも参画できますが,手術となるとどうしても難しい。臨床実習や臨床研修というごく短期間でやりがいを伝えることは相当ハードルが高いです。
髙見 「貢献している感」は大事ですよね。私の場合,手術見学している医学生に「ちょっとここ持ってて!」とお願いすることもあります。
鈴木 私もです。皆喜んで参加してくれます。手術の場面に限れば,執刀医がどのような思考回路で手術に臨んでいるのか,例えば「郭清範囲をどう決めているのか」といったことを言語化し伝えていくことも,興味関心を深めてもらうには重要なポイントでしょう。
短期間で外科のやりがいを伝えるには
髙見 臨床実習を担当する医師の中には,「早く実習を切り上げたほうが喜ぶだろう」など,学生に配慮しすぎている方が多い印象を受けます。けれども外科に進みたいと考えている学生にとっては,将来自分の仕事になり得る環境を体感する機会を減らしてしまっているだけです。密度濃く,外科医の仕事を隣で見せることが重要だと考えます。
鈴木 その問題は学生だけでなく,ローテート中の研修医への対応でも同じことが言えますね。働き方改革の影響もあり,18時には退勤できるような体制を敷いていますが,外科をローテートする数週間の間で,指導医側が見込んだ成果に達しているかと問われると,昔ほどは到達していないと言わざるを得ません。
磯部 研修期間が短すぎて,苦手意識のあった研修医が「できる!」という感覚になる前に研修が終わってしまっている可能性は否めないです。
髙見 そのため当院では外科に割り当てられる研修期間の4週間を2週間ずつに分け,2領域の研鑽に励んでもらっています。本音を言えば,上部,下部,肝胆膵,乳腺内分泌の4領域を全て回ってもらいたいのですが,各領域1週間ずつだと患者さんの術前,術後の流れが一通り把握できないために,このような体制にしました。
鈴木 それは面白いですね。当院では第2助手として手術に参加してもらったり,患者を受け持ってもらったりします。以前はプライマリーで,基本的には受け持ち患者が退院するまでを全て担当してもらう方針でしたが,働き方改革に伴い,チーム制を敷くことになりました。勤務時間の是正は達成しつつあるものの,受け持ち患者を必ずしも入院時から退院時まで診ることができなくなった点はマイナスに働いているように感じます。
当院外科の伝統は,「自分ができることは自分でやるな。できるよう下を指導しろ」。しかし,この伝統も働き方改革で岐路を迎えました。定時の勤務時間に収めるには,先輩が代わりに担当してしまうことが多くなります。そのほうが早く業務が終わり,効率的だからです。けれども,若手の伸びしろを消してしまっているのではと,疑問を持つようになりました。
髙見 外科診療は,1人の医師にかかる負担も大きいためにチーム制を採用すべきだと考えますが,「もうすぐ交代時間だから,あとはお任せします」など,責任感がやや希薄になっているようにも感じますね。働き方改革の推進は重要である一方で,こうした問題にも同時に目を向けていかなければならないと考えています。
産婦人科で取り組まれる戦略的なリクルート活動
鈴木 磯部先生が専門とする産婦人科は,専攻医採用者数は一時期減少したものの,最近では増加傾向を示し始めたようですね。
磯部 ええ。2022年度の産婦人科専攻医採用者数は517人(前年度比42人増)と,初めて500人を超えました1)。最も不人気と形容されたこともある診療科でしたから,上昇傾向...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

鈴木 研裕(すずき・あきひろ)氏 聖路加国際病院 消化器・一般外科 副医長
2003年信州大卒業後,聖路加国際病院にて外科の修練に励む。08年同院消化器・一般外科チーフレジデント。09年に外科専門医資格を取得した後,米テキサス大MDアンダーソンがんセンター消化器腫瘍科フェローとして渡米。12年に帰国したタイミングで聖路加国際病院にて研修医教育に携わるようになる。現在は,同院の外科専門研修プログラムの副統括責任者として,研修のカリキュラムづくりからリクルートにも携わる。22年4月より現職。

髙見 秀樹(たかみ・ひでき)氏 名古屋大学医学部附属病院 卒後臨床研修・キャリア支援センター センター長補佐
2003年名大卒。名古屋記念病院,小牧市民病院にて外科修練の後,12年名大大学院消化器外科学にて博士課程に進むと同時に,肝胆膵外科の臨床に携わる。15年に大学院を修了後,同大の教育専任教員になったことで医学教育に注力するようになる。21年4月より現職。20年から2年間は文科省医学教育科の技術参与として出向もした。現在は臨床実習や研修医教育,肝胆膵外科医教育に携わるほか,病院全体の研修医指導や指導医講習会の講師も担う。

磯部 真倫(いそべ・まさのり)氏 新潟大学医歯学総合病院 総合研修部副部長/医師研修センター副センター長
2002年山形大卒業後,同大病院産婦人科に入局。08年大阪労災病院産婦人科。婦人科腹腔鏡手術を専門とし,新潟大と関連病院における腹腔鏡手術の実施および教育に取り組むため,13年新潟大病院産科婦人科に助教として異動。21年5月より現職。現在は新潟大の医学生に対する卒前教育の実施や,新潟大病院にて行われる臨床研修全体の統括を担う。外科教育も専門としており,日本全体で外科医の教育マインドの向上に取り組む。また,日本産科婦人科学会未来委員会に所属し,産婦人科医のリクルート活動を全国で支えている。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。