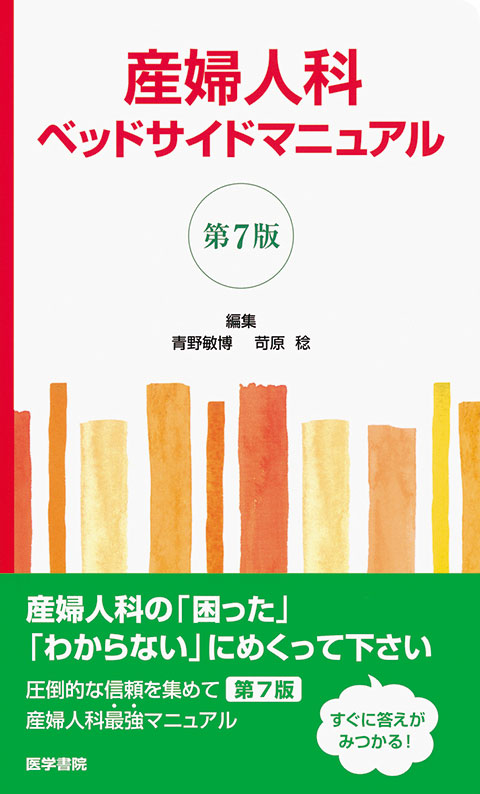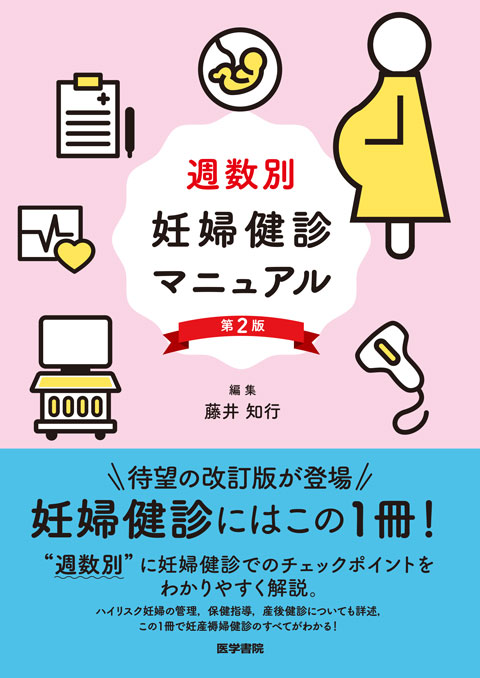安全な無痛分娩提供体制の構築をめざして
海野信也氏に聞く
インタビュー 海野信也
2022.10.24 週刊医学界新聞(通常号):第3490号より

過去10年で約20万件減と国内の分娩件数が減少する中,これまで諸外国に比べて著しく少なかった無痛分娩の実施件数は年々増加する傾向にあり,安全な無痛分娩の実施に関するコンセンサス形成が求められていた。そうした状況を受け,2017年以降厚労省,関連専門学会は,無痛分娩関係学会・団体連絡協議会(JALA)の設立を含めた体制の整備を進めてきた。その歩みについて,JALA総会議長である海野氏に話を聞いた。
――2017年に安全な無痛分娩提供体制の整備に向けた動きが始まりました。きっかけは何だったのでしょうか。
海野 メディア報道に伴う社会的関心の高まりです。無痛分娩中に母体の状態が悪くなり寝たきりになった方,亡くなった方の事例が繰り返し報じられたのが大きく影響しました。また,日本産婦人科医会をはじめとする関係学会・団体では,2010年から妊産婦死亡報告事業に取り組み,妊産婦死亡事例の再発防止策を検討して,「母体安全への提言」1)として解析結果を毎年公表していますが,その中でも,無痛分娩の安全性への懸念が指摘されました。
――本格的な体制整備の動きよりも以前から,妊産婦死亡事例に関する調査が行われていたのですね。
海野 ええ。国内の妊産婦死亡事例は,2010年から現在に至るまで,おおよそ年間数十件です。総分娩件数は100万件前後で推移していますから,規模の大きな分娩施設でも妊産婦死亡に出合うことはまれ。いざ目の前で妊産婦死亡が起きたとして,その理由は自施設だけで考えていてもなかなかわからないわけです。妊婦さんが亡くなるのは大変な悲劇であり,少しでも減らすための方策が必要でした。そこで改善の方針を立てるため,国内の死亡事例を集めて検討し,原因を見極める妊産婦死亡報告事業が始まったのです。
――事業を通してどのような問題が見えてきましたか。
2010年当初の分析でまず問題として挙がったのは産後の大量出血でした。ただこれは医療体制が整備されるにつれ徐々に減ってきた。そうした中,2017年になって,帝王切開や無痛分娩の麻酔が妊産婦死亡に関連する可能性が指摘されました。もちろん当時は実際に因果関係があるのか定かでなかったのですが,麻酔を使用した分娩,とりわけ無痛分娩の安全性を確認・検討する必要があることは明らかでした。そうした検討が開始される時期に,無痛分娩の死亡例の報道が相次いで起こった,という事の次第です。
――その頃の無痛分娩の診療体制は,どのようなものだったのですか。
海野 当時は診療体制に関して,学会のガイドラインなどの基本的な大枠さえ存在していませんでした。そもそも,無痛分娩がどこで,どのように,どのくらい行われているのかという基礎的なデータすら把握できていない状況でした。ですから,まずは現状を知ることが必要だったのです。その成果が日本産婦人科医会の「分娩に関する調査」2)です。分娩施設約2000のうち無痛分娩を行う施設は500ほど。全分娩件数に占める無痛分娩の割合が約6%で,その割合は増加傾向にあることが明らかになりました。一方で,無痛分娩と妊産婦死亡との間に明確な関連性はみられませんでした。もちろん関連がないとは言い切れませんが,調査結果に鑑みると無痛分娩そのものを危険視するほどではない,との結論に至りました。
硬膜外麻酔に伴うリスクへの準備を怠らない
――つまり無痛分娩の安全性に問題点はなかったということでしょうか。
海野 必ずしもそうではありません。子宮破裂や出血過多であれば麻酔が原因で起こったのかはっきりとはわかりませんが,全脊椎麻酔に関しては明らかに硬膜外麻酔の合併症です。厚労省の研究班が把握した範囲では,10年間で約50万件と推定される無痛分娩のうち4例で全脊椎麻酔による死亡・脳障害事例が報道事例だけでも確認...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

海野信也(うんの・のぶや)氏 JALA総会議長/JCHO相模野病院周産期母子医療センター顧問
1982年東大医学部卒後,同大病院産科婦人科学教室入局。焼津市立総合病院等を経て,94年米コーネル大獣医学部生理学教室客員助教授。帰国後は東大産婦人科講師,長野県立こども病院産科部長,長野県総合周産期母子医療センター長等を歴任し,2004年北里大産婦人科主任教授,12年同大病院長などを経て,22年より現職。18年よりJALA総会議長,19~21年日本産科麻酔学会理事長。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。