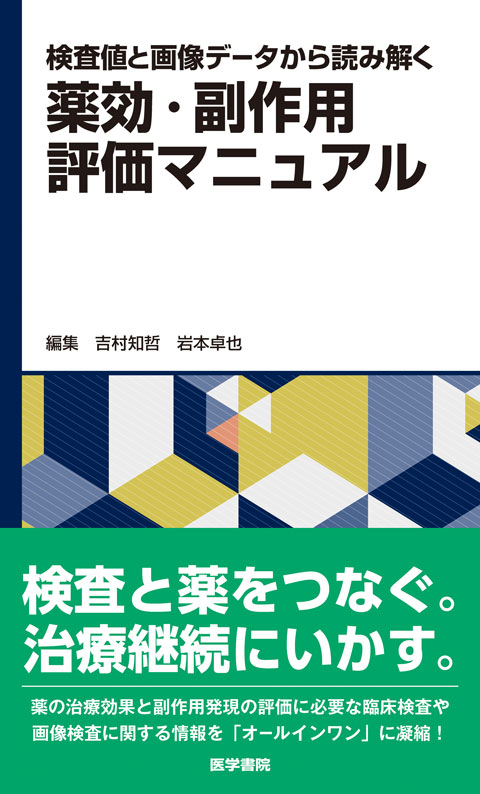MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.10.17 週刊医学界新聞(レジデント号):第3489号より
《評者》 成田 崇矢 桐蔭横浜大教授・スポーツ健康政策学部 スポーツテクノロジー学
乗車した読者の治療概念を進化させる一冊
本書の初版は,2001年に発行された。この「アナトミー・トレイン:筋膜経線」というものに触れ,今まで,筋,骨,関節と別々にとられていた治療概念に「つながり」を意識した人も多かったと思われる。今回の第4版でも,多くの最新情報が掲載されている。「筋膜(fascia)」という用語は,日本において急激に広まっているものの,未知の部分も多い。本書は,まさに電車のように,とどまることなく最新の情報を取り入れて進化している。
特筆すべきは,著者トーマス・W・マイヤース氏は,間違いなく臨床家であるという点である。それは,「治療の核心は手技の応用にとどまらず,聴く,見る,感じる,そして理解する能力にある。少なくともこれが本書の根幹である」と言い切っている点と,ある一定のルールに従えば「読者が本書に記載していない列車を加えることができる」と著者の考えが全てではなく,読者自身が創意工夫により新たな発見をしても良いと自由度を与えている点からもうかがえる。まさに本書の根幹は臨床にあり,単なる解剖書とは異なり,本書にあふれる概念を理解すれば,間違いなく臨床の一助になるというのが,読後に抱いた第一印象である。
本書は11章で構成され,第1章「レールを敷く」では,アナトミー・トレインの考え方が,エビデンスも含めて理論的に紹介されている。特にこの概念が生まれた歴史も丁寧に書かれており,先人たちに多くの敬意が込められており,好感を覚える。各論に当たる第2~9章では,アナトミー・トレインのルールと,各アナトミー・トレインの詳細が解剖にそって解説されている。この筋膜連結こそが,本概念の特徴であるが,正直,一度読んだだけで理解するのは難しい。しかし,本書では,動画での解説もされており,映像で3次元的にとらえることが可能であるため,かなり理解が進む。何度も繰り返し見ることもできるため,繰り返し視聴することをお勧めする。
第10章「アナトミー・トレイン・イン・ムーブメント」,第11章「ボディリーディング®」では,アナトミー・トレインの概念を応用した治療法が解説されており,第2~9章で得た筋膜のつながりの臨床応用がわかる。この章で述べられていることを各読者の臨床に応用することで,読者の臨床力が飛躍的に向上するヒントが数多く掲載されている。ぜひ参考にしてほしい。
85ページにわたる付録1「膜読本」は,「膜(fascia)」に対する最新の情報が,エビデンスも含めて重厚にまとめられている。筋は骨の近位端と遠位端のみに付着するという観念的概念を変え,正しく一般化したいという著者の想いが表れたパートだと思われる。全ての「筋膜(fascia)」にかかわる治療者に一読していただきたい。
本書は,これまでのアナトミー・トレインを超える,より進化したアナトミー・トレインであり,乗車した読者の治療概念を進化させる一冊である。
《評者》 池田 龍二 宮崎大病院 教授・薬剤部長
包括的に臨床能力を高めたい薬剤師にお薦めの一冊!
くすりの専門家である薬剤師は,医薬品に関する医療安全を担保しながら薬の治療効果および副作用を適切に評価し治療継続につなげる役割がある。そのためには,薬の治療効果および副作用を正しく評価し,的確に対処することが求められる。しかしながら,悪性新生物,虚血性心疾患,糖尿病,精神疾患など疾患が多岐にわたり,科学の進歩で薬物療法も多様化・複雑化する中で,薬の治療効果や副作用を臨床検査値や画像データと関連させ適切に評価することは容易なことではない。
本書は,「薬の治療効果と副作用の評価項目」と「臨床検査・画像検査の評価ポイント」の2部構成となっており,医薬品を評価する上で必要な臨床検査値や画像検査を医薬品の有効性と安全性の観点から関連付けてわかりやすく解説している。
「薬の治療効果と副作用の評価項目」では,疾患に関連する薬剤と臨床所見,評価に必要な主な検査,評価のタイミングが記載されている。特に,本書では,臨床現場で確認すべき臨床所見,バイタルサイン,血液検査,画像検査などが薬効別に理路整然とまとめられており,治療の有効性・安全性を担保する上で大いに役立つ内容となっている。
また,「臨床検査・画像検査の評価ポイント」の項目では,血液一般検査,肝機能検査,腎機能検査,出血・凝固・線溶系関連検査,電解質検査,糖代謝検査,脂質代謝検査,ホルモン関連検査,免疫・アレルギー関連検査,感染症検査,腫瘍マーカー・がん関連遺伝子検査,尿検査など各項目について,検査項目の特徴や病態との関連性とその意義・機序を含め,評価のポイントに関してわかりやすく記載されている。さらに,心電図検査,脳波検査,呼吸機能検査,X線検査,血管造影検査,超音波検査,CT検査,MRI検査,核医学検査などに関して基本的な考え方や病態との関連性が画像を含め具体的に明記されており,読者の知識・理解をさらに深めることで,薬物療法に関...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

![アナトミー・トレイン [Web動画付] 第4版 徒手運動療法のための筋膜経線](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/4216/6071/0392/110492.jpg)