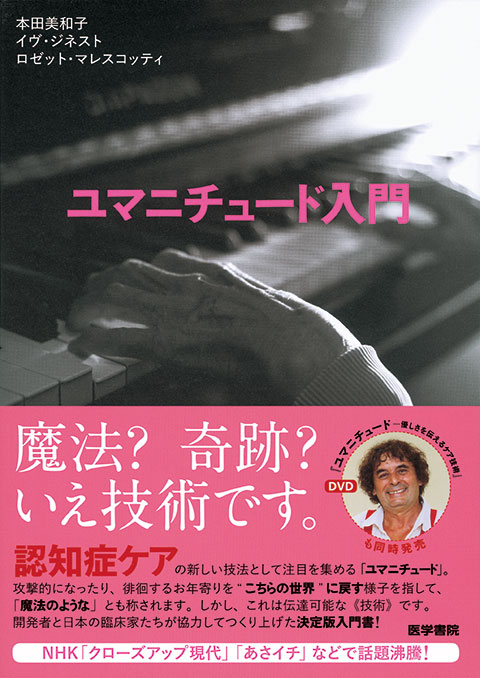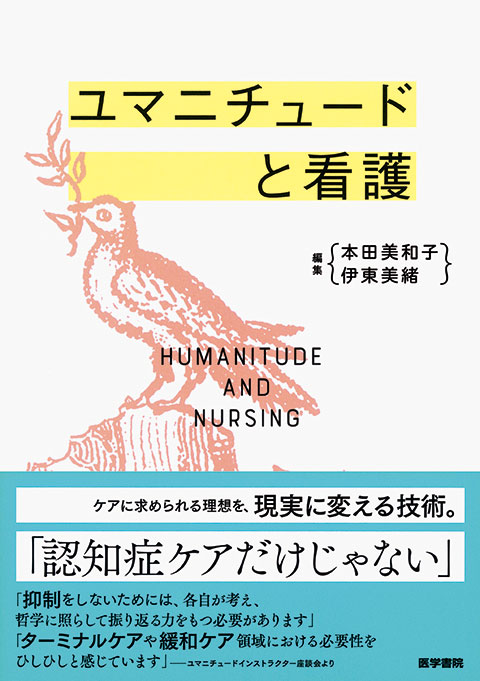医療系学部教育におけるユマニチュード®の現在と未来
寄稿 伊東美緒
2022.09.26 週刊医学界新聞(看護号):第3487号より
4つの柱と5つのステップで信頼関係を築く
ユマニチュードとは,フランス人のイヴ・ジネスト氏とロゼット・マレスコッティ氏によって開発された,とりわけ言語中心のコミュニケーションが難しい人に治療やケアを提供する際,相手に不安や混乱を与えないためのケア方法である。“人とは何か”,“ケアをする人とは何か”という哲学的な問いに基づいた技術であり,ケアを受ける人が言語を理解できない状態であっても「自分は大切にされている」と感じることができる,人間らしさを尊重したケアが提供される。
ユマニチュードの基本的な技術は,4つの柱と5つのステップで構成される。4つの柱は,①見つめる,②話しかける,③触れる,④立つ(立位援助),の基本となる支援である。ユマニチュードにおいて特徴的と言えるのは,まず①,②,③を同時に組み合わせて行うマルチモーダル・コミュニケーションにより,視覚・聴覚・触覚が刺激され,ポジティブな感情が生み出されるという点である。また,相手の状態に合わせた具体的な方法が存在する点も特徴的だ。例えば①では,近づいて話しかけても相手がこちらの存在に気がつかなければ,目と目の距離を20センチくらいまで近づけ,目を合わせたまま話しかける。これに加え,④ではあらゆるケアの場面において短時間でも座位や立位を促し,身体機能の維持・改善も目指す。
5つのステップは,①出会いの準備(自分の来訪を告げる),②ケアの準備(ケアの同意を得る),③知覚の連結(治療やケアを実施する),④感情の固定(行ったケアを良い印象として記憶に残す),⑤再会の約束(次に来る時を伝える)というものであり,相手に近づき,治療・ケアを行い,離れるまでの手順が一つのシークエンスとしてまとめられている。治療やケアを行う際に4つの柱と5つのステップを用いて「目の前にいる人はいい人だ」と認識してもらい,相手と良い関係を構築することで,本人に負荷がかかる治療やケアであっても受け入れられる確率が高まる。
コミュニケーション教育としてのユマニチュードの可能性
群馬大学医学部では,医学科の「医系の人間学」と保健学科看護学専攻の「老年看護学方法論・演習」の講義において,ユマニチュードを学習する。生徒は講義の中で,ユマニチュードの理念と方法論について実際の患者の変化を撮影した動画で学び,コミュニケーションの影響力を理解する。また,実際に学生同士で目を合わせたり触れたりする演習により,相手の目を近くで見つめ続けることや,触れ続けることの難しさなどを実感できる。
学部教育でユマニチュードを学ぶ意義は,臨床に出る前から患者とのコミュニケーションの基本的な考え方や実践方法を意識して学べる点にある。本校では今回,生徒のみならず多くの大学関係者にユマニチュードを紹介する場を設けることができ,また新たな学習方法を試す機会を得た。本校での取り組みを踏まえ,医療系学部教育におけるユマニチュード学習について紹介したい。
◆創始者によるユマニチュードの講演
イヴ・ジネスト氏と,日本でユマニチュードの普及・研究活動をしている本田美和子氏(国立病院機構東京医療センター)による1時間半の講演が,2022年7月22日の夕方に本校で行われた。感染対策のため,人数制限を行い申し込みを受け付けたところ,医学科3年生と看護学専攻3年生からそれぞれ約40人ずつの申し込みがあった。加えてユマニチュードをこれまで学ぶ機会がなかった理学療法学専攻,作業療法学専攻,検査学専攻の学生...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

伊東 美緒(いとう・みお)氏 群馬大学大学院保健学研究科老年看護学 准教授
1995年千葉大看護学部卒。2008年東京医歯大大学院保健衛生学研究科博士後期課程修了。博士(看護学)。東京都健康長寿医療センターにおいて観察調査を中心に20年以上認知症ケア研究を行ってきた。19年群馬大に赴任。11年執筆の「不同意メッセージへの気づき:介護職員とのかかわりの中で出現する認知症の行動・心理症状の回避に向けたケア」(老年看.)が同年,日本老年看護学会の研究論文奨励賞を受賞。『ユマニチュードと看護』(医学書院)の編集に携わる。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。