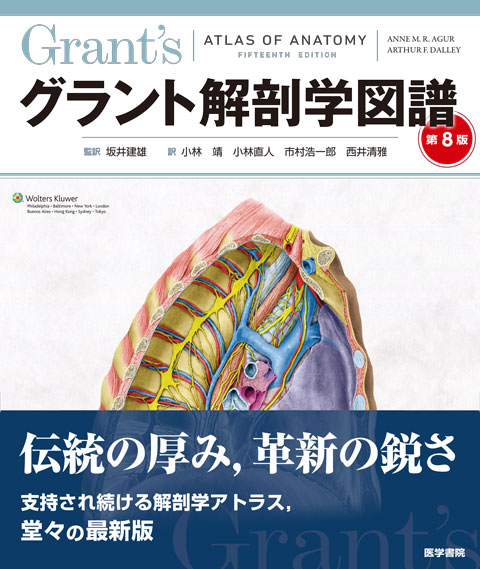MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.09.19 週刊医学界新聞(通常号):第3486号より
《評者》 荒川 高光 神戸大大学院准教授・リハビリテーション科学・解剖学
解剖学を図譜で学ぶ意義がここにある
解剖学を学ぶための書籍には,教科書的な書籍とともに図譜の書籍(いわゆるアトラス,実物写真などを含む)が存在する。解剖学をしっかり学びたい人にとっては,1冊で全てを網羅してほしいというのが本音であろうが,人体のしくみを1冊に収めるとなるとその書籍のボリュームは手に取れる常識的なサイズではなくなってしまう(古くなるが,第38版の“Gray’s Anatomy”のボリュームを見てほしい)。
解剖学の図譜には手書きのイラストが多く,写真だけで構成されているものは少ない。写真で伝える解剖学的情報は説得力が大であることは言うまでもない。しかし,実物標本の写真化には,標本の作製に関する倫理的問題があるほか,三次元で存在する実体を写真にする際に,どうしても見せられない部分が出てくる。手書きの図譜は,読者の理解を助けるために写真に写らないところを表したり,着色したり,許される範囲でデフォルメすることが可能である。その反面,手書きの図譜で問題となるのは「実物との違い」である。
本書『グラント解剖学図譜 第8版』には標本写真もある。頭蓋骨の写真群は美麗であり,理解を助けるものであろう。しかし,大半は歴史を感じさせる手書きの図譜である。「古い図であれば書き換えたほうがいいのではないか」と思うかもしれない。しかし,この手書きの図譜は,実物から作成したものであるだけでなく,もととなった標本が同じ状態で現存しているため,実物との差異を実際に確かめることができるものなのである。その歴史的意義は非常に重いと思う。
評者である私は,10年ほど前に著者の1人であるAnne M. R. Agur教授のもとに渡り,研究指導を仰いだ。University of Torontoで過ごしていたある日,私は研究室の一画に存在する「J.C.B. Grant Museum of Anatomy」の存在に気付いた。地下の研究室群の一角の部屋にあるMuseumには,本書籍の図譜と全く同じ状態で丁寧に剖出された実物標本が,図譜とともに展示されていた。University of Torontoの学生たちはそのMuseumで自習したり,友達と会話をしたり,グループディスカッションをしたりしているのである。他にも貴重な写真や標本が,Museumの中だけでなく廊下にも展示されていた。
身体の内部構造は,写真さえ撮って見せれば理解できると思うかもしれない。しかし,何の準備も予備知識もなく写真を見ても,「森を見て木を探せ」と言われているような状態になる(動脈や神経などは特に)。これが,世界中に解剖学の図譜が存在する理由である。本書の図譜には,そのもととなった実物標本が現存し,図譜が描かれて以来70年以上,標本と図譜が共存しているのである(本書中のいかにも歴史がありそうな手書きの図譜がそれにあたる)。
日本で,University of Torontoと同様の展示を行うことは難しい。日本で解剖学を学ぶ多くの人々は,人体の実物をすぐに観察できる環境にはない。だからこそ,歴史ある図譜を備えた本書は,実物から離れず,さらに理解しやすいという意味においても,大変よい学習の友となるだろう。
-
![安全に施行するためのESDテクニック[Web動画付]](/application/files/2616/4912/4212/108983.jpg)
安全に施行するためのESDテクニック[Web動画付]
- 宮澤 光男,大西 俊介 編
-
B5・頁176
定価:9,350円(本体8,500円+税10%) 医学書院
ISBN978-4-260-04861-3
《評者》 中本 安成 福井大教授・消化器内科
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。