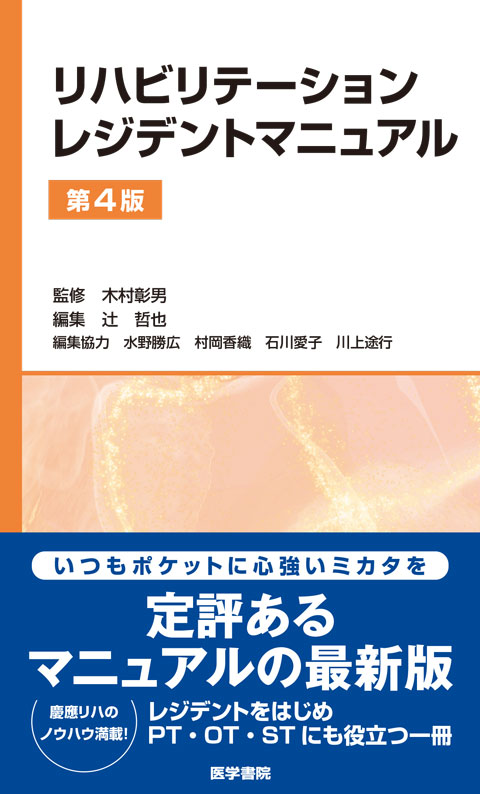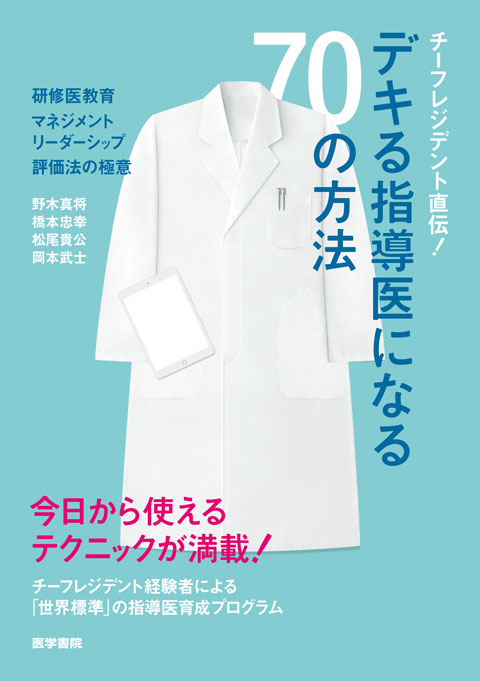MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.09.12 週刊医学界新聞(レジデント号):第3485号より
《評者》 山口 智史 順大先任准教授・理学療法学
いまだから必要なリハビリテーションが凝縮された一冊
神経疾患,整形外科疾患,内部疾患,悪性腫瘍など多種多様な疾患において,どのようなリハビリテーションが必要なのか? 最良のリハビリテーションを提供するには,どのような知識が必要なのか? 本書では,そういった不安や疑問を,日本のリハビリテーション医学・医療を牽引してきた慶大リハビリテーション医学教室に携わるリハビリテーション専門医が,明確にポイントを示しながら図表とともにわかりやすく解説している。
監修を務める木村彰男先生が序文で述べられているように,近年の医学・医療では,医療制度の改定により,疾患ごとの治療法や治療期間が制限され,画一的な医療が提供されるようになった。これはリハビリテーション医学・医療においても同様であり,日常生活動作の早期獲得のみを目的とした,生活動作の反復練習を主体とするリハビリテーションを目の当たりにすることがある。当然,生活動作の反復は重要であり,日常生活の自立度を高めるために必要である。しかしながら,リハビリテーション医学・医療の治療は,動作反復だけでよいのだろうか?
第I章では,この問いに答えるように「リハビリテーション医学・医療」について,重要な定義が記載されている。リハビリテーション医学は,運動障害(dysmobility)を来す疾患・病態の診断・評価・治療を専門とする医学の一分野であり,臓器・疾患別ではなく,運動障害をシステムとしてとらえる。さらに運動障害の原因は,①神経・筋・骨関節系(運動実行系),②呼吸・循環系(エネルギー供給系),③生活環境に分けられる。そのいずれかに問題がある場合には,疾患横断的に,リハビリテーション医学・医療の対象となる。そして治療として,廃用を予防するとともに,機能回復的アプローチにより,障害の的確な評価に基づいて,機能を最大限まで回復し,代償的なアプローチにより日常生活の自立度を高める。このリハビリテーションの治療概念は,医学・医療の進歩により,新しい治療が開発されたとしても,リハビリテーション医学・医療の根幹だと考える。
第II章では,リハビリテーション医学・医療を実践するための診断と評価が障害や動作レベルに分類され説明されている。さらに,第III章では,具体的な治療方法について記載されるとともに,治療後の効果判定にまで言及されており,より実践的な視点を学ぶことができる。第IV章では,リハビリテーション医学・医療の対象となることが多い疾患別の診断と評価,リハビリテーション治療がわかりやすく説明されている。第V章では,在宅リハビリテーション,行政や福祉用具の知識,さらに災害リハビリテーションにまで触れられている。
本書はポケットサイズで,物足りない内容なのではないかと考える方もいるかもしれないが,前述のように重要なポイントが全ての項目で端的にまとめられており,本当に必要な知識が記載されている。本書は,リハビリテーション科専門医をめざす研修医や医師,他科の医師,理学療法士,作業療法士だけでなく,養成校の学生においても必要な知識を提供してくれる一冊と言えるだろう。
《評者》 志水 太郎 獨協医大主任教授・総合診療医学
本邦初,チーフレジデント視座からの指導医向けテキスト
本書の役割は,巻末の対談で野木真将先生が仰っている「みんなの(リーダー育成のための解決法に対しての)共通認識を広げ,育てるツールとして役立ってほしい(p.331)」という言葉に集約されていると感じます。日米の伝統的なチーフレジデント制度を持つ研修病院でチーフレジデントを経られたメンバーらが,指導医として,ミドルレベルのマネジャーとして,教育者として,どのようなことに気を付けながら診療・教育・マネジメントを実践していけばよいかを指南してくださっています。しかし,押しつけのような形...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。