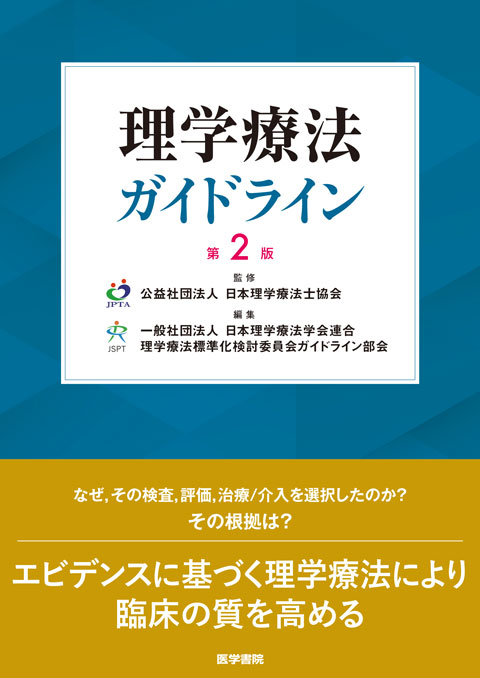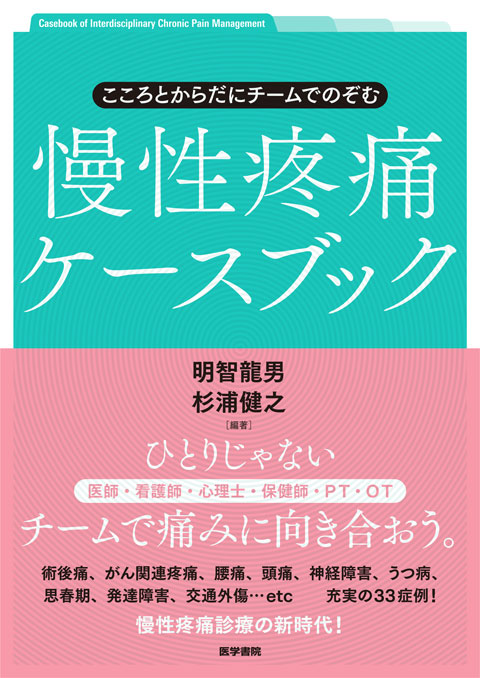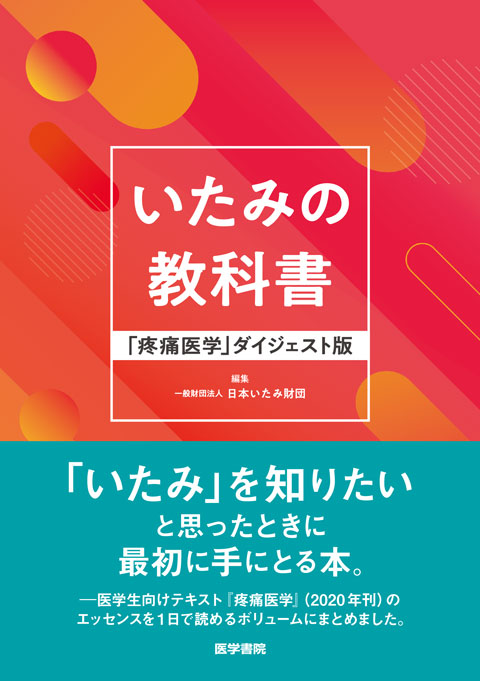腰痛を予防し,医療・介護従事者が働き続けられる職場づくりを
寄稿 田辺将也,高橋稚菜
2022.08.22 週刊医学界新聞(通常号):第3482号より
わが国における業務上疾病のうち,腰痛は全体の約6割を占めます。医療・介護職種においては約8割を占め,職場での予防的対策が急務です1)。これらの状況に鑑み,日本理学療法士協会が「2020 職場における腰痛予防宣言」を企画。医療・介護施設での理学療法士による腰痛予防の取り組みを募集しました。同施策の金メダル施設として認定された,当施設のノーリフティングケアを取り入れた腰痛予防の取り組みを紹介します。
医療・介護人材が健康に働き続けるための支援法
ノーリフティングケアは,近年認知が広がっている概念で,「持ち上げない・抱え上げない・引きずらないケア」を指します。リフト等の福祉用具の積極的な利用による,介護を受ける側と行う側の双方に負担の少ないケアの実施が狙いです。オーストラリアの看護師団体が取り組みを始め世界中に広まりました。
ノーリフティングケアと私(田辺)との出合いは,以前勤務していた榛名荘病院でのことでした。ある日,共に働いていた看護師さんが,日々の激務がたたり,手術患者として目の前に現れたのです。手術後の理学療法を担当する中,なぜ腰を痛めるまで仕事を続けたのかを伺うと,「他にも腰を痛めながら働いている職員はいるし,患者さんのことも好きだから,腰が痛くても頑張ってしまった」と返ってきました。
その言葉を聞き,「患者さんのために」との思いが強いあまり,医療・介護従事者が自分自身のことを二の次にしてしまう状況を痛感しました。そこで,腰を痛めて手術が必要になってから初めてかかわるのではなく,医療・介護従事者が健康に働き続けられるように早期から支援できることはないかと模索した結果,ノーリフティングケアにたどり着いたのです。
その後,異動した介護老人保健施設あけぼの苑は,構成する通所・一般棟・認知症専門棟の全てにリハビリ部門がかかわります。当初は人力によるケアに依存し,腰痛や肩こりなどの身体症状を抱えながら勤務する職員が多く,身体を壊し離職する職員も後を絶ちませんでした。そこで,共に働く仲間が健康に働き続けられる職場を目標に,ノーリフティングケアの導入に施設全体で取り組み始めました。
推進委員会を中心として施設全体で腰痛予防に取り組む
まず,看護師・介護士・理学療法士から構成されるノーリフティングケア推進委員会を発足し,現場の声を業務に生かせる仕組みを作りました。また,理学療法士が中心となり,腰痛予防講習会と題してノーリフティングケアに関する講習会を開催し(写真1),職員全員にノーリフティングケアの理解を促しました。

福祉用具を用いた移乗など,負担の少ないケアを推進委員会メンバーが職員に指導した。
◆施設内のリスク見積もりと改善
日本理学療法士協会が推進する「2020 職場における腰痛予防宣言!」では,職場で日々行う業務のリスク見積もりと改善提案が推奨されていました。そこで推進委員会のメンバーから,日々の業務で負担となる動作や環境を抽出してもらい,改善策を一緒に考えました。改善策実施後には,毎月開催する委員会で様子を共有し,効果判定を行いました。他の棟での取り組み状況を共有し互いに学ぶことで,次の改善に生かすことができました。
また,事務長とも課題を共有したことで,スライディングシートやスライディングボードなどの物品の購入がスムーズに進みました。入浴用リフトやスタンディングリフトなどの導入ハードルが高...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

田辺 将也(たなべ・まさや)氏 群馬パース大学リハビリテーション学部理学療法学科 助教
2014年群馬パース大卒後,榛名荘病院に勤務。18年に一般社団法人健康労働支援協会を設立し,労働者が健康的に働き続けられるための支援活動を展開。20年より現職。理学療法士。介護老人保健施設あけぼの苑にてノーリフティングケアを導入し,利用者と職員の両方を大切にした職場づくりをめざす。

高橋 稚菜(たかはし・わかな)氏 一般財団法人榛名荘 介護老人保健施設あけぼの苑
2017年高崎健康福祉大卒。理学療法士。19年より現職。榛名荘病院にて脊椎脊髄疾患患者のリハビリテーションに従事した後,介護老人保健施設あけぼの苑にてノーリフティングケア推進委員会の運営を担当。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。