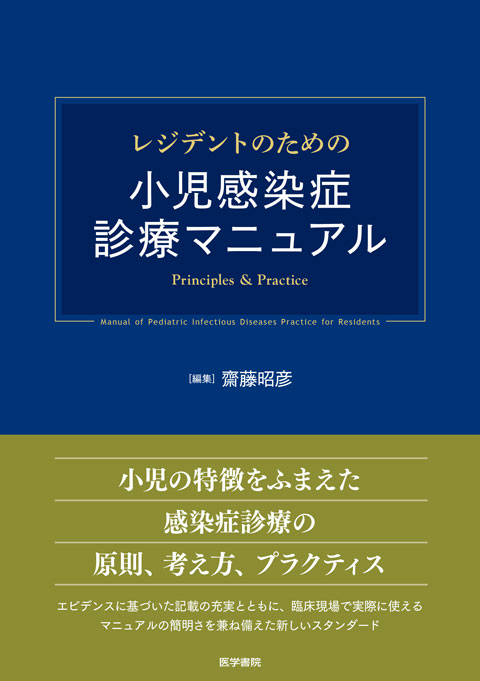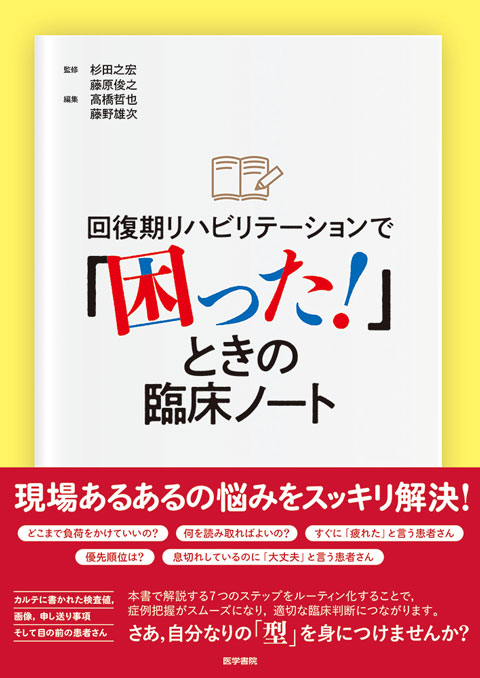MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.06.20 週刊医学界新聞(通常号):第3474号より
《評者》 谷口 俊文 千葉大病院講師・感染制御部・感染症内科
レジェンドがまとめる小児感染症診療のバイブル
一人の成人内科専門医および感染症専門医としての視点で本書を読んでみた。青木眞先生の『レジデントのための感染症診療マニュアル』もそうだが,本書の最も読み応えのあるところは「総論」だ。小児と成人の感染症診療のアプローチははっきりと違う。ここでは「小児の免疫の特徴」に多くのページを使っている。これらの特徴をしっかりと把握することにより,成人とは違う病態の気付きなども得られる。また基礎的な病態生理にもしっかりと触れられている。総論でここまで網羅している感染症の本はなかなか見当たらない。それだけ小児感染症診療の実践には基礎的な知識が必要であるということなのだろう。
読み進めると,所々に散りばめられたメモ欄には,小児科ならではの疾患の知識やクリニカル・パールが詰まっており,これを拾い読みするだけでも勉強になる。各論に入ると,さまざまな治療方法が感染症ごとにまとめられている。欧米で使用できる薬なども日本では使用できず,歯がゆい思いをされている先生方も,日本で小児感染症のトップランナーたちがまとめた実践的な抗菌薬使用方法は,読んで納得することができるのではないだろうか。
米国では基本は必須としつつも成人感染症の領域は「一般」「移植」「HIV」など細分化しており,例えば普段から固形臓器移植など免疫不全の患者の感染症に触れていないと苦手意識が出るのだが,日本の小児感染症医はオールマイティにこなさなければならない。本書を手に取りながら基礎を学ぶのは,最も効率的と思われる。「小児感染症の本」というのは英語でもなかなか良書に出合うのが難しいが,日本語でこれだけ臨床に実践的な内容が詰めこまれている本があるということ自体,素晴らしいのと同時に世界にもひけをとらない小児感染症領域のレベルを築き上げるのにも役立つだろう。また私が青木先生の本を手に取り感染症医を志したのと同じように,本書を手に取り小児感染症医を志す医学生や研修医も必ず出てくると思う。レジェンドが描く,将来の日本小児感染症診療の世界が楽しみだ。
《評者》 上野 勝弘 西記念ポートアイランドリハビリテーション病院リハビリテーション科統括科長
先輩セラピストの思考と後輩セラピストの課題が浮き彫りに
回復期リハビリテーション病棟は2000年4月に制度化され,これまで多くの脳血管疾患や整形疾患の患者さんに対して,回復期のリハビリテーションに取り組んできました。そして,この22年間で高齢化は進み,患者さんが抱える障害像は多岐に変化してきています。
2022年度の診療報酬改定では,「回復期リハビリテーションを要する状態」の対象に「急性心筋...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。