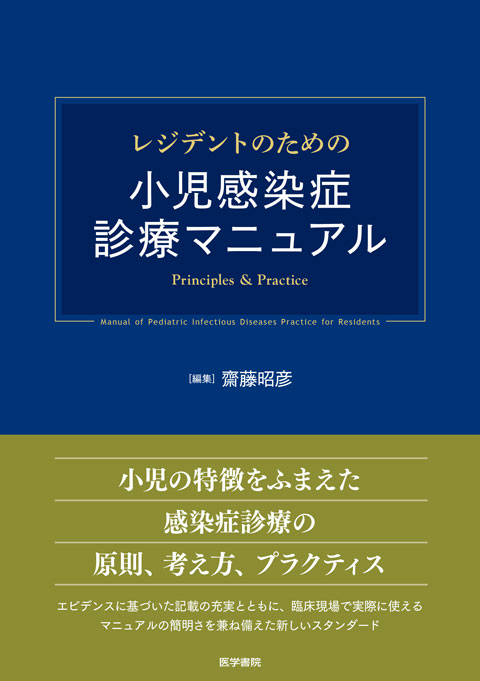MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.06.13 週刊医学界新聞(レジデント号):第3473号より
《評者》 青木 眞 感染症コンサルタント
小児診療に携わる病院総合診療医,家庭医にも必携の書
◆はじめに
本書の序にもあるように「小児は小さな成人ではない」。1984年に州立Kentucky大で内科初期研修を始めるに当たり,可能な限り感染症を中心に学びたいという希望を出した評者に冒頭から「小児の感染症には手を出すな」と警告を発したのは感染症内科の教授陣であった。米国では小児感染症科が小児総合診療的な特徴を維持しつつも,一種独立した部門として存在感を示していたのは,あれから40年近く経過した今も記憶に新しい。このたび日本人として初の米国小児感染症専門医となって帰国された齋藤昭彦先生が,多くの弟子,孫弟子と共に満を持して出されたのが本書である。
評者は通読し,いかに小児感染症について無知であったか思い知らされた。本書は小児科医のみならず,小児診療に携わる病院総合診療医,家庭医にも必携の書と言えるだろう。素晴らしい記述が多いが,紙面に限りがあり一部のみ紹介する。括弧内の太字は評者のコメント。
◆小児感染症診療の原則
p9:白血球数,CRP(C-reactive protein)値などは……その弊害として,その値だけが一人歩きしてしまい……。(このあたりは病態生理や鑑別診断の整理が不十分な中での検査など,程度の差こそあれ成人と同様)
p95:感染症と鑑別が必要な疾患。……多くの検査よりも,身体所見を繰り返し取ることが重要。
p96:非感染症の診断の仕方。非感染症についてよく知り,積極的に診断するのが一番の近道。
p131:感染症治療の評価は,感染臓器特異的な指標を用いて行う……。
p144:治療の効果判定,治療期間。クリニカルコースを知る。……バイタルサインの改善と炎症反応の低下はどちらが先なのか……。
◆小児科ならではの内容
p29:表1-15「原発性免疫不全症を疑う10の徴候」
p34~35:小児の感染症の特徴。年齢によって起因微生物が異なる。ウイルス感染症が圧倒的に多い。ワクチンで予防できる疾患がある。
p38~39:小児の感染症に関連する独特の検査所見がある。末梢白血球数の正常値は年齢が高くなるにつれて低くなる。尿中肺炎球菌抗原は鼻咽頭に常在する肺炎球菌により陽性になることが多い。
p49:小児のPK/PDの特徴。小児のほうが体組成に占める水分量が多い……水溶性薬剤の分布容積に影響を与え……。
p74:新生児の感染症の特徴。母体の……妊娠中や出産時の経過,在胎週数,出生時体重などが最も重要な情報となる。
p75:通常の妊婦の感染症の血液検査……。(プライマリケアの医師にも必須)
p79:風疹ウイルスは出生後,ウイルスの排泄が数か月続き,感染対策が必要。
p136:表2-15「遷延する発熱に対する検討事項」検査事項:成長曲線
p306:培養検査の原則。細菌性髄膜炎の罹患率は大きく減少している。そのため,3か月未満の発熱に対してルーチンで行われてきた……髄液検査は,見直すべき時期にある。
◆成人の感染症テキストにも欲しい内容
p58~59:Memo「β-ラクタムアレルギー」,表1-23「セファロスポリン系抗菌薬のR1側鎖の種類」。アンピシリンは……第1~2世代セフェムとR1側鎖が完全に同一……アレルギーがあった場合には,もう一方の使用は避けるべきである。(執筆者の顔が思い浮かぶ優れた内容)
p166:頭頸部感染症。中耳炎。抗菌薬を処方する前に,経過観察が可能かどうかを考える。
p389:Memo「腸管出血性大腸菌による急性腸炎を治療するべきか」。抗菌薬投与によるデメリットの方が大きい……。
p437:Memo「ユニバーサルワクチンの開発」。要注目である。(やがてコロナにも……)
p495:Memo「麻疹の診断にコプリック斑は有用か?」(風疹にもパルボにも出るのか……)
p722:Memo「2011年のHib,肺炎球菌ワクチンを含む同時接種後の死亡例から学ぶこと」(日本のワクチン行政のさらなる前進に期待します)
◆おわりに
齋藤先生は評者が30年前に帰国して最初に指導した研修医の一人である。聖路加国際病院の採用試験を一番で通過する秀才でありながら決して目立とうとはしない紳士であり,Establishmentを無用に刺激しない人格者である。しかし同時に困難に屈しない芯の強さを持ち,彼が仲間と共に構築した小児感染症専門医制度は,経験する症例の量も質も十分な医療機関のみを認定施設とし,試験内容も「受験すれば受かる」ようなものにはしなかった。そのため大学病院でも認定施設の資格を得られず,教授でも受験資格を得られないこともあったその認定試験は,合格率も7割前後であったと聞く。多くの逆風があったに違いないが,その中で本物を構築されたことは素晴らしいの一言に尽きる。コロナ禍による閉塞感に満ちたこの日本にも創造可能である,このような「空間」に希望を感じている。
-
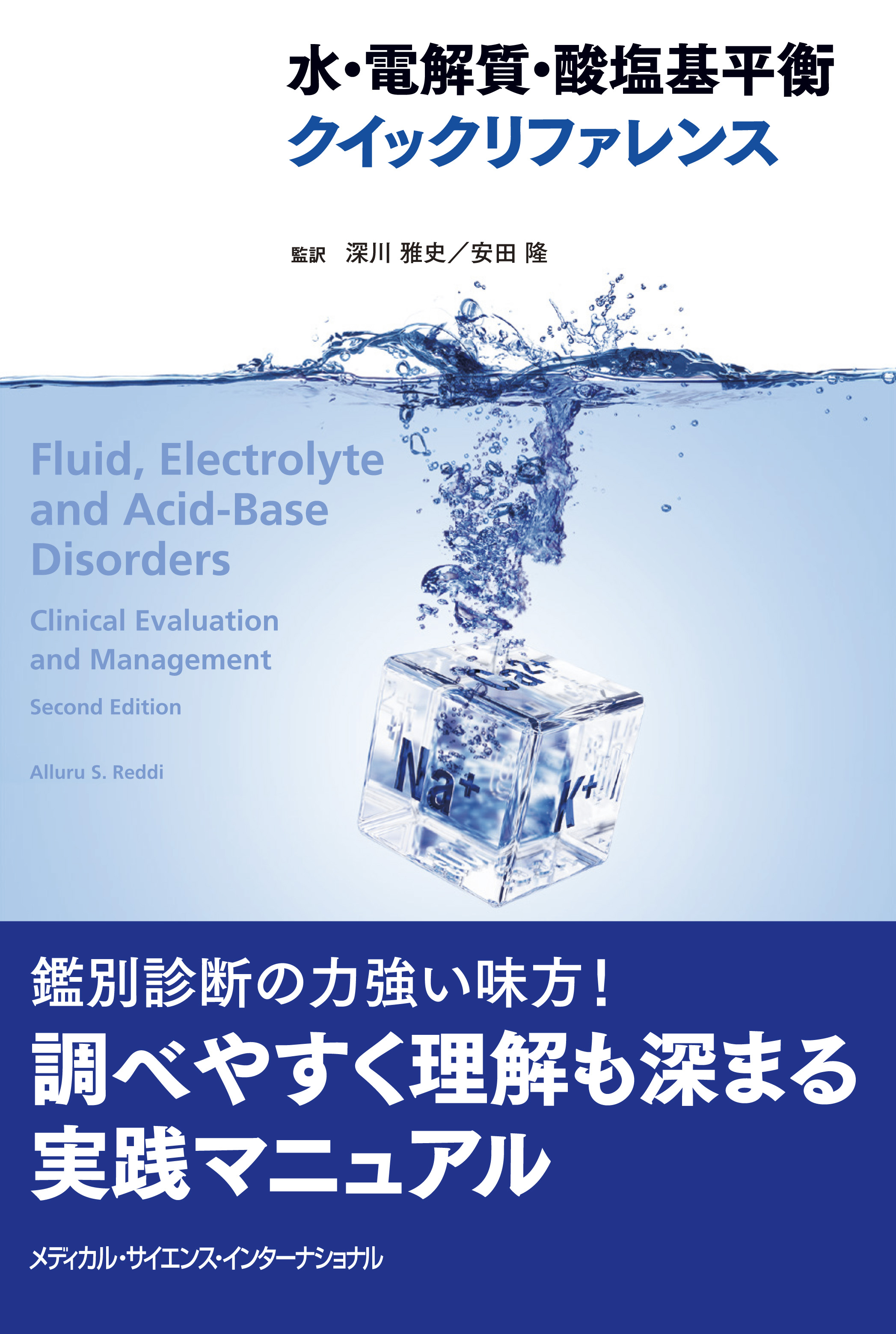
水・電解質・酸塩基平衡クイックリファレンス
- 深川 雅史,安田 隆 監訳
-
A5変型・頁540
定価:6,930円(本体6,300円+税10%)MEDSi
https://www.medsi.co.jp
《評者》 和田 健彦 東海大准教授・腎内分泌代謝内科/腎・血液透析センター長
専門家にも満足度が高く,学生でも取り組みやすい書
水,電解質,酸塩基平衡異常は,臨床のさまざまな場面で遭遇し,対応が求められる分野である。
したがって,この領域を勉強したいというニーズは非常に大きい。それは,学会などにおける若手向けの電解質企画が常に多くの聴衆を集めることからも実感できる。しかし一方で,多くの人が教科書に書かれている生理学的知識を理解・習得する過程で挫折を経験しており,わかりやすい「電解質本」が常に求められてきた。
そのようなニーズを満たすのが今回出版された『水・電解質・酸塩基平衡クイックリファレンス』である。
本書は米国で2018年に出版された“Fluid, Elect...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。