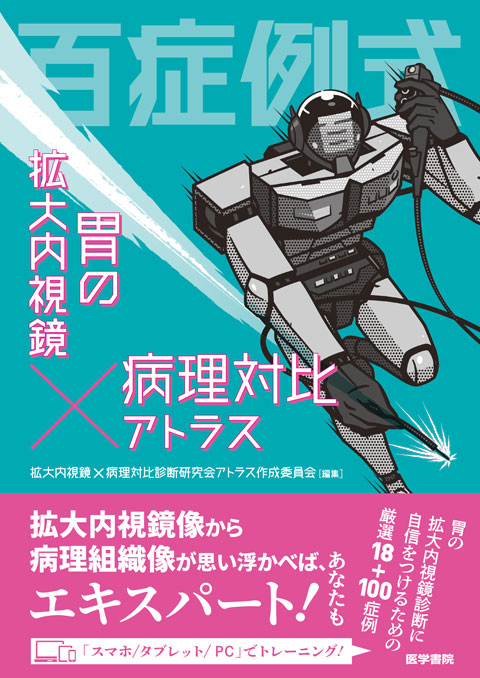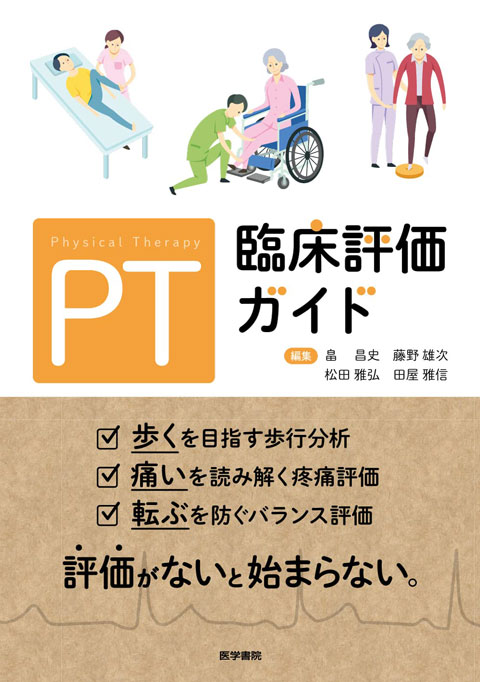MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.04.18 週刊医学界新聞(通常号):第3466号より
《評者》 柳澤 昭夫 京都第一赤十字病院病理診断科特別顧問/京府医大大学院特任教授・人体病理学/名誉教授
拡大内視鏡像と病理組織像が厳密に対比された一冊
胃癌の診断・治療の進歩は著しいものがある。拡大内視鏡の診断もその一つであるが,内視鏡診断において最も重要な点は,通常内視鏡観察による病変の認識である。病変の認識がない状態での拡大内視鏡観察や病理所見との対比は成り立たない。本書は,タイトル『胃の拡大内視鏡×病理対比アトラス』から推察されるように,内視鏡で観察された所見と病理組織像をより正確に1対1対応させることにより,内視鏡で観察される所見が,どのような組織形態により成り立っているか解説したものである。
正しい内視鏡診断は,観察されている内視鏡像がどのような病理組織像により成り立っているか理解することで得られることは言うまでもない。本書を読むことにより,内視鏡観察により認識された病変が,どのような病理組織像により成り立っているか理解することで,病変の認識・診断が容易になるとともに,より興味深いものとなることが期待できる。
内視鏡像と病理組織像の対比が行われている成書は多く出版されているが,本書のように内視鏡像と病理組織像がこれほど厳密に対比されているものはほとんどない。内視鏡像と病理組織像の対比は,内視鏡医と病理医との協力があって初めて成り立つものであり,両者の協力があって初めて,このような書籍が出版されることになる。本書を読んでいただければ理解されると思うが,実際にここまで厳密に拡大内視鏡像と病理組織像を対比した成書は,なかなか見当たらない。
「I章 総論」では,まず拡大内視鏡の基本が明確,簡潔に述べられており,拡大内視鏡像を容易に理解することを可能にしている。次に,内視鏡所見と病理組織像とのより正確な対比方法が述べられている。内視鏡的に切除された標本と病理組織像をより正確に1対1対応させることは決して容易ではないが,その方法がより丁寧にわかりやすく解説されている。ここで紹介している“KOTO method”は,内視鏡観察所見が病理組織像のどのような形態を反映しているかを正確に知る上で重要な方法であることが理解される。そして,この方法で対比された内視鏡像と病理組織像が具体的に提示されているが,両画像の関係が一目瞭然であることがわかる。
「II章 症例提示」では,通常内視鏡観察像,拡大内視鏡像,切除された標本像と“KOTO method”で1対1対応して得られた病理組織像が掲載されている。通常内視鏡観察像や拡大内視鏡像が,どのような病理組織像を基に形成されているかを理解する上で有用となることが期待される。
内視鏡像と病理組織像の対比は,あくまでも通常内視鏡観察で病変を見つけ,次のステップで生検などの確定診断を行い,内視鏡切除の治療が行われて可能となる。前述したように,通常内視鏡観察で病変を認識することが最も重要であることは言うまでもないが,このような内視鏡像で病理組織像を想定することにより,より正しい内視鏡診断が得られることが期待される。
最後に,本書は,「序」で新潟大地域医療教育センター・魚沼基幹病院消化器内科 八木一芳先生が述べられているように,西日本の京都,奈良,神戸,岡山,高知の若手からなる拡大内視鏡研究会での症例を基に作成されたものである。研究会での内視鏡医と病理医の熱心な意見交換があって初めてこのような成書が成り立ったことが行間(写真間)から伝わってくる。このような病理医と内視鏡医との親密なる意見交換が行われることにより,ほとんどの胃癌が侵襲のない治療法で治癒されるようになるために,本書が貢献することが期待できる。
《評者》 生野 公貴 西大和リハビリテーション病院
「生きた評価」を扱った若手PTにベストバイな参考書
「理学療法士は評価に始まり評価に終わる」。この言葉は,私が養成校の学生時代に教員の先生から事あるごとに聞かされた言葉である。当時はそ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。