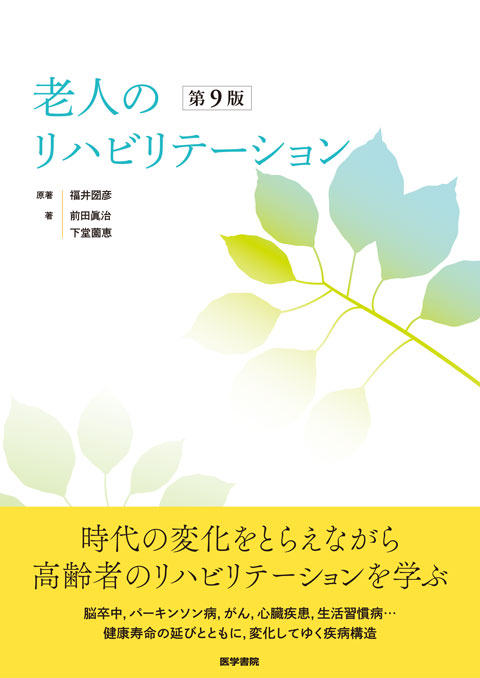MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.04.04 週刊医学界新聞(通常号):第3464号より
《評者》 川平 和美 鹿児島大名誉教授
高齢者のリハビリテーションへの知識と技術が得られる必読の書
日本は世界で一,二を争う高齢化率の超高齢社会である。人口の高齢化の進行の中で医療と福祉の連携体制強化に努めてきたが,今回の新型コロナウイルス感染症の拡大ではその備えの弱点が明らかになっている。また新型コロナウイルスに感染したハイリスクの高齢者への医療で並存疾患の悪化への対応に苦労していることから,高齢者へのリハビリテーション医療の体制強化への関心が高まっている。
本書は初版の発刊から50年近くの長い歴史を持つが,常に高齢者の疾病構造の変化とそれに伴う医療体制やリハビリテーション治療の変遷に対応して内容の拡充を継続しており,リハビリテーション医療に従事する者あるいはそれを志す者にとって,常に新しい知識と技術が得られる必読の書となっている。
高齢者への医療では疾病の診断と治療,さらにリハビリテーション医療と,切れ目なく必要な医療を提供することの重要性への認識が強まっている。特にリハビリテーション医療は,脳卒中や心不全など特定の疾患だけでなく,全ての診療科における基礎的な治療として不可欠な存在となっている。
本書はリハビリテーション医療が置かれた環境への対応の必要性を敏感に反映して,高齢者を取り巻く社会環境の変化や加齢に伴う身体機能の変化の概略を説明した後,医療における高齢者の尊厳を守ることへの配慮,さらには終末期におけるリハビリテーション医療の注意点を述べている。
「IV.主な老人性疾患のリハビリテーション」の章では,高齢者に多い中枢神経系から内臓,運動器の疾患までの幅広い疾患を取り上げているが,いずれの疾患についても多くの図表を用いて障害の特徴や治療内容の理解を容易にしている。特に脳卒中については,急性期医療の説明に多くの写真や図を用いて,急性期の手術室から回復期,慢性期への医療の流れを読者に実感させて,その流れの中で行われるリハビリテーション治療を詳細に説明している。さらに,その画像診断は豊富なCTやMRIを用いて詳細に説明し,病巣部位の診断を容易にしている。高次脳機能障害についても,失語や失行失認,認知症の症状と病巣の関連を,豊富な画像と図表でわかりやすく説明している点は特筆すべきである。
「V.知っておくべき多様な問題点」の章では,ノーマライゼーションの重要性,障害者心理への理解,廃用症候群,嚥下障害などリハビリテーション治療で配慮すべき事柄について,漏れなく取り上げている。
本書が多くのリハビリテーション医療の関係者に愛読されて,高齢者のリハビリテーション治療に残る課題が少しでも解消され,多くの障害を持つ高齢者に恩恵があることを願っている。
《評者》 野口 善令 豊田地域医療センター総合診療科
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。