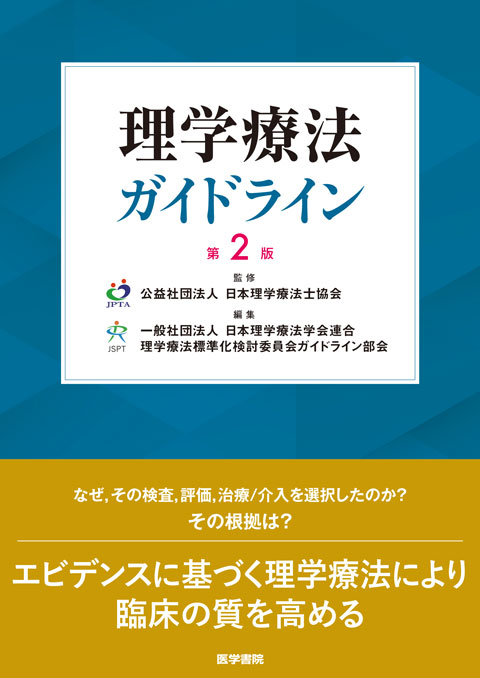MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.03.07 週刊医学界新聞(通常号):第3460号より
《評者》 吉田 俊子 聖路加国際大看護学部長
さまざまな医療職が自身の臨床に生かせる良書
現在の医療においてガイドラインは必須であり,医療の質保証の根幹にある。ガイドラインの作成には,当該分野を主導する学術団体などが膨大なエビデンスの集積と精選を行い,臨床での位置付けを示していく。医学のさまざまな分野からガイドラインが出され,多職種連携による包括的な介入の重要性が示されているが,目前の患者に対して各専門職がどのように介入していくのかに悩む場面も見受けられる。
この悩みを解決するためには,医療チームでの検討とともに,専門性や独自性にのっとった検討が重要となる。患者の個別の状況,施設の医療体制や人員配置などの影響のほか,同じ職種間においてもガイドラインの理解や介入方法に相違も見受けられる。エビデンスに基づく介入を臨床に落とし込むには,各専門職がどのような手法を用いるのか,どのような効果を得るのかを明確にしていくことが求められる。
『理学療法ガイドライン 第2版』は,「理学療法」のエビデンスを体系的に一冊にまとめたものである。21領域にわたり理学療法の臨床分野が網羅されており,総勢1400人が参画して作成されている。最新の臨床上の疑問についてCQを用いて表現されており,理学療法の見地から臨床上の疑問や課題を設定し,その疑問に答えることにより推奨を回答していく形をとっている。また,網羅的な論文を対象としたシステマティックレビューによる推奨と,理学療法士が専門家としての意見をまとめたステートメントで構成されており,外部評価には医師などの他職種のほか,患者会や一般市民も参加して作成されている。
現在の医療は多要素に行われていることから,理学療法としてのCQを示してその効果を評価していくことは,かなりの苦労があったのではないかと推察する。このCQの設定は,もちろん理学療法の観点で臨床上の疑問に沿ってまとめられているが,看護の疑問解決につながる内容が多く認められる。例えば,フレイル患者を対象とした運動療法は,看護師が普段接するフレイル患者の活動性をどのように考えていくかにつながっていく。このように,全般にわたり他職種の介入にも重要な示唆を得ることができる内容が示されている。
本書は,5年以上の歳月を費やして出版されているが,医療の目覚ましい進歩により,まとめる経過途中では変化する医療へのさまざまな対応や審議があったのではないかと思う。理学療法に携わる医療者の熱意と統合していく力,結果を体系づけて示していく力に,心より敬意を表したい。診療報酬を獲得していくためにも,このエビデンスの集積は重要な課題である。多彩な専門領域をどのように集積してエビデンスを示して臨床につなげていくか,本書から学ぶことは大きい。理学療法士のみならず,さまざまな医療職が自身の臨床に生かしていくことができる良書であり,ぜひ手にとって活用していただきたいと思う。
-
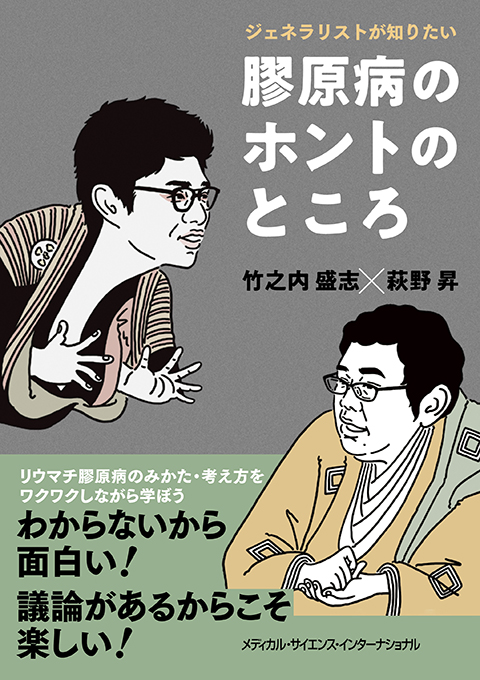
ジェネラリストが知りたい膠原病のホントのところ
- 竹之内 盛志,萩野 昇 著
-
A5・頁244
定価:3,960円(本体3,600円+税10%) MEDSi
https://www.medsi.co.jp
《評者》 倉原 優 近畿中央呼吸器センター呼吸器内科
広がれ,咲け,膠原病診療の花
「底なしの知識を持つ萩野昇先生を読者の皆さんに披露したい」という竹之内盛志医師のまえがきがあるが,萩野医師はまさに知の巨人である。スウィフトの“ガリバー”どころではない,進撃の巨人でいう“鎧の巨人”クラスである。実に,衝撃的な本だった。対談し続けていただければ,無限に医学書が作れるのではないか,そんな気すらする。
対談内容を補足解説するために,全体的に小さい文字であるが余白を余すことなく使った,コスパの良い仕上がりにもなっている。どう考えても,お値段以上である。
私は呼吸器内科医で,膠原病科医とのやりとりは基本的に「間質性肺疾患」という窓を通して行うが,小さな窓から膠原病の世界を見ても,せいぜい肺と関節が燃えていることくらいしかわからない。目の前の患者アウトカムを最良のものにするためには,双方密なコミュニケーションが必要になる。それぞれの臓器の専門科医は,膠原病に関して「こんなもんでいいだろう」と妥協すると,知の成長の骨端線は閉鎖される。それゆえ,「とりあえずプレドニゾロンや免疫抑制剤を投与してみるか」みたいな膠原病診療はいまだに多くの診療科で行われているのが現状である。「Time is lung.」などの内科的エマージェンシーの場合は迷わず投与してよいと思うが,漫然とこれらを継続されている慢性疾患患者はまだ国内にたくさんいるかもしれない。
私が勤務する病院のように,膠原病科医がいない施設は多いだろう。そのため,軽く相談したいとき,外部の膠原病科医に電話で「これってどうでしょうか?」と聞くことが多いのだが...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。