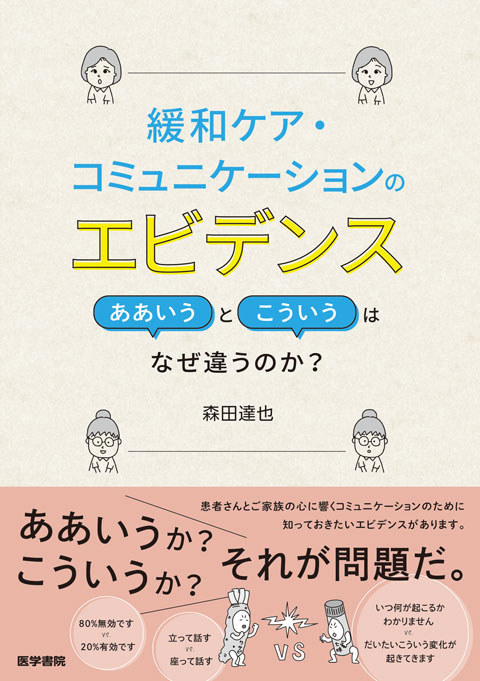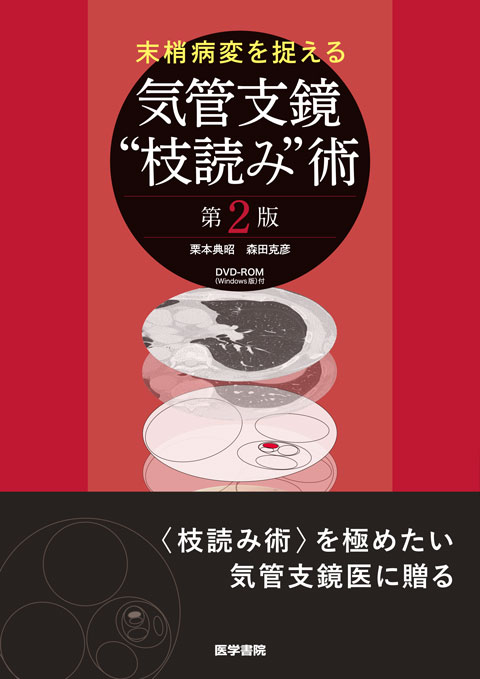MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.01.17 週刊医学界新聞(通常号):第3453号より
《評者》 勝俣 範之 日医大武蔵小杉病院腫瘍内科部長
また森田先生のファンになってしまった!
「患者さんとのコミュニケーション」というなかなかエビデンスが成り立ちにくい分野で,第一線で臨床,研究をされている森田達也先生のこの本を一気に読ませていただきました。森田先生たちが,自ら臨床の現場で成し遂げた研究の成果,エビデンスと,それに対する解説,また臨床現場での用い方まで,詳しく楽しく物語風に描いてくださったので,非常にわかりやすく,かつ実践的であり,読み終わった時には赤ラインと付箋でいっぱいになってしまいました。この本は,がん医療にかかわる医師や,医療従事者の人たちにぜひ読んでほしい。特に,がん治療医,腫瘍内科医に必読の本と思います。
われわれがん治療医が診療現場で患者さんによく言ってしまうセリフに,「いつ何が起こるかわかりません」「どちらにするか,決めてください」「もう治療はありません,できることはありません,ホスピスを勧めます」「余命はわかりません」「余命は〇か月です」などがありますが,これらの言葉掛けがあまり好ましくないコミュニケーションの例として,エビデンスを交えて紹介されています。そして,どのように対応したらよいのか,具体的な例が示されているので,非常に実践的です。日頃,臨床医がよく使っている言葉が,患者さんにとってはとても傷つく言葉であったり,好ましくない言葉であったりすることにあらためて気付かされ,目からうろこでした。明日からの臨床にもすぐ使える内容と思います。
以前,森田先生にお会いした際,まだ映画化される前だった『君の膵臓をたべたい』(住野よる著)を読むように紹介されました。この小説は,主人公が難病になりながらも日常生活に喜びを見つけて生き生きと生きる姿に加えて,人生の不条理を描いたものですが,森田先生の文学への造詣の深さにも感心いたしました。本文の途中に出てくるコラムにも文学的要素が反映されており,また森田先生のファンになってしまいました。特に,コラムの中の「(文学や哲学の領域では)医学研究がわざわざ質の高いインタビュー研究やら代表性の高い集団のコホート研究やら新規性の高い実験心理研究やらをしなくても,死を前にした人間の体験はあらかたのことが,『わかって』いるのではないのかという気にもなることが多くあります」との言葉がとても印象的でした。
-

即戦力が身につく頭頸部の画像診断
- 尾尻 博也,加藤 博基,久野 博文 編
- B5・頁484
定価:8,580円(本体7,800円+税10%) MEDSi
https://www.medsi.co.jp
《評者》 興梠 征典 産業医大名誉教授/門司メディカルセンター院長
工夫の塊のような素晴らしいケースレビュー
本書に対する期待は,尾尻博也先生をはじめとする編集者,ならびに分担執筆者の顔ぶれを見ただけで高まった。よくあるケースレビューの体裁を取っているものの,随所にこだわりがみられて,やはりひと味違う本に仕上がっていた。
入門編,実力編,挑戦編というレベル別の構成が面白い。トライしてみたところ,入門編の中にも決して簡単ではない症例があるので,読者が自信をなくす必要はない。一方,挑戦編も全く歯が立たない訳ではない。いずれにせよ,クイズ感覚でどんどん読み進めていけるのが,本書の強みであろう。系統的な教科書だと,ある程度読むうちに,眠くなる人も多いのではなかろうか。
どんどん読んでいけるのは,解説の記載を徹底的に「ダイエット」した効果もあると思う。これだけ知っておけばよいという割り切りが気持ちよい。もっと詳しく知りたいときには,いわゆる成書を読めばいい。「序」に書かれているとおり,Q & A方式は本書の目玉であると思う。Qに対しまず自分で考えるという作業を通して,とても効率よく,必要な関連知識を習得できる。
そして全136症例を制覇できたころには,「とっつきにくい,自分には無理だ,できれば読影したくない」などと思っていた頭頸部画像診断を,進んでやりたくなっているであろう。実際にレポートを書く際は,本書の「所見」欄を参考にすればよい。冗長を避けて,簡潔に必要な所見を記載するコツがつかめる。ひと通り「力試し」を終えた後は,部位別に疾患名が記載されている別目次を使えば,通常の教科書のような使い方もできる。「一粒で二度おいしい」という古いキャッチフレーズを思い出した。
私は常々,若い放射線科医に,系統的かつ包括的に記載された「ボリュームのある」専門書を読みなさいと言ってきた。ケースレビュー的な本だと,どうしても知識が断片的になるきらいがある。しかし,こういう工夫の塊のような素晴らしいケースレビューが出てくれば,忙しい画像診断医,専門医をめざす人たちにとって本当にありがたいことである。
些細なことだが,読んでいて一つだけ気になった。試験問題を解くときのように,症状と画像のみで診断を考えようとしていると,症例によって診断(正解)がすぐ目に入ってしまうのである。私は,英単語を勉強していた昔を思い出しながら,手元にあったハガキで正解を覆って,読んでいった。本書の体裁上やむを得ないと思われるものの,何か工夫ができればさらに素晴らしい。
放射線診断専門医をめざす人たちはもちろん,全ての画像診断医にとって間違いなくお薦めの書である。
《評者》 森谷 浩史 大原綜合病院放射線科・副院長/画像診断センター長
気管支分岐を立体的に把握する秘術を惜しみなく伝授
栗本典昭先生に初めてお会いしたのは日本気管支学会(現在の日本呼吸器内視鏡学会)だったと思います。超音波を用いた気管支壁構造や縦隔リンパ節の研究内容を教えていただき,その緻密さに感銘を受けました。私がX線CTを使った仮想内視鏡の検討を行っていた頃です。あの時見せていただいた超音波画像に匹敵するような微細形態をCTでも描出できないかと今でも夢想しています。
先日,栗本先生の『気管支鏡“枝読み”術』を拝読し,とても懐かしく感じました。私は,1982(昭和57)年から2年間,坪井栄孝先生が開発した坪井式末梢病巣擦過法を習得するために郡山市の坪井病院で研修を受けました。当時の研修方法は,複数枚の断層写真からトレーシングペーパーに気管支走行をトレースして,立体的なトレース像を作成することでした。情報が足りなければ気管支造影を行いました。そうやって分枝名を記載した詳細な気管支樹を作成した後に実手技を行っていました。「枝読み術」はこのトレース作業を気管支内に視点を置いて行...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。