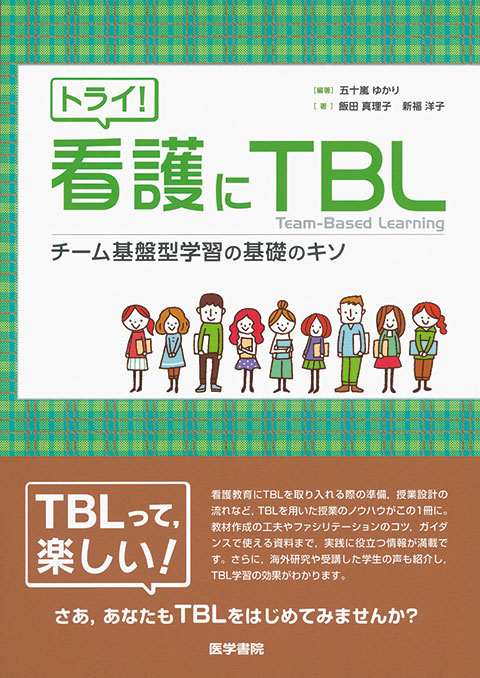若手研究者をエンカレッジ!
学際的・国際的活動のススメ
対談・座談会 新福 洋子,岸村 顕広,安田 仁奈,岩崎 渉
2021.12.13 週刊医学界新聞(看護号):第3449号より

「近年,研究者には学際的・国際的な社会貢献活動が強く求められている」。研究者が担う役割の拡大をこう表現したのは,国際保健看護学分野で活躍し,2020年にWHOから「世界の卓越した女性の看護師・助産師のリーダー100人」に日本人で唯一選ばれた新福洋子氏だ。日本は学際的・国際的活動を通じて世界でのプレゼンス発揮が期待される一方で,若手研究者によるこれらの取り組みが十分ではない現状がある。では自身の研究領域や国家という「枠組み」を飛び越えて若手研究者が活躍するには,どのような後押しが必要だろうか。
新福氏を司会に,Global Young Academy(GYA,MEMO)の現役メンバーかつ日本学術会議若手アカデミー(YAJ)のメンバーとして複合的・分野横断的な課題解決に向けて精力的に活動する4氏が,若手研究者がリーダーシップを発揮して学際的・国際的な研究に向き合う意義と,促進の方策を話し合った。
新福 私たち4人はそれぞれの研究領域は異なるものの,科学の知見を生かした国際会議での政策提言や学際的なアウトリーチ活動,研究成果の社会実装など学際的・国際的活動を実践してきた仲間です。岸村さんの専門は応用化学,安田さんは海洋分子生態学,岩崎さんはバイオインフォマティクス,そして私は国際保健看護学。GYAやYAJに参加せず自身の研究領域のみに取り組んでいたら,私たちは出会っていなかったかもしれません。今回の座談会を通じて,若手研究者に期待したい学際的・国際的取り組みについて,議論を深めたいと思います。
自分の研究領域から一歩外に踏み出してみよう
新福 近年,研究者が担うべき役割は拡大し,自身の研究に加えて他領域の研究者と協働した学際的・国際的な社会貢献活動が強く求められています。これらに率先して力を注いできた3人は,若手研究者が活動に取り組む意義をどう考えますか。
岸村 自分が身を置く領域や環境を背負って立つ覚悟で「外に出る」経験を若手のうちに積めるのは,かけがえのない財産になると考えています。私の場合は応用化学の専門家を代表して他分野と連携し,日本を代表して見解を示して諸外国と共に活動に取り組みます。これは大きな緊張感を伴うと同時に,視野を広げて自分の状況を見つめ直すきっかけになりました。
岩崎 「外に出る」結果として,学問領域や国を越えた仲間との強固なネットワークを構築できるのも魅力的ですね。国際会議に参加したり幅広い学問分野の研究者と議論したりする中で,他国や異分野の優れた若手研究者とのコネクションが得られました。学問の学際化・国際化が急速に進む現代社会において,これらの活動が近い将来に自分の研究に還元されることもあると思います。今はその「種」をまいている状況です。
新福 視野が広がることで,自分の研究にも幅を持たせられますね。例えば私は2019年にタンザニアで妊産婦の死亡率を低下させるため,現地の助産師に知識を届けるアプリ開発を行いました1)。看護学に軸足を置きつつ学際的な活動で得たアクセシビリティなどの工学的な視点が加わったことで,ユーザーにとってより使いやすいアプリに結び付きました。
また,日々の研究ではなかなか出会えない若手研究者とつながりを持てるのは大きなメリットです。学際的・国際的活動に積極的にかかわる研究者は,社会貢献したいとの強い公共心を持っています。こうした出会いはモチベーションの向上にもつながるでしょう。
安田 3人に付け加えるならば,国際会議に参加することで,発出されるステートメントにコメントできる点でも意義深いです。GYAやYAJでは,国際会議にメンバーを派遣して領域を越えた研究者による合意形成をめざします。この時に研究者としての価値観や経験も踏まえつつ,科学的知見に基づく意見を述べる機会を得られるのです。国際的なステートメントを決定事項として受け取るのではなく,決定プロセスから参画することで,より高い解像度で施策の内容を理解できます。
新福 そうですね。私もこれまで,G7の科学アカデミー会合であるGサイエンス学術会議2)や,G20の科学アカデミー会合であるS20など多くの国際会議に出席し,ステートメント作成に関与してきました。科学的な知見に基づいて見解を示し政策への反映をめざすのは,研究者としての大きなやりがいを感じられます。
国際舞台でリーダーシップを発揮して存在感を示す
新福 日本の若手研究者が国際会議に参加して議論のイニシアチブを取るのは,国際社会における日本のプレゼンスや信頼の向上に大きく寄与すると考えています。将来,大規模な学際的・国際的共同プロジェクトを日本がリードすることにもつながるでしょう。
岸村 同感です。これまで日本の若手研究者が国際会議でリーダーシップを発揮した具体例として,2019年の筑波会議(註1)3)と同年の世界科学フォーラム(WSF,註2)がありますね。GYAとYAJの枠組みからは安田さんと私が参加し,セッションを主体的に企画・運営しました。各国の研究者や政策立案者,産業界のリーダーなどが海洋プラスチック問題などを例に領域横断的な議論を交わし,SDGs(持続可能な開発目標)というグローバルな目標達成の方略を探りました。
安田 国際会議で自らセッションを立ち上げる経験は,課題を俯瞰する一段高い視点の獲得につながりました。学際的・国際的な問題の多くは複合的なファクターが絡み,ステークホルダーごとに重視する内容が異なります。多岐にわたる利害関係の調整を通じて,多角的な見かたを強く意識するようになったのです。
岩崎 新福さんが先ほどお話ししたGサイエンス学術会議でも,日本は存在感を示せたと思います。この会議ではいくつかのテーマに基づき,G7サミットに向けた政策提言を行います。2019年にはGYAとYAJの枠組みから新福さんと私が参加しました。各国の科学アカデミー会長やノーベル賞受賞者が居並ぶ会議であり,若手研究者の出席は珍しかったため,私たちの参加は「日本が若手研究者を重視している」との印象を各国参加者に与えました。
新福 他国の科学アカデミーにおける若手研究者参加の促進に結び付きましたね。当時,私は市民と研究者の協働による活動であるシチズンサイエ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

新福 洋子(しんぷく・ようこ)氏 広島大学大学院医系科学研究科国際保健看護学 教授=司会
2002年聖路加看護大(当時)卒。助産師として勤務後,10年米イリノイ大シカゴ校大学院看護学研究科を修了。博士(看護学)。聖路加国際大助教,京大大学院医学研究科人間健康科学系専攻家族看護学講座准教授などを経て,20年より現職。専門は国際保健看護学。日本学術会議若手アカデミー前副代表。共著に『トライ! 看護にTBL』(医学書院)など。

岸村 顕広(きしむら・あきひろ)氏 九州大学大学院工学研究院応用化学部門 准教授
2000年東大工学部化学生命工学科卒。05年同大大学院工学系研究科化学生命工学専攻修了。博士(工学)。同大大学院工学系研究科マテリアル工学専攻助教などを経て,13年より現職。専門は応用化学。日本学術会議若手アカデミー前代表。20年より九大にて総長補佐を兼任。

安田 仁奈(やすだ・にな)氏 宮崎大学農学部海洋生物環境学科 准教授
2003年早大理工学部応用化学科卒。08年東工大情報理工学研究科情報環境学専攻修了。博士(学術)。宮崎大農学部海洋生物環境学科助教,同大テニュアトラック推進機構准教授などを経て,19年より現職。専門は海洋分子生態学。日本学術会議若手アカデミー副代表。日本サンゴ礁学会代議員。

岩崎 渉(いわさき・わたる)氏 東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻 教授
2005年東大理学部生物化学科卒。09年同大大学院新領域創成科学研究科情報生命科学専攻修了。博士(科学)。同大大気海洋研究所講師,同大大学院理学系研究科生物科学専攻准教授などを経て21年より現職。専門はバイオインフォマティクス。日本学術会議若手アカデミー代表。ISCB(国際情報生物学会)理事。
いま話題の記事
-
取材記事 2026.02.10
-
あせらないためのER呼吸管理トレーニング
[ミッション4] HFNC vs. NPPV――病態生理に基づいて使い分けよう連載 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。