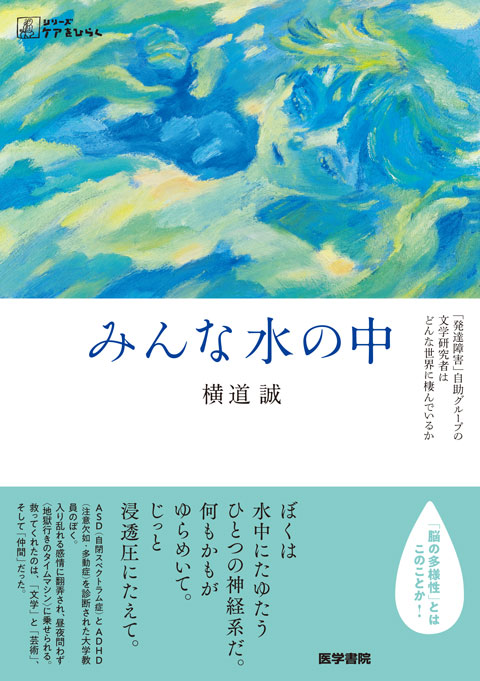ニューロダイバーシティで「発達障害」をとらえ直す
対談・座談会 横道 誠,村中 直人
2021.11.15 週刊医学界新聞(通常号):第3445号より

近年,脳・神経科学の研究が大きく進んだことを背景に,ニューロダイバーシティへの関心が世界的に高まっています。ニューロダイバーシティとは,脳や神経,それらに由来する個人レベルでのさまざまな特性の違いを,多様性ととらえて相互に尊重し,社会の中で生かしていく考え方(MEMO)です。この考え方は,「発達障害をどう治療するか」から「発達障害が障害にならない社会をどうめざすか」へのパラダイムシフトになり得るのではないでしょうか。
発達障害当事者の立場からニューロダイバーシティの重要性を考察して『みんな水の中―「発達障害」自助グループの文学研究者はどんな世界に棲んでいるか』(医学書院)を上梓した横道氏と,発達障害支援の実践者である村中氏。2人がニューロダイバーシティの意義やこの概念を浸透させることで実現したい社会の在り方について語り合いました。
横道 私はドイツ文学や民間伝承分野の研究を専門とする大学教員であり,ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如・多動症)の発達障害当事者でもあります。「何となく周りの人と異なる」感覚を長年抱えながらも,ずっと大学教員として勤務してきました。2019年に適応障害で休職した時に初めて,自分が発達障害者だとわかったのです。
村中 これまで私は臨床心理士・公認心理師として発達障害児の支援に当たってきました。かかわればかかわるほどに,発達障害児の特性は多様性に満ちており,発達障害を正しく理解するために脳・神経科学や認知科学などを学ぶ必要性を感じました。学習の過程で出合ったのが,ニューロダイバーシティの概念です。これは今では支援者としての私の基本スタンスになっています。横道さんは,どのような経緯でニューロダイバーシティを知ったのでしょうか。
横道 休職中に,発達障害者同士のつながりである自助グループ活動に参加する中で,ニューロダイバーシティの考えに触れたのがきっかけです。関心を持ってさまざまな文献を調べるうちに,村中先生のご著書『ニューロダイバーシティの教科書―多様性尊重社会へのキーワード』(金子書房)を読み,対人支援者からの発達障害者に対する人間理解の深さと温かさに感銘を受けました。ニューロダイバーシティに関する研究は海外で先行しており,日本ではまだ普及していません。『ニューロダイバーシティの教科書』は対人支援者の立場から,私が出版した『みんな水の中』は当事者の立場から,それぞれニューロダイバーシティが秘める可能性を描き出した先駆けと言えます。
発達障害者の生きづらさを引き起こすのは何か
村中 横道さんは『みんな水の中』で,発達障害当事者でしか体験し得ない「水中世界」に包まれながら生きていると表現していますね。あえて言葉にするとどのような感覚なのか,あらためてお話しいただけますか。
横道 現実がいつも夢に浸されていて完全に覚醒し切れない感覚です。私がそこから眺める現実世界はASDとADHDの影響を受けて,まるで水中に存在するかのようにぼやけて揺らめいています。私はマジョリティである定型発達者と異なる世界を体験しているのです。
村中 そのために感覚のズレやそれに起因する対人関係の困難を感じるのですね。具体的にはどのような困難があるのでしょうか。
横道 冒頭にお話しした通り,私はASDとADHDの診断を受けています。そのためASDの特徴である共感の困難,ADHDの特徴である注意力の欠如などが問題となります。仕事面では会議の場の雰囲気を感じ取って自然な笑顔を浮かべたり,他者と視線を合わせたり,落ち着いて座り続けたりするのが困難であり,周囲から奇異の目で見られることがしばしばです。生活面でも多くの困難があります。料理や掃除をしていると,ADHDに起因する脳内多動のためにさまざまな思考が渦巻いて脳内を圧迫します。終わった頃には情報が処理し切れずに疲弊してしまうのです。影響を半日から数日は引きずり何も手に付かなくなるなど,日常生活に重大な支障を来します。
村中 ニューロダイバーシティの観点では,横道さんの困り事は人に内在する「障害」ではなく,「脳や神経由来の特性が持つ多様性」が社会環境下で引き起こす困難としてとらえられます。そして神経学的マジョリティの定型発達者とマイノリティの発達障害者は,脳・神経由来の特性レベルでコミュニケーションや行動様式などの在り方が異なると考えるのです。これは「文化が違う」とも表現できます。つまり定型発達者と発達障害者はそれぞれの文化を持っており,それらに優劣は存在し得ません。
横道 私たち当事者の目線からは,ニューロダイバーシティは「多様性が存在する」と主張するだけでなく,「マイノリティの文化を持つ発達障害者を定型発達者と同様に尊重してほしい」という積極的な意味合いを持ちます。これは全ての人の多様性が尊重される社会をめざすキーワードと言えるでしょう。
村中 そうですね。とはいえニューロダイバーシティは新しい考え方であり,社会に標準装備されるにはまだ時間を要すると思います。残念ながら現代社会では,発達障害者の特性は治療すべき障害や能力の欠如とみなされます。多様性として尊重される場合は少ないでしょう。
横道 私たちはマイノリティゆえに定型発達者とコミュニケーションを行う上でさまざまな軋轢が起こり,理不尽とも思える多くの生きづらさに直面します。それは現代社会では,マジョリティである定型発達者によって「この時はこのように振る舞うのが当たり前だ」という価値規範や行動規範が形成されており,私たちは発達特性上それに沿った行動が難しいためです。また,マジョリティの社会に適応しようとするあまり過度なストレスを抱えて生きるうちに,私のように適応障害などを引き起こすことも少なくないのです。
生きづらさを軽減するための4つの支援ネットワーク
横道 ニューロダイバーシティが十分に浸透していない現状では,私たちマイノリティはマジョリティのためにデザインされた社会を生きることになります。そのためには,さまざ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

横道 誠(よこみち・まこと)氏 京都府立大学文学部欧米言語文化学科 准教授
2002年京都府立大文学部文学科(西洋文学専攻)卒。07年京大大学院人間・環境学研究科共生文明学専攻(文明構造論分野)博士課程指導認定退学。京都府立大講師などを経て16年より現職。21年よりウィーン大(東アジア学研究所)客員研究員を兼任。19年に適応障害で休職し,ASDとADHDの発達障害の診断を受けるも20年に復職。近著に『みんな水の中――「発達障害」自助グループの文学研究者はどんな世界に棲んでいるか』(医学書院)。

村中 直人(むらなか・なおと)氏 一般社団法人子ども・青少年育成支援協会代表理事
2000年大阪市大生活科学部人間福祉学科卒。04年京都文教大大学院臨床心理学研究科修了。臨床心理士,公認心理師として発達障害児の支援に当たる。20年より現職。「発達障害サポーター’sスクール」の立ち上げと運営に携わり,発達障害支援者の養成に力を注いでいる。近著に『ニューロダイバーシティの教科書――多様性尊重社会へのキーワード』(金子書房)。日本ニューロダイバーシティ研究会発起人。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。